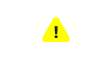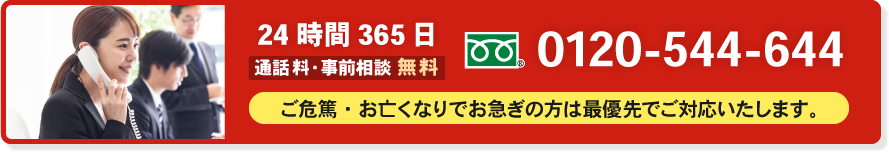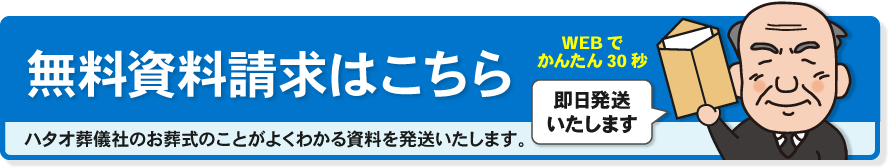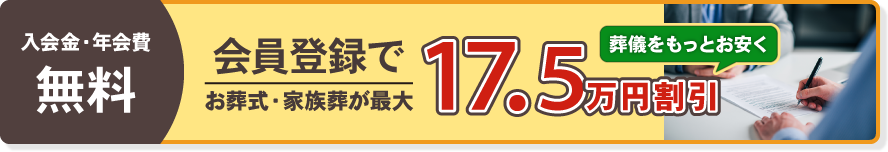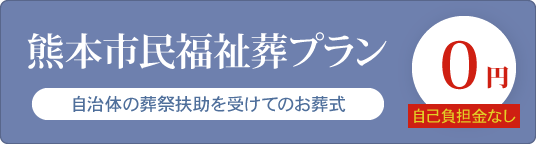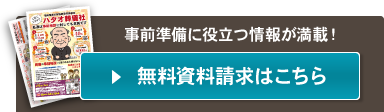新着情報
2025.03.07
警察署での遺体安置から引き取りまで、緊急時の対応と流れ
遺体が警察署に安置されるまでの流れ
死亡確認と警察への連絡
遺体が警察署に安置される流れは、まず死亡が確認されることから始まります。自宅や公共の場など病院以外で死亡が確認された場合、事件性や事故の可能性などを考慮して警察に連絡することが必要になります。この際、まず救急車を呼び、医師による死亡確認を受けることが一般的ですが、その後、状況によっては警察が現場に駆けつけ、必要な調査を行います。死亡確認後に警察が介入するのは、死因や状況に関して疑義がある場合や、自然死以外の可能性がある場合です。
検視の開始と実施内容
警察が現場に到着すると、「検視」が開始されます。検視は、故人が亡くなった状況や死因、犯罪性の有無を確認するために行われる手続きです。具体的には、現場の状況確認、遺体の外見からの情報収集、証拠の収集などが含まれます。このプロセスは、医師の立ち会いや監察医が中心となって実施される場合が多く、状況によっては遺族の立ち会いが求められることもあります。検視の目的は、事件性がないかを早期に判断し、遺族に次の段階の指示ができるようにすることです。
検視が必要なケースと判断基準
検視が必要とされるケースには、事故死、犯罪が疑われる場合、不審な状況下での死亡、あるいは自然死であっても医師の診断が不十分な場合などが含まれます。例えば、自宅で急死された場合や遺体の発見時点で死亡から時間が経過している場合などには、警察が検視を実施する可能性が高くなります。一方で、病院での死亡や自然死が明らかな場合には、検視を行わず、主治医から死亡診断書が発行されるため、警察の介入はありません。検視が必要とされる状況では、その場で法的手続きを含めた段取りが進むため、遺族は警察の指示に従うことが重要です。
遺体の警察署への搬送手順
検視が終了すると、多くの場合、遺体が警察署に搬送されます。この搬送作業は、専門の業者や警察による協力のもと行われ、遺体を適切に取り扱うための準備が進められます。遺体は、納体袋という専用の袋に収められることが一般的です。警察署内では、保管場所に安置され、引き取り準備が整うまで保存されます。この間、遺族は必要な手続きや事務作業を進める必要があります。搬送にかかる費用についても、検視の有無や地域により異なるケースがあるため、事前に警察や担当者と費用負担の確認をしておくことが望ましいです。
検視と死因究明の手続き
検視の目的とプロセス
検視は、遺体が発見された際に行われる法律に基づいた手続きで、警察が中心となり行います。その目的は、故人がどのような状況で亡くなったのかを明らかにすることです。特に、犯罪性の有無や事故か事件かといった要因を確認する役割を果たします。検視は医師の立ち合いのもとで行われ、必要に応じて検察官も関与します。プロセスとしては、死亡現場の状況確認、遺体の外部検査、必要に応じた解剖などを経て死因究明を進めます。
検死と検案の違い
検視に関連してよく混同されがちなのが「検死」と「検案」です。検死とは、遺体そのものを調査し死因を明確にする作業であり、監察医などが実施します。一方、検案とは医師が亡くなった状況や遺体の状態から死因を判断し、死体検案書を作成する手続きです。重要な違いとして、検死は主に事故死や変死などの疑義がある場合に行われるのに対し、検案は自然死など疑わしき点がない場合に進められるという点が挙げられます。
検案書と死亡診断書の取得方法
検視が行われ、事件性がないと判断された場合、最終的に「死体検案書」が作成されます。一方、病院で医師の管理下にある状態で死亡が確認された場合は、「死亡診断書」が発行されます。これらの書類は、葬儀手続きや行政への死亡届提出に必要となります。検案書は検視の結果を経た後、指定の医師が作成しますが、その取得については警察からの連絡に基づき手続きが行われます。死亡診断書の場合は、病院に直接問い合わせることで比較的簡単に発行されます。
検視が行われる時間や費用
検視にかかる時間はケースによって大きく異なります。比較的簡潔な事例では半日程度で終了する場合もありますが、複雑な事件や不明点が多い場合は数日から数週間、場合によっては数ヶ月を要することもあります。また、検視にかかる費用については遺族が一部負担する場合があり、主に遺体の輸送や安置に必要な費用が含まれます。地域によって異なりますが、3万円から10万円程度が目安となります。特殊なケースで解剖が必要となる場合は、15万円から30万円程度の追加費用がかかることがあります。
遺体の引き取りと搬送
警察署からの引き取り連絡の流れ
警察による検視が終了し、犯罪性がないと判断されると、遺族に対して遺体引き取りの連絡が行われます。連絡は通常、警察担当者から電話で行われ、引き取り可能な日時や必要な手続きについて説明があります。遺族はこの連絡を受け取り次第、迅速に対応を始める必要があります。特に、遺体安置の段取りを早めに決めることが求められます。
遺体引き取りに必要な書類と手続き
遺体を引き取る際には、警察署から発行される書類や必要な情報を確認することが第一です。具体的には、身分証明書、検視後に交付される死体検案書などの受け取り手続きが必要となる場合があります。また、警察側の指示に従い、正確な手続きを進めることが重要です。これらの準備が整っていないと、不要な遅れが発生することがあるため、事前に確認するのが良いでしょう。
遺体搬送での注意点と霊柩車の利用
遺体搬送は慎重に行う必要があります。霊柩車を利用する場合、事前に葬儀社に連絡し、スケジュール調整や搬送先の確認を行うことが一般的です。警察署による安置から自宅や葬儀場への移動では、移送中にトラブルが発生しないよう、書類や手続き内容を再確認することが求められます。霊柩車の利用にあたっては、追加費用が発生するケースもあるため、事前に料金について確認しておくと安心です。
葬儀社への連絡と搬送先の決定
警察署から遺体を引き取った後は、主に自宅か葬儀場への安置が選択肢となります。この搬送先を決定する際、葬儀社との打ち合わせが必要です。葬儀社は、遺体の搬送以外にも、以後の葬儀の段取りや必要な行政手続きについてアドバイスしてくれます。早めに信頼できる葬儀社を選び、スムーズに手続きを進めることが、遺族にとって大きな助けとなるでしょう。
葬儀までの準備と段取り
自宅安置と葬儀場安置の選択
遺体をどこに安置するかは重要な判断となります。主に「自宅安置」と「葬儀場安置」の二つの選択肢があります。自宅安置では、故人を身近に感じながら見送ることができますが、衛生面やスペースの確保が課題になることがあります。一方、葬儀場安置は、設備が整っており、適切な温度管理が可能です。そのため、夏場や長期的な安置が必要な場合には特に適しています。検視後、警察から遺体が引き渡されるタイミングでどちらを選ぶか確認しておくと段取りがスムーズです。
葬儀社との打ち合わせ手順
遺体の安置が確定したら、早急に葬儀社と打ち合わせを行う必要があります。具体的に決めるべきことは、葬儀の形式、会場、日程、予算などです。また、葬儀社に遺体の搬送を依頼する場合は、その流れについても確認しておきましょう。葬儀社は遺族の意向を反映させつつ、法律や宗教上の規定を守る形で段取りを進めてくれます。特に事故や変死の場合、警察での検視が済んだタイミングなどスケジュールが限定されるため、迅速な調整が求められます。
死亡届の提出と行政手続き
葬儀を行うまでには、死亡届の提出をはじめとする行政手続きを行う必要があります。死亡届は遺族またはその代理人が、死亡診断書や死体検案書を基に所轄の市区町村役場に提出します。この手続きが完了すると火葬許可証が発行され、葬儀や火葬が行えるようになります。また、葬儀後には相続関連の手続きや年金の停止など、さまざまな対応が必要になるため、必要書類を整理しておくとよいでしょう。
親族や知人への連絡と役割分担
親族や知人への訃報の連絡も重要なステップです。まずは近親者に事情を説明し、その後、葬儀の日時や場所が決まり次第、関係者に知らせましょう。この際、誰に連絡を担当してもらうのかなど役割分担を事前に調整しておくとスムーズです。また、場合によっては参列者数を把握し、食事の手配や供花の対応もしなければなりません。こうした段取りを事前に考えておくことで、当日の混乱を避けることができます。
トラブル回避と事前に知っておきたい知識
時間がかかるケースと対処法
警察が介入する場合の「検視」は、死因究明や事件性の確認といった重要な手続きです。しかし、検視には時間がかかるケースがあり、特に犯罪性が疑われる場合や詳しい死因を確認するために解剖が必要な場合には、手続きが長引くことがあります。また、検視後の遺体が警察署に安置される期間も状況により異なり、通常の葬儀準備に影響を及ぼすことがあります。
遺族としては、手続きの進行状況を警察に確認し、葬儀社とも密に連絡を取り、段取りを早めるよう努めることが重要です。特に自宅安置を希望する場合や火葬場の予約が必要な場合には、警察署や葬儀社と連携を取りながら予定を調整することをおすすめします。時間がかかる場合でも、冷静に対応できる心構えを持つことが大切です。
費用負担についての確認ポイント
検視や警察署での安置、遺体搬送には基本的には国の負担となります。例えば、警察による検視にかかる費用は通常3万円から10万円程度と言われています。また、遺体の搬送における車両費や納体袋の使用料などは遺族が負担することは基本ありません。ご遺体の着付けや状態の復元処置などを希望または必要とされる場合には、15万円から50万円程度の費用がかかることもあります。
これらの費用は基本的に遺族が負担しますが、事前に明細を確認し、不明点について葬儀社に相談することが重要です。特に限られた予算内で葬儀を行いたい場合には、早めに必要な費用の総額を見積もることを心がけましょう。
警察署とのスムーズな連携方法
警察署は、遺体の安置や検視、死因究明の重要な手続きを行う場ですが、遺族としてスムーズに対応するためには警察との連携が不可欠です。連絡を受けた際には、必要書類や手続き内容を正確に確認するようにしましょう。また、検視や遺体引き取りのプロセスが進む中で不明点があれば、迷わず担当者に質問し、進行中の流れを随時確認することが大切です。
さらに、警察からの指示や連絡に的確に対応できるよう、葬儀社などの専門家のサポートを依頼することも有効です。特に初めてのケースで不安がある場合や、手続きの細部についてあまり詳しくない場合には、葬儀社に相談することで負担を軽減できます。
エンディングノートの活用で備える
トラブルを未然に防ぐためには、エンディングノートを活用して事前に必要な情報を書き記しておくことがおすすめです。エンディングノートには、葬儀の希望や遺族に残したいメッセージ、連絡してほしい親族や知人の情報などを記載しておきます。また、万が一自宅で突然亡くなった場合や警察が介入するケースについての対応も記しておくと、いざというときに遺族が落ち着いて行動しやすくなります。
エンディングノートは、遺族が手続きを円滑に進めるだけでなく、検視や葬儀の流れについて予め意思を示すことができる重要なツールです。未然に準備を整えておくことで、精神的な負担を軽減し、大切な方とのお別れに不安がない環境を整えることができます。
葬儀場の詳細を見る
公営斎場もご利用になれます

【公営斎場】熊本市斎場
住 所
〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町796
アクセス
熊本市役所から車で、約35分

【公営斎場】菊池火葬場
住 所
〒861-1315 熊本県菊池市木柑子1318
アクセス
阿蘇高原線 三里木駅からタクシー24分

【公営斎場】大津火葬場
住 所
〒869-1233 熊本県菊池郡大津町大字大津110
アクセス
豊肥本線「肥後大津駅」からタクシーで5分