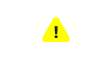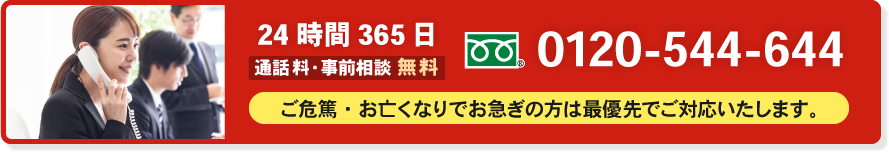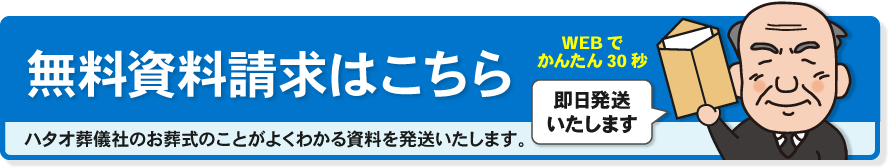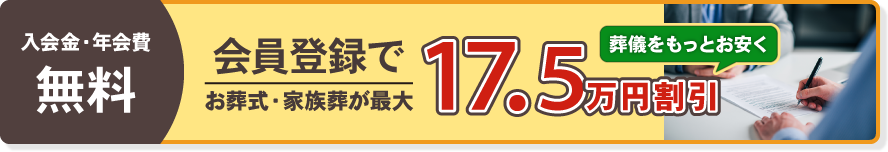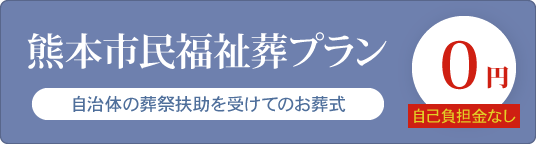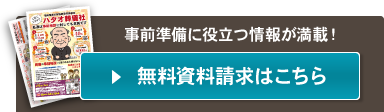新着情報
2025.03.11
春のお彼岸に向けて:ご先祖様への感謝を形に 早めのご準備を
春のお彼岸に向けて:ご先祖様への感謝を形に
春のお彼岸、ご先祖様への感謝を形に – その由来と意味を紐解く –
春の暖かな日差しが心地よい季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。ハタオ葬儀社の畑尾一心です。
春といえば、美しい桜の開花とともに「春のお彼岸」がやってきます。お彼岸は、ご先祖様を偲び、感謝の気持ちを伝える大切な期間ですが、「そもそもお彼岸って何?」「なぜこの時期にご先祖様を供養するの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、お彼岸の由来や意味、そしてご先祖様への感謝を形にする方法について、少し掘り下げてお話したいと思います。
お彼岸の由来 – 仏教と日本の文化が織りなす美しい習慣 –
お彼岸は、仏教の「彼岸」という概念と、日本古来の祖先崇拝、自然信仰が融合して生まれた、日本独自の行事です。
仏教では、西方には阿弥陀如来のいる極楽浄土(彼岸)があるとされています。春分の日と秋分の日は、太陽が真東から昇り真西に沈むため、この世(此岸)と彼岸が最も通じやすいと考えられました。
一方、日本には仏教が伝わる以前から祖先を敬う文化があり、農作業の節目に祖先に感謝し、自然の恵みに感謝する風習がありました。これらの要素が結びつき、お彼岸の時期に祖先の供養を行う習慣が定着したと考えられています。
お彼岸にすること – 心を込めてご先祖様を偲ぶ –
お彼岸には、お墓参りや仏壇の掃除、お供えなど、様々な供養の方法があります。大切なのは、心を込めてご先祖様を偲び、感謝の気持ちを伝えることです。
お墓参りでは、お墓の掃除や、お花やお供え物をすることで、ご先祖様を供養しましょう。仏壇では、お線香をあげ、お経を唱えることで、ご冥福を祈りましょう。
また、家族みんなで集まり、ご先祖様の思い出話をするのも良いのではないでしょうか。ご先祖様から受け継いだ大切なものを、次の世代へと語り継ぐことも、供養の一つになります。
ご先祖様との絆を深める、心温まるお彼岸を –
お彼岸は、ご先祖様との絆を改めて感じ、日々の感謝を伝える大切な機会です。心を込めて準備をし、温かい気持ちでご先祖様を偲びましょう。
しかし、「お彼岸には何をすればいいの?」「何か特別なことをしないといけない?」と疑問に思われる方も多いかもしれません。忙しい毎日の中で、お墓参りや仏壇のお手入れをしたいと思っていても、なかなか時間が取れない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、お彼岸の意味や、準備すること、ご先祖様への感謝を形にする方法について詳しくお話しします。ぜひ、今年のお彼岸の過ごし方の参考にしてください。
お彼岸とは?その意味と由来
お彼岸は、春分の日と秋分の日を中心とした、それぞれ前後3日間を合わせた7日間の期間を指します。今年(2025年)の春のお彼岸の日程は、以下の通りです。
- 彼岸入り:3月17日(月)
- 中日(春分の日):3月20日(木・祝)
- 彼岸明け:3月23日(日)
少し詳しくお話しすると、「彼岸(ひがん)」とは、仏教の教えにおける「悟りの境地」を意味します。私たちが生きている世界を「此岸(しがん)」といい、ご先祖様がいる世界が「彼岸」とされています。お彼岸の時期は、昼と夜の長さがほぼ同じになり、自然界のバランスが取れる特別な日。そのため、仏教では「ご先祖様の供養をするのにふさわしい期間」と考えられてきました。 日本では、古くからお彼岸の時期に先祖供養を行う習慣が根付いており、特に江戸時代以降、庶民の間でも広まりました。現在でも、多くの家庭でお墓参りや仏壇のお手入れを行い、ご先祖様に感謝の気持ちを伝える大切な行事となっています。
お彼岸に行うこと
お彼岸の期間には、ご先祖様に感謝を伝えるために、以下のようなことを行うのが一般的です。
1. お墓参り
お彼岸の最も代表的な行事です。
お墓の掃除:
・お墓の周りの落ち葉や雑草を取り除き、清掃します。
・墓石を丁寧に磨き、汚れを落とします。
・花立てや線香立てなどの清掃も行いましょう。
お供え:
・故人が好きだった花や食べ物、お菓子などをお供えします。
・お線香を焚き、ご先祖様への感謝の気持ちを伝えます。
・お供えした食べ物は、持ち帰って家族でいただきましょう。
お参り:
・お墓の前で手を合わせ、ご先祖様のご冥福を祈ります。
・日頃の感謝の気持ちや、近況報告などを伝えると良いでしょう。
2. 仏壇の供養
お墓参りと同様に、仏壇の供養も大切です。
仏壇の掃除:
・仏壇の埃を払い、丁寧に拭き掃除をします。
・仏具を磨き、綺麗に飾り直します。
・仏壇周りも整理整頓し、清潔な状態に保ちましょう。
お供え:
・お花、お線香、ろうそくをお供えします。
・ぼたもちやおはぎなど、お彼岸ならではのお供え物も用意しましょう。
・故人が好きだった食べ物や飲み物もお供えすると喜ばれます。
お参り:
・仏壇の前で手を合わせ、ご先祖様のご冥福を祈ります。
・お経を唱えたり、ご先祖様の思い出話をしたりするのも良いでしょう。
3. 彼岸会への参加
菩提寺で彼岸会が執り行われる場合は、積極的に参加しましょう。
彼岸会とは:
・お寺で僧侶が読経し、ご先祖様の供養を行う法要です。
・参加者も一緒にお経を唱えたり、焼香したりします。
準備:
・お布施を用意しましょう。金額は地域や寺院によって異なりますので、事前に確認しておくと安心です。
・平服でも構いませんが、落ち着いた服装を心がけましょう。
4. 家族で過ごす時間
・お彼岸は、ご先祖様を偲び、家族の絆を深める良い機会です。
家族で集まる:
・普段なかなか会えない家族も集まり、ご先祖様の思い出話や近況報告などをしましょう。
・一緒に食事をしたり、お墓参りに行ったりするのも良いでしょう。
ご先祖様の供養:
・ご先祖様の写真や遺品などを飾り、偲ぶ時間を作りましょう。
・ご先祖様から受け継いだ大切なものを、次の世代へと語り継ぎましょう。
5. その他
精進料理:
・お彼岸期間中は、肉や魚を避けた精進料理をいただきましょう。
・ご先祖様への供養にもなりますし、自身の心身を清める意味もあります。
感謝の気持ち:
・ご先祖様への感謝の気持ちを忘れずに、日々を過ごしましょう。
・ご先祖様がいたからこそ、今の自分があるということを意識することが大切です。
お彼岸は、ご先祖様を供養し、感謝の気持ちを伝える大切な期間です。心を込めて供養し、ご先祖様との絆を深めましょう。
お彼岸の思い出
「私にとってお彼岸は、単なる年中行事ではありません。それは、幼い頃から積み重ねてきた、かけがえのない思い出の宝箱のようなものです。春の暖かな日差しが降り注ぐ頃になると、胸の奥がきゅっと締め付けられるような、懐かしい感情が込み上げてきます。
子供の頃、お彼岸が近づくと、母と一緒に過ごす時間が何よりも楽しみでした。母は、いつもと変わらず温かく、優しい笑顔で迎えてくれました。お墓参りの後、縁側に腰を下ろし、母が作ってくれた牡丹餅をいただくのが、私たち家族にとって最高の瞬間だったのです。
母の作る牡丹餅は、もち米の優しい甘さと、あんこの上品な甘さが絶妙に絡み合い、口の中に広がるたびに、幸せな気持ちで満たされました。家族みんなで、時には近所の方も加わり、賑やかに牡丹餅を頬張る。そんな光景が、今でも鮮明に目に浮かびます。
特に印象に残っているのは、母と一緒に牡丹餅を作った時のことです。小さな手で、もち米を丸め、あんこを包むのは、なかなか難しい作業でした。上手くできずに、あんこがはみ出してしまったり、形が崩れてしまったり。それでも、母はいつも優しく、「大丈夫、大丈夫」と声をかけ、丁寧に教えてくれました。
母の優しい眼差し、温かい手の感触、そして、一緒に作った牡丹餅の優しい甘さ。それらは、私にとって、かけがえのない宝物です。
自分自身が家族を持つようになって、改めて、お彼岸の意味を深く考えるようになりました。ご先祖様を偲び、感謝の気持ちを伝える。それは、単に過去を振り返るだけでなく、未来へと繋がる大切な営みだと思います。
ご先祖様、両親がいたからこそ、今の私たちが存在し、家族の絆が受け継がれていく。お彼岸は、そんな当たり前のことを、改めて実感する機会を与えてくれます。
忙しい日々に追われる中で、つい忘れがちな感謝の気持ち。お彼岸は、そんな心の隙間を埋め、温かい気持ちで満たしてくれる、特別な時間です。
今年のお彼岸は、皆様も、ぜひご家族でゆっくりと過ごし、亡き方への感謝の気持ちを伝えてください。そして、かけがえのない思い出を、たくさん作ってください。
お彼岸が、皆様にとって、心温まる、穏やかな時間となりますように。」
ハタオ葬儀社
畑尾一心 スタッフ一同
執筆者 監修者
執筆者:畑尾一心
創業昭和30年 熊本県儀式共済株式会社
ハタオ葬儀社 3代目 代表取締役社長
1972年、熊本で50年余年続く葬儀店に生まれる。
葬祭業に従事して30年
現在、年間約400件を超えるご葬儀、ご相談に携わっています。
NPO法人全国葬送支援協議会熊本中央本部 代表
厚生労働省認定葬祭ディレクター技能審査 1級葬祭ディレクター
一般社団法人 終活協議会 終活セミナー講師 終活ガイド資格3級
一般社団法人 終活カウンセラー協会 終活カウンセラー
創業者、会長の想いを引き継ぎながら
日本独自の葬送文化の意味を現代の意味を感じて頂き
後悔の無いお葬式を大切に葬儀の仕事に取り組んでいます。
趣味は、散歩。近所はもちろん、知らない街をあることで
その地域に住む人たちとのコミュニケーションを楽しんでいます。
葬儀場の詳細を見る
公営斎場もご利用になれます

【公営斎場】熊本市斎場
住 所
〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町796
アクセス
熊本市役所から車で、約35分

【公営斎場】菊池火葬場
住 所
〒861-1315 熊本県菊池市木柑子1318
アクセス
阿蘇高原線 三里木駅からタクシー24分

【公営斎場】大津火葬場
住 所
〒869-1233 熊本県菊池郡大津町大字大津110
アクセス
豊肥本線「肥後大津駅」からタクシーで5分