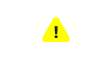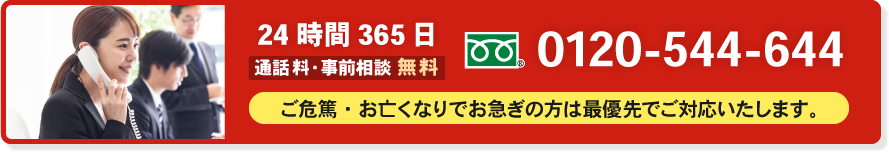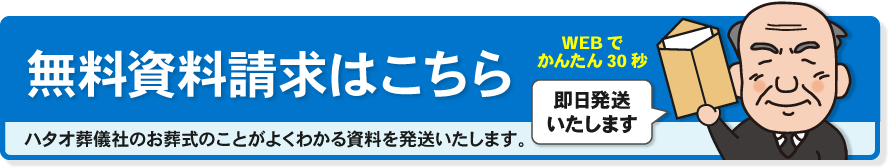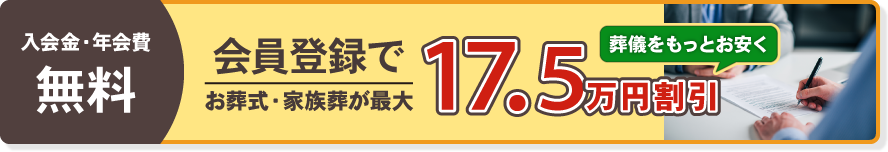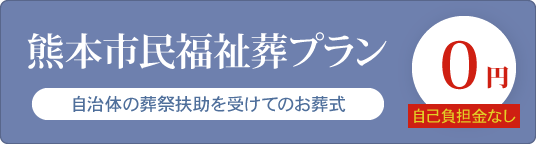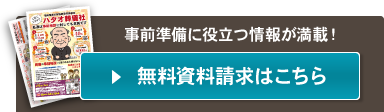新着情報
2025.03.25
葬儀に必要なものリスト|持ち物や準備すべきことを徹底解説
はじめに
人生の節目である葬儀は、故人様を偲び、感謝の気持ちを伝える大切な儀式です。しかし、突然の出来事に、何を準備すれば良いのか、何を持参すれば良いのか、戸惑われる方も少なくありません。
「葬儀に必要なものリスト|持ち物や準備すべきことを徹底解説」では、そんな皆様の不安を少しでも和らげ、安心して故人様をお見送りいただけるよう、葬儀の準備から持ち物、葬儀後に必要なことまで、わかりやすく丁寧に解説いたします。
地域と心に寄り添う葬儀の専門家、ハタオ葬儀社は、皆様の悲しみに寄り添い、温かい心でサポートいたします。この記事が、皆様にとって少しでもお役に立てれば幸いです。
このような方へおすすめ
✅初めて喪主を務めることになり、葬儀の準備や持ち物について具体的に知りたい方
✅急な葬儀の連絡を受け、何を持参すれば良いか、どのような服装で参列すべきか不安な方
✅家族葬や一般葬など、葬儀の種類や準備内容について、事前に情報を整理しておきたい方
目次
- 葬儀前に準備しておくべきこと
- 持参すべき基本アイテム
- 服装や身だしなみの注意点
- 副葬品の種類と選び方
- 重要書類の準備
- 葬儀中に必要な持ち物とその役割
- 香典の用意方法とマナー
- 数珠の選び方と扱い方
- 手土産や供物の選定ポイント
- 必要に応じた文書や弔辞
- 遺族として準備すべきことと注意点
- 故人の思い出を形にする準備品
- 葬儀日程の決め方と関連手続き
- 式典中のトラブル対策と予備品
- 僧侶や司会者とのコミュニケーション
- 葬儀後に準備しておきたいもの
- 法事・法要に必要な準備
- お返し品選びの注意点
- 費用の見直しと家計管理のポイント
- 遺族間の打ち合わせと共有事項
1.葬儀前に準備しておくべき必要なものとは?
持参すべき基本アイテム
葬儀にかかるときは、事前に必要なものをきちんと準備しておくと安心です。うっかり忘れ物をしないために、「葬儀の持ち物リスト」を作ってチェックしながら用意しておけば大丈夫です。ちなみに、香典(こうでん)は袱紗(ふくさ)に包んで持っていきます。他にも、数珠(じゅず)や黒いハンカチなども必要なお知らせです。
そのほかに、エプロンや風呂敷(ふろしき)、ちょっとした貴重品入れもあると便利ですよ。
葬儀に参列する際は、以下の基本的な持ち物を準備しておくと安心です。忘れ物がないように、リストで確認しましょう。
| 持ち物 | 説明 | 用途 | 普段からの準備 |
| 香典 | 故人の霊前にお供えする金銭。 | 弔意を示すため。 | 香典袋、袱紗とともに用意しておくと安心。 |
| 袱紗(ふくさ) | 香典を包む布。 | 香典を汚したり、落としたりしないように保護するため。丁寧な印象を与える。 | 慶弔両用、または弔事用の袱紗を用意。 |
| 数珠 | 仏式の葬儀で使用する仏具。 | 焼香の際などに使用。 | 略式数珠を用意しておくと、宗派を問わず使える。 |
| ハンカチ | 黒色または白色の無地のもの。 | 涙を拭う際などに使用。 | 普段から用意。 |
| 貴重品袋 | 財布、スマートフォンなどを入れる小さめの袋。 | 貴重品をまとめて管理するため。 | 普段使いのもので可。 |
| エプロン (必要な場合) | お手伝いをする際に、衣服の汚れを防ぐため。 | 必要に応じて。 | |
| 風呂敷 (必要な場合) | 手荷物をまとめたり、持ち帰る際に使用。 | 必要に応じて。 |
ポイント:
- 香典は袱紗(ふくさ)に包んで持参するのがマナーです。
- 数珠は仏式の葬儀で必要になります。
- ハンカチは黒色または白色の無地のものを用意しましょう。
- 貴重品は小さな袋にまとめて管理すると安心です。
- エプロンや風呂敷は、お手伝いをする際に役立ちます。
その他
- マスク(黒色または白色の無地のもの)
- ティッシュ
- 予備のストッキング(女性の場合)
これらの持ち物は、突然の葬儀に備えて、普段から準備しておくと安心です。
服装や身だしなみの注意点
葬儀・告別式に参列する際の服装は、故人への敬意を表し、遺族の方々を不快にさせないためにも、マナーを守ることが非常に重要です。
◇喪服の種類と参列者の服装マナー
喪服には、格式の高い順に「正喪服」「準喪服」「略喪服」の3種類があります。一般的に、参列者は準喪服を着用するのが適切とされています。
- 正喪服:
- 最も格式の高い喪服で、喪主や近親者が着用します。
- 男性はモーニングコート、女性は黒のワンピースやアンサンブルなどが該当します。
- 準喪服:
- 一般の参列者が着用する喪服で、黒のスーツやワンピースなどが該当します。
- 略喪服:
- 地味な色のスーツやワンピースなど、略式の喪服です。
- 急な弔問やお通夜などで着用されることがあります。
参列時の服装チェックシート
参列前に以下の項目をチェックし、服装のマナーを守れているか確認しましょう。
男性
- 黒のスーツ(光沢のないもの)
- 白のワイシャツ
- 黒のネクタイ(光沢や柄のないもの)
- 黒の靴下
- 黒の革靴(光沢のないもの)
- 結婚指輪以外のアクセサリーは控える
女性
- 黒のワンピースまたはスーツ(光沢やレースなどの装飾が少ないもの)
- 黒のストッキング
- 黒の靴(光沢のないパンプスなど)
- 結婚指輪以外のアクセサリーは控える(パールの一連ネックレスは可)
- 派手なネイルやメイクは避ける
- 香水は控える
注意点
- 動物の革製品(ヘビ、ワニなど)や毛皮製品は避ける
- 殺生を連想させるため、アクセサリーは控えるのが基本
- 髪型は、顔にかからないようにまとめ、清潔感を保つ
- メイクは、ナチュラルメイクを心がけ、派手な色は避ける
- 香水は、控えめにするか、つけないようにする
参列時の服装に関するその他のマナー
- お通夜は、急な弔問であるため、略喪服でも可とされています。
- 学生の場合は、制服が正式な喪服となります。
- 乳幼児を連れて参列する場合は、落ち着いた色の服装を選び、音の出るおもちゃなどは避けるようにしましょう。
参列時の服装は、故人への弔意と遺族への配慮を示すものです。服装のマナーを守り、故人を偲び、遺族の方々の気持ちに寄り添うようにしましょう。
副葬品の種類と選び方
副葬品とは、故人様があの世へ旅立つ際に、棺に納める品物のことです。故人様が生前愛用されていた物や、思い出の品などを納めることで、故人様への想いを伝え、弔いの気持ちを表します。
副葬品を選ぶ際の心構え
副葬品を選ぶことは、故人様との最後の思い出を分かち合う、とても大切な時間です。故人様が生前何を大切にされていたのか、どんなものを好んでいたのかを思い出しながら、心を込めて選びましょう。
副葬品として選ばれるもの
- 写真:
- 故人様の笑顔の写真や、ご家族との思い出の写真など、故人様を偲ぶことのできる写真を選びましょう。
- 手紙・メッセージ:
- 故人様への感謝の気持ちや、伝えたい言葉などを手紙やメッセージに込めて納めましょう。
- 故人様が生前愛用していた物:
- 故人様が愛用されていた服や本、趣味の道具などを納めることで、故人様らしさを表現することができます。
- 故人様が好きだった食べ物やお菓子:
- 故人様が好きだった食べ物やお菓子を納めることで、故人様があの世でも寂しくないようにという願いを込めることができます。
- 生花:
- 故人様が好きだった花や、故人様のイメージに合った花を添えましょう。
副葬品として避けるべきもの
- ガラス・金属類:
- 火葬の際に溶けて遺骨を損傷する恐れがあります。
- プラスチック製品:
- 燃え残ったり、有害物質が発生したりする可能性があります。
- カーボン製品:
- 火葬炉を傷つける可能性があります。
- 書籍、雑誌類(分厚い物):
- 燃え残る可能性があります。
- 危険物:
- ライター、電池などは火葬中に爆発する危険性があります。
- 水分を多く含むもの:
- スイカやメロンなどの果物、缶詰などは、火葬の際に水分が蒸発して、棺を損傷する可能性があります。
- 布団、毛布類:
- 燃え残る可能性があり、ダイオキシンが発生する場合があります。
- 大型の品物:
- 棺に納まらない場合があります。
副葬品を選ぶ際の注意点
- 燃えやすい素材を選ぶ:
- 燃えにくい素材は、火葬の際に遺骨を損傷する恐れがあります。
- 有害物質が発生しないものを選ぶ:
- ビニールやプラスチックなど、燃やすと有害物質が発生するものは避けましょう。
- 小型のものを選ぶ:
- 大きすぎるものは、棺に納まらない場合があります。
- 故人様の希望を尊重する:
- 生前に故人様が希望されていたものがあれば、それを優先しましょう。
- 宗教や宗派の教えに従う:
- 宗教や宗派によっては、副葬品に関する考え方が異なる場合があります。
遠い親戚や友人の場合の注意点
遠い親戚や友人の場合、故人様との関係性や、ご家族の意向を尊重することが特に大切です。
- ご家族への確認:
- 副葬品の内容や量、宗教や宗派の考え方などを確認し、許可を得ましょう。
- ご家族は悲しみの中にいます。ご家族の気持ちに寄り添い、失礼のないように配慮しましょう。
- 勝手な判断は避ける:
- 故人様との個人的な関係だけで判断せず、必ずご家族の許可を得ましょう。
- ご家族の意向を尊重する:
- ご家族が副葬品を辞退された場合は、その意向を尊重しましょう。
- 無理強いはしない:
- ご家族が副葬品に迷われている場合は、無理強いせず、時間をかけて相談しましょう。
副葬品に関する準備
副葬品を選ぶ際には、ご家族で故人様との思い出を振り返りながら、故人様らしい品を選ぶことが大切です。また、葬儀社に相談することで、副葬品に関するアドバイスをもらうことができます。
副葬品は、故人様への弔いの気持ちを表す大切なものです。心を込めて選び、故人様を温かくお見送りしましょう。
副葬品を選ぶ際の心構え
副葬品を選ぶことは、故人様との最後の思い出を分かち合う、とても大切な時間です。故人様が生前何を大切にされていたのか、どんなものを好んでいたのかを思い出しながら、心を込めて選びましょう。
副葬品として選ばれるもの
- 写真:
- 故人様の笑顔の写真や、ご家族との思い出の写真など、故人様を偲ぶことのできる写真を選びましょう。
- 手紙・メッセージ:
- 故人様への感謝の気持ちや、伝えたい言葉などを手紙やメッセージに込めて納めましょう。
- 故人様が生前愛用していた物:
- 故人様が愛用されていた服や本、趣味の道具などを納めることで、故人様らしさを表現することができます。
- 故人様が好きだった食べ物やお菓子:
- 故人様が好きだった食べ物やお菓子を納めることで、故人様があの世でも寂しくないようにという願いを込めることができます。
- 生花:
- 故人様が好きだった花や、故人様のイメージに合った花を添えましょう。
副葬品として避けるべきもの
- ガラス・金属類:
- 火葬の際に溶けて遺骨を損傷する恐れがあります。
- プラスチック製品:
- 燃え残ったり、有害物質が発生したりする可能性があります。
- カーボン製品:
- 火葬炉を傷つける可能性があります。
- 書籍、雑誌類(分厚い物):
- 燃え残る可能性があります。
- 危険物:
- ライター、電池などは火葬中に爆発する危険性があります。
- 水分を多く含むもの:
- スイカやメロンなどの果物、缶詰などは、火葬の際に水分が蒸発して、棺を損傷する可能性があります。
- 布団、毛布類:
- 燃え残る可能性があり、ダイオキシンが発生する場合があります。
- 大型の品物:
- 棺に納まらない場合があります。
副葬品を選ぶ際の注意点
- 燃えやすい素材を選ぶ:
- 燃えにくい素材は、火葬の際に遺骨を損傷する恐れがあります。
- 有害物質が発生しないものを選ぶ:
- ビニールやプラスチックなど、燃やすと有害物質が発生するものは避けましょう。
- 小型のものを選ぶ:
- 大きすぎるものは、棺に納まらない場合があります。
- 故人様の希望を尊重する:
- 生前に故人様が希望されていたものがあれば、それを優先しましょう。
- 宗教や宗派の教えに従う:
- 宗教や宗派によっては、副葬品に関する考え方が異なる場合があります。
遠い親戚や友人の場合の注意点
遠い親戚や友人の場合、故人様との関係性や、ご家族の意向を尊重することが特に大切です。
- ご家族への確認:
- 副葬品の内容や量、宗教や宗派の考え方などを確認し、許可を得ましょう。
- ご家族は悲しみの中にいます。ご家族の気持ちに寄り添い、失礼のないように配慮しましょう。
- 勝手な判断は避ける:
- 故人様との個人的な関係だけで判断せず、必ずご家族の許可を得ましょう。
- ご家族の意向を尊重する:
- ご家族が副葬品を辞退された場合は、その意向を尊重しましょう。
- 無理強いはしない:
- ご家族が副葬品に迷われている場合は、無理強いせず、時間をかけて相談しましょう。
副葬品に関する準備
副葬品を選ぶことは、故人様との大切な思い出を振り返り、感謝の気持ちを伝える、心温まる時間です。故人様が安らかに旅立てるよう、そしてご家族の心が少しでも癒されるよう、心を込めて選びたいですね。
故人様への想いを形にする
- 感謝の気持ちを伝える
- 故人様との思い出を振り返り、「ありがとう」の気持ちを込めて、何を納めるかじっくり考えてみましょう。
- 手紙やメッセージに、伝えきれなかった感謝の言葉や、心に残るエピソードを綴るのも素敵ですね。
- 故人様らしい見送り
- 故人様が生前大切にしていたもの、好きだったものを思い浮かべてみましょう。
- 故人様らしい品を選ぶことで、温かい気持ちで見送ることができます。
故人様の気持ちを尊重する
- 生前の希望を大切に
- もし故人様が「これを納めてほしい」と話していたことがあれば、その気持ちを尊重しましょう。
- 故人様の願いを叶えることが、一番の供養になるかもしれません。
- 故人様らしさを表現
- 故人様の趣味や愛用品など、故人様を象徴する品を選びましょう。
- 故人様が生きた証を、形として残すことができます。
ご家族の気持ちに寄り添う
- ご家族と相談する
- ご家族と故人様の思い出を語り合いながら、何を納めるか一緒に考えましょう。
- ご家族みんなで選ぶことで、故人様を偲ぶ気持ちを共有できます。
- 心の支えとなる品
- ご家族にとって、故人様との思い出が詰まった品は、心の支えとなります。
- 温かい思い出が蘇るような、優しい気持ちになれる品を選びましょう。
感謝の気持ちを込める
- 思い出を振り返る
- 故人様との思い出を振り返り、「ありがとう」の気持ちを込めて品を選びましょう。
- 感謝の気持ちは、きっと故人様に届くはずです。
- あの世でも寂しくないように
- 故人様が生前愛用していたものや、好きだったものを納めましょう。
- 「あの世でも寂しくないように」という、優しい気持ちを届けましょう。
故人様との思い出を大切にする
- 思い出を語り合う時間
- 副葬品を選ぶ時間は、故人様との思い出を語り合う、かけがえのない時間です。
- ご家族や親しい方々と、故人様の思い出話に花を咲かせましょう。
- 心を込めて選ぶ
- 故人様への感謝の気持ち、そして「安らかに眠ってください」という願いを込めて、丁寧に品を選びましょう。
- 心を込めて選ぶことが、故人様への一番の供養になります。
副葬品を選ぶことは、故人様との思い出を振り返り、感謝の気持ちを伝える、心温まる時間です。故人様が安らかに旅立てるよう、そしてご家族の心が少しでも癒されるよう、心を込めて選びたいですね。
◇重要書類の準備 ※喪主など近しいご親族の際
葬儀後の手続きは、精神的にも肉体的にも負担が大きいため、生前に準備しておくと、ご家族の負担を軽減できます。特に、故人に関する情報や財産に関する書類は、早めに整理しておくことをお勧めします。
生前に準備しておくと、葬儀後の手続きが楽になる書類
- 故人の情報に関する書類
- 戸籍謄本・除籍謄本:
- 故人の出生から死亡までの身分関係を証明する書類です。
- 相続手続きや遺族年金の請求などに必要となります。
- 本籍地の市区町村役場で取得できます。
- 住民票の除票:
- 故人が住民登録されていたことを証明する書類です。
- 相続手続きや不動産の名義変更などに必要となります。
- 最後に住民登録していた市区町村役場で取得できます。
- 年金手帳・年金証書:
- 遺族年金の請求などに必要となります。
- 基礎年金番号や加入記録を確認しておくと、手続きがスムーズに進みます。
- 健康保険証・介護保険証:
- 資格喪失の手続きに必要となります。
- 返却期限があるため、早めに手続きを行いましょう。
- 各種契約書(生命保険、損害保険、不動産、ローンなど):
- 契約内容の確認や名義変更、解約などに必要となります。
- 契約先の連絡先や証券番号などをまとめておくと便利です。
- 銀行口座・証券口座の情報:
- 口座番号、支店名、暗証番号などをまとめておくと、相続手続きがスムーズに進みます。
- インターネットバンキングを利用している場合は、IDやパスワードも控えておきましょう。
- クレジットカード・各種会員証:
- 解約手続きに必要となります。
- カード番号や会員番号、連絡先などをまとめておきましょう。
- デジタル遺品に関する情報:
- パソコン、スマートフォン、SNSアカウントなどのログイン情報やパスワードをまとめておきましょう。
- デジタル遺品の整理方法や処分方法について、生前に決めておくと安心です。
- 遺言書:
- 遺産の分け方などを記載した重要な書類です。
- 公正証書遺言を作成しておくと、相続争いを防ぐことができます。
- 葬儀に関する情報
- 葬儀の希望:
- 葬儀の形式、規模、宗教、場所、喪主などを決めておきましょう。
- 葬儀社との事前相談や見積もりもしておくと安心です。
- 葬儀費用の準備:
- 葬儀費用の目安や支払い方法などを確認しておきましょう。
- 葬儀保険や共済などに加入しておくことも検討しましょう。
- 遺影写真の準備:
- 故人らしい写真を選んでおきましょう。
- デジタルデータがあれば、すぐに印刷できます。
- 訃報の連絡先リスト:
- 訃報を連絡する親族や友人などのリストを作成しておきましょう。
- 連絡先の住所や電話番号も記載しておくと便利です。
- 納棺の際に一緒に納めるもの:
- 故人の愛用品や趣味のものなどをリストにしておきましょう。
- 宗教や宗派によって納める事が出来ないものもあるので、事前に葬儀社に確認しておきましょう。
- その他
- エンディングノート:
- 自分の情報や希望、メッセージなどを自由に書き残せるノートです。
- 葬儀や相続に関する情報だけでなく、人生の振り返りや大切な人へのメッセージなども残せます。
これらの書類を準備しておくことで、ご家族は故人の意思を尊重し、スムーズに手続きを進めることができます。また、精神的な負担も軽減され、故人を偲ぶ時間をゆっくりと過ごせるでしょう。
2.葬儀中に必要な持ち物とその役割
◇香典の用意方法とマナー
葬儀に参列する際、故人への敬意と遺族への弔意を表す香典は、細やかな心遣いが求められます。香典袋の選び方から金額の目安、渡し方のマナーまで、失礼のないように準備するための情報をまとめました。
香典袋の選び方と書き方
香典袋の種類
- 水引:
- 弔事には、黒白、双銀、または黄白の結び切りを使用します。
- 水引が印刷された略式の香典袋もあります。
- 表書き:
- 仏式:「御霊前」「御香典」
- 神式:「御玉串料」「御榊料」
- キリスト教式:「御花料」「御ミサ料」
- 宗派が不明な場合:「御香典」と書くのが無難です。
- 名前:
- フルネームで記入します。夫婦連名の場合、夫のフルネームと妻の名前のみを並べて書きます。
- 会社名や肩書きを書く場合は、名前の右上に小さく書きましょう。
中袋の書き方
- 金額:
- 旧字体で「金〇〇圓」と記入します。
- 例:「金壱萬圓」
- 氏名・住所:
- 裏面に氏名と住所を記入します。
-
- お札の向き:香典袋に入れるお札
-
- お札は肖像画が下向きになるように入れます。
- これは、故人への哀悼の意を表すためです。
- 新札について:
- 新札は避けるのがマナーとされていますが、やむを得ない場合は中央に折り目を入れて使用される場合もあります。
香典の金額の目安
香典の金額は、故人との関係性や自身の年齢、社会的立場によって異なります。一般的な目安は以下の通りです。
- 親族:
- 1万円~10万円
- 友人・知人:
- 5千円~1万円
- 職場関係者:
- 5千円~1万円
- 隣人・知人:
- 3千円~5千円
香典を渡す際のマナー
- 袱紗(ふくさ)に包む:
- 香典袋は袱紗に包んで持参し、受付で袱紗から出して渡します。
- 袱紗が無い場合は、地味な色のハンカチで代用することも可能です。
- 渡すときのマナー:
- 香典袋を袱紗から出し、相手が正面から文字を読める向きにして両手で渡します。
- 「御霊前にお供えください」など、弔いの言葉を添えて渡しましょう。
- お悔やみの言葉:
- 「この度はご愁傷様です」など、簡潔にお悔やみの言葉を述べます。
- 故人の死因や状況などを尋ねることは避けましょう。
注意事項
- 忌み言葉:
- 「重ね重ね」「度々」などの重ね言葉や、「死ぬ」「生存」などの直接的な表現は避けます。
- 宗教・宗派:
- 故人の宗教・宗派を確認し、適切な表書きや香典袋を選びましょう。
香典は、故人への弔意と遺族への心遣いを表すものです。マナーを守り、失礼のないように準備しましょう。
◇数珠の選び方と扱い方
葬儀における数珠は、故人を偲び、冥福を祈る大切な仏具です。宗派を問わず使える略式数珠を中心に、数珠の種類や選び方、扱い方のマナーについてご説明します。
数珠の種類と選び方
数珠は、大きく分けて本式数珠と略式数珠の2種類があります。
- 本式数珠:
- 宗派ごとに定められた正式な数珠です。
- 珠の数や形、房の形状などが異なります。
- 略式数珠:
- 宗派を問わず使用できる数珠です。
- 一般的に、どの宗派の葬儀・法要でも使用できます。
- 片手念珠とも呼ばれます。
略式数珠の選び方
略式数珠を選ぶ際は、以下の点に注意しましょう。
- 素材:
- 黒檀、紫檀、水晶、翡翠など、さまざまな素材があります。
- 素材によって質感や価格が異なるため、好みに合わせて選びましょう。
- 房:
- 房の色や形も素材同様に様々です。
- 房の色は、紫や灰色などの落ち着いた色を選ぶのが一般的です。
- サイズ:
- 男性用、女性用、共用の3種類があります。
- 手の大きさに合わせて選びましょう。
- 価格:
- 数千円から数十万円と、価格帯は様々です。
- 予算に合わせて選びましょう。
数珠の扱い方マナー
数珠は、仏様と心を通わせる大切な道具です。以下の点に注意して扱いましょう。
- 持ち方:
- 基本的には左手に持ちます。
- 合掌する際は、両手の中指にかけ、房は下に垂らします。
- 保管方法:
- 使用しない時は、数珠袋に入れて保管します。
- ポケットやバッグに直接入れるのは避けましょう。
- 貸し借り:
- 数珠の貸し借りは基本的にNGです。
- 数珠は持ち主の分身とも言われており、貸し借りは避けるべきです。
- 数珠を落とした時:
- 拾い上げて、服やハンカチで軽く拭き取りましょう。
- 数珠は仏具ですので、落としてしまったからと言って、雑に扱うことは避けましょう。
数珠を持つ意味
数珠は、仏教において以下のような意味を持ちます。
- 念仏を唱える回数を数える道具:
- 珠を繰りながら念仏を唱えることで、集中力を高めます。
- 仏様と心を通わせる道具:
- 数珠を持つことで、仏様との繋がりを感じ、心が安らぎます。
- お守り:
- 数珠は、災いから身を守るお守りとしての意味も持ちます。
数珠の準備
数珠は、葬儀に参列する際に持参するのがマナーです。突然の訃報で慌てることがないよう、事前に準備しておくことをおすすめします。
数珠は、仏具店や葬儀社で購入できます。インターネット通販でも購入可能です。
数珠は、故人を偲び、冥福を祈る気持ちを表す大切な仏具です。マナーを守って、心を込めて扱いましょう。
◇手土産や供物の選定ポイント
葬儀において、遺族や故人への供養の意味を込めて手土産や供物を持参する場合もあります。供物としては果物や菓子類、花などが一般的で、宗教や宗派に応じた選定が重要です。特に果物や菓子を贈る際は、香りが強すぎるものや、腐りやすいものは避けるよう配慮しましょう。
- 宗教・宗派に合わせる:
- 仏式、神式、キリスト教式など、故人の宗教・宗派に合わせた品物を選びましょう。
- 不明な場合は、葬儀担当者に相談するのが確実です。
- 品物の種類:
- 果物、菓子類、花などが一般的です。
- 果物は、日持ちするものが適しています。
- 菓子類は、個包装されたものが配りやすく喜ばれます。
- 花は、白や淡い色の落ち着いたものを選びます。
- 避けるべきもの:
- 香りが強すぎるもの(香りの強い花や果物など)
- 殺生を連想させるもの(肉や魚など)
- 日持ちしないもの(生菓子など)
- 葬儀担当者への確認:
- 事前に葬儀担当者に相談し、供物が適切であるか確認しましょう。
- 供物を辞退される場合もあるので、確認が必要です。
- 手土産について:
- 弔問先の遺族が負担にならない程度の軽いものを選びます。
- 日持ちする菓子などが適しています。
◇必要に応じた文書や弔辞
ときに葬儀では、故人を追悼するために弔辞や挨拶文を用意する必要があります。故人との関係性によって役割を求められる場合があり、事前準備が重要です。弔辞は、故人との思い出や人柄を振り返り、敬意と感謝を込めた内容にすることが大切です。
- 故人との関係性を考慮する:
- 故人との関係性によって、弔辞や挨拶の内容は異なります。
- 故人との思い出や人柄が伝わる内容にしましょう。
- 弔辞の内容:
- 故人の業績や人柄を称える言葉
- 故人との思い出やエピソード
- 故人への感謝と別れの言葉
- 遺族への慰めの言葉
- 挨拶文の内容:
- 弔意を示す言葉
- 故人への敬意
- 遺族への慰めの言葉
- 形式・流れの確認:
- 葬儀担当者に弔辞・挨拶の形式や流れを確認しましょう。
- 時間制限や言葉遣いなどの注意点を確認します。
- 事前準備:
- 急な依頼に備え、故人の思い出やエピソードを整理しておくと役立ちます。
- 家族で分担して準備を進めるとスムーズです。
その他
- 香典:
- 香典は、故人への供養と遺族への経済的な支援の意味があります。
- 金額は、故人との関係性や地域によって異なります。
- 香典袋の表書きは、宗教・宗派によって異なるので注意が必要です。
- 服装:
- 葬儀に参列する際は、喪服を着用するのが一般的です。
- アクセサリーは、結婚指輪以外は避けるのがマナーです。
- 言葉遣い:
- 葬儀では、忌み言葉や重ね言葉は避けるようにしましょう。
- 遺族への配慮を忘れず、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
これらのポイントを参考に、故人や遺族への心遣いを形にしましょう。
3.遺族として準備すべきことと注意点
◇故人の思い出を形にする準備品
葬儀は、故人様との大切な思い出を分かち合い、感謝の気持ちを伝える場です。故人様らしい温かいお見送りのために、思い出を形にする準備をすることは、ご遺族にとって非常に大切な要素となります。
故人様の思い出を形にする準備品
- 故人様の写真:
- 故人様の笑顔の写真や、ご家族との思い出の写真などを飾りましょう。故人様のお人柄を偲ぶことができます。
- 故人様の愛用品:
- 故人様が愛用されていた品々を飾ることで、故人様との思い出が蘇ります。
- 例:趣味の道具、愛読書、形見の品など
- 思い出のアルバムや映像:
- 故人様の写真を集めたアルバムや、思い出の映像を上映するのも良いでしょう。
- 副葬品:
- 故人様が好きだったものを棺に納めることで、故人様があの世でも寂しくないようにという願いを込めることができます。
- 例:手紙、写真、お花など
- ただし、火葬できるものに限ります。プラスチック製品や金属類など、火葬禁止品もあるため、葬儀担当者に相談しましょう。
準備の際の注意点
- 葬儀担当者との相談:
- どのような持ち物が適切か、葬儀担当者に相談しながら準備を進めましょう。
- 持ち物リストの作成:
- 必要なものを事前にリストアップしておくと、慌てずに準備を進められます。
- ご家族との話し合い:
- 故人様の思い出を共有し、ご家族で話し合いながら準備を進めましょう。
その他
- 思い出コーナーの設置:
- 葬儀会場に思い出コーナーを設け、参列者の方々にも故人様との思い出を振り返っていただけるようにするのも良いでしょう。
- メッセージコーナーの設置:
- 参列者の方々に故人様へのメッセージを書いていただけるコーナーを設けるのも、故人様への供養となります。
これらの準備品は、故人様への弔いの気持ちを表し、ご遺族の心を癒すためにも大切なものです。故人様との思い出を大切にしながら、心を込めて準備しましょう。
◇葬儀日程の決め方と関連手続き
葬儀の日程は、故人様を送り出す上で非常に重要な要素です。故人様とご遺族の意向を尊重し、関係者全員が納得できる日程を決めましょう。
葬儀日程を決める際のポイント
- 一般的な日程:
- 故人様が亡くなった翌日に通夜、その翌々日に葬儀・告別式を行うのが一般的です。
- 参列者の都合:
- 遠方からの参列者や、仕事の都合などで参列が難しい方の都合も考慮しましょう。
- 火葬場の空き状況:
- 火葬場の空き状況によっては、希望の日程で葬儀を行えない場合があります。葬儀社と連携し、早めに火葬場の予約状況を確認しましょう。
- 宗教・宗派の儀式:
- 宗教・宗派によって、葬儀の日程や儀式の流れが異なります。葬儀社や僧侶に相談し、適切な日程を決めましょう。
- 友引:
- 友引は「友を引く」とされ、友引に火葬を行うことを避ける地域もあります。友引を避ける場合は、葬儀社に相談しましょう。
- 関係者への連絡:
- 日程が決まり次第、親族、友人、会社関係者など、速やかに連絡しましょう。
- 葬儀社との綿密な相談:
- 葬儀社は、葬儀に関する知識と経験が豊富です。葬儀社と綿密に相談することで、スムーズに日程を決められます。
葬儀と並行して行う手続き
- 死亡届の提出:
- 故人様が亡くなった日から7日以内に、市区町村役場に死亡届を提出する必要があります。
- 火葬許可証の申請:
- 火葬を行うためには、市区町村役場から火葬許可証の発行を受ける必要があります。
- 故人の銀行口座の凍結解除:
- 故人様の銀行口座は、死亡届が提出されると凍結されます。相続手続きを行い、口座の凍結を解除する必要があります。
葬儀事前準備の計画
これらの手続きは、慌ただしく進むことが多いため、事前に葬儀事前準備の計画を立てておくことで、スムーズに進められます。
- エンディングノートの作成:
- エンディングノートに、葬儀の希望や連絡先リスト、銀行口座情報などをまとめておくと、ご家族の負担を軽減できます。
- 葬儀社との事前相談:
- 葬儀社と事前に相談し、葬儀の流れや費用、必要書類などを確認しておきましょう。
- 家族との話し合い:
- 葬儀に関する希望や役割分担などを、家族で話し合っておきましょう。
葬儀は、故人様を偲び、感謝の気持ちを伝える大切な儀式です。事前にしっかりと準備をし、故人様らしい温かいお見送りをしましょう。
◇式典中のトラブル対策と予備品
葬儀の式典は、故人様を偲び、送り出す大切な時間ですが、予期せぬトラブルが起こる可能性も考慮しておく必要があります。慌ただしい状況でも落ち着いて対応できるよう、事前に準備しておくと安心です。
葬儀中に起こりうるトラブルと対策
- 衣装のトラブル
- トラブル例:
- 食べ物や飲み物をこぼしてしまった
- 服装のほつれや破れ
- 対策:
- 予備のハンカチ、ティッシュ、安全ピン、ソーイングセットなどを持参する
- シミ抜きシートやウェットティッシュも役立ちます
- 体調不良
- トラブル例:
- 頭痛、腹痛、発熱
- 慣れない服装や緊張による体調不良
- 対策:
- マスク、ティッシュ、常備薬(鎮痛剤、胃腸薬など)を持参する
- 必要に応じて、カイロや冷却シートなども準備する
- 式典中のトラブル
- トラブル例:
- 照明や音響のトラブル
- 供花の倒壊
- 対策:
- 葬儀担当者や葬儀社の連絡先を控えておく
- 事前に式場の設備や緊急時の対応について確認しておく
- 天候の変化
- トラブル例:
- 雨、雪、強風
- 気温の急激な変化
- 対策:
- 折りたたみ傘、レインコート、靴カバーなどを持参する
- 防寒具や日焼け止めなども用意しておくと安心です
- 子どものトラブル
- トラブル例:
- 子どものぐずりや泣き声
- 子どもの体調不良
- 対策:
- 子ども用のおもちゃやお菓子、絵本などを持参する
- 子ども用の着替えやタオル、おむつなども用意する
- その他
- トラブル例:
- 香典の金額不足
- 貴重品の紛失
- 対策:
- 香典の金額は事前に確認しておく
- 貴重品は肌身離さず持ち歩く
事前準備のポイント
- 持ち物リストを作成する:
- 上記のトラブル例を参考に、必要な持ち物をリストアップしておきましょう。
- 持ち物はまとめておく:
- 必要な時にすぐ取り出せるよう、持ち物は一つのバッグにまとめておきましょう。
- 葬儀担当者と連携する:
- トラブル発生時は、葬儀担当者に相談し、指示に従いましょう。
- 落ち着いて対応する:
- トラブルが発生しても、焦らず落ち着いて対応することが大切です。
家族の準備
- 役割分担:
- 葬儀中の役割分担を決めておきましょう。
- 受付、案内、会計など、誰が何を担当するかを明確にしておくことで、スムーズな対応ができます。
- 情報共有:
- 葬儀に関する情報は、家族間で共有しておきましょう。
- 特に、連絡先やスケジュールなどは、全員が把握しておくことが大切です。
- 協力体制:
- 葬儀中は、家族で協力し合い、助け合いましょう。
- 困った時は、遠慮せずに周りの人に助けを求めましょう。
葬儀は、予期せぬことが起こりやすい場面でもあります。しかし、事前に準備をしておくことで、慌てず落ち着いて対応することができます。故人様を安心して送り出すためにも、しっかりと準備をしておきましょう。
◇僧侶や司会者とのコミュニケーション
葬儀を滞りなく進めるためには、僧侶や司会者とのスムーズな連携が不可欠です。事前のコミュニケーションを密にすることで、当日も安心して式に臨むことができます。
僧侶とのコミュニケーション
- 読経のタイミングや内容の確認:
- 読経のタイミングや内容、宗派の儀式などを事前に確認しておきましょう。
- 故人様の戒名や法名についての希望も、事前に伝えておく必要があります。
- お布施に関する相談:
- お布施の金額は、寺院や地域によって異なります。
- 相場は10万円~50万円程度と言われていますが、事前に相談し、明確にしておきましょう。
- お布施の他に、お車代や御膳料が必要になる場合もあります。
- 不明点の確認:
- 葬儀に関する不明点や疑問点は、遠慮せずに僧侶に質問しましょう。
- 信頼関係を築くことで、当日も安心して式に臨めます。
司会者とのコミュニケーション
- 式典全体の進行の確認:
- 式典の流れや進行、挨拶のタイミングなどを確認しましょう。
- 故人様の経歴や人柄などを伝え、紹介してほしい内容を明確に伝えます。
- 参列者への案内:
- 参列者への案内方法や、注意事項などを確認しましょう。
- 特に、高齢の方や遠方から参列される方への配慮について相談しておきましょう。
- 希望の伝達:
- 故人様らしい式にしたいなど、希望があれば遠慮せずに伝えましょう。
- 葬儀担当者との連携:
- 司会者との連絡は、葬儀担当者を通じて行うとスムーズです。
- 葬儀担当者も交えて打ち合わせをすると、より確実です。
スムーズな葬儀のために
- 早めの相談:
- 僧侶や司会者との打ち合わせは、早めに始めましょう。
- 特に、葬儀の規模が大きい場合や、特別な要望がある場合は、余裕をもって準備を進めることが大切です。
- 情報共有:
- 打ち合わせの内容は、家族間で共有しておきましょう。
- 役割分担や連絡先などを明確にしておくことで、当日もスムーズに対応できます。
- 感謝の気持ち:
- 僧侶や司会者への感謝の気持ちを忘れずに、丁寧な言葉遣いで接しましょう。
これらの準備をしておくことで、故人様を安心して送り出すことができます。
4.葬儀後に準備しておきたいもの
◇法事・法要に必要な準備
葬儀が終わると、故人様を偲び、ご冥福をお祈りするための法事・法要の準備が始まります。ご遺族にとっては、悲しみの中、慣れない準備に追われることになり、心身ともに負担が大きい時期です。スムーズに法事・法要を進めるために、事前に準備しておくと安心です。
法事・法要の種類と時期
- 初七日法要:
- 故人様が亡くなってから7日目に行う法要です。
- 近年では、葬儀・告別式の後、繰り上げて行うことが多くなっています。
- 四十九日法要(満中陰法要):
- 故人様が亡くなってから49日目に行う法要です。
- 忌明けの法要として、重要な意味を持ちます。
- 一周忌法要:
- 故人様が亡くなってから1年目に行う法要です。
- 三回忌法要:
- 故人様が亡くなってから満2年目に行う法要です。
- 七回忌法要、十三回忌法要、十七回忌法要、二十三回忌法要、二十七回忌法要、三十三回忌法要、五十回忌法要、百回忌法要:
- 年数が経つにつれて、規模を縮小していくのが一般的です。
法事・法要の準備
- 寺院・僧侶への依頼:
- 法事・法要の日程が決まり次第、早めに寺院・僧侶に依頼しましょう。
- お布施の準備:
- お布施の金額は、寺院や地域によって異なります。事前に確認しておきましょう。
- 参列者の招待:
- 参列者の人数を把握し、会場の選定や料理の手配を行います。
- 案内状を送る場合は、法要の日時、場所、施主の名前などを記載します。
- 香典返し・引き出物の準備:
- 香典返しは、いただいた香典の半額から3分の1程度の品物を用意するのが一般的です。
- 引き出物は、参列者へのお礼として渡します。
- 供物の準備:
- 供物は、果物、お菓子、花などが一般的です。
- 宗教・宗派によって、供物の種類や飾り方が異なる場合があります。
準備をスムーズに進めるために
- 葬儀担当者や寺院への相談:
- 法事・法要に関する知識や経験が豊富な葬儀担当者や寺院に相談することで、スムーズに準備を進められます。
- 事前準備の計画:
- 法事・法要の日程、場所、参列者の人数、料理、引き出物などをリストアップし、計画的に準備を進めましょう。
- 親族との連携:
- 法事・法要の準備は、親族と協力して行うと、負担を軽減できます。
法事・法要は、故人様を偲び、ご冥福をお祈りする大切な儀式です。心を込めて準備し、故人様を供養しましょう。
◇お返し品選びの注意点
葬儀後のお返し品選びは、故人様への供養の気持ちと、いただいた香典への感謝の気持ちを伝える大切な準備です。地域の慣習やマナーを考慮し、失礼のないように品物を選びましょう。
お返し品選びの注意点
- 地域の慣習を確認する:
- 地域によって、お返し品の選び方や金額、渡す時期などが異なる場合があります。
- 葬儀担当者や地域の年長者に相談し、地域の慣習を確認しましょう。
- 金額の目安:
- 一般的に、いただいた香典の半額から3分の1程度の品物を選ぶのがマナーとされています。
- 高額の香典をいただいた場合は、3分の1程度の品物でも失礼にはあたりません。
- 品物の選び方:
- 「消え物」と呼ばれる、後に残らない消耗品が適しています。
- 例:お茶、海苔、タオル、洗剤など
- 最近では、カタログギフトも人気があります。
- 受け取った方が好きなものを選べるため、喜ばれることが多いです。
- 「消え物」と呼ばれる、後に残らない消耗品が適しています。
- 包装・挨拶状:
- お返し品には、掛け紙をかけ、挨拶状を添えるのが丁寧です。
- 掛け紙は、黒白または黄白の結び切りを使用します。
- 挨拶状には、香典へのお礼と、忌明けの報告などを記載します。
- 時期:
- 香典返しは、四十九日法要後1ヶ月以内に行うのが一般的です。
- 葬儀当日に香典返しを行う「当日返し」もあります。
その他
- 忌み言葉を避ける:
- お返し品の品物や包装、挨拶状には、忌み言葉(「重ね重ね」「度々」など)を使用しないように注意しましょう。
- 相手の好みを考慮する:
- 親しい間柄の方には、相手の好みに合わせた品物を選ぶのも良いでしょう。
- 葬儀担当者への相談:
- お返し品選びに迷った場合は、葬儀担当者に相談しましょう。
お返し品は、故人様への供養の気持ちと、感謝の気持ちを伝える大切な贈り物です。マナーを守り、心を込めて選びましょう。
◇費用の見直しと家計管理のポイント
葬儀費用は、予期せぬ出費であり、ご遺族にとって大きな負担となることがあります。スムーズな支払いと、その後の経済的な負担を軽減するために、以下の点に注意しましょう。
葬儀費用の支払い時期と準備
- 支払い時期:
- 一般的には、葬儀後1週間から10日以内に請求書が届き、その後支払います。
- 葬儀社によって支払い時期が異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
- 費用の準備:
- 故人様の預金口座は、死亡届提出後に凍結されることが多いため、葬儀費用は現金やご遺族の預貯金から支払う必要があります。
- 事前に葬儀費用の見積もりを取り、ある程度の金額を用意しておくと安心です。
- 費用の内訳確認:
- 請求書が届いたら、費用の内訳をよく確認しましょう。
- 不明な点があれば、葬儀担当者に質問し、納得した上で支払うようにしましょう。
葬儀後の費用と家計管理
- 葬儀後の費用:
- 葬儀後には、法事・法要、香典返し、仏壇・仏具の購入など、さまざまな費用が発生します。
- これらの費用も考慮し、家計管理を行いましょう。
- 領収書の保管:
- 葬儀や法事・法要に関する領収書は、大切に保管しておきましょう。
- これらの領収書は、相続税の控除対象となる場合があります。
- また、今後の法事・法要の費用を見積もる際の参考にもなります。
葬儀担当者との相談
- 費用の相談:
- 葬儀費用や支払い方法について、葬儀担当者に相談しましょう。
- 葬儀費用を抑えるためのアドバイスや、支払い方法の提案を受けられる場合があります。
- 各種手続きの相談:
- 葬儀後の各種手続き(死亡届の提出、相続手続きなど)についても、葬儀担当者に相談しましょう。
- 専門家を紹介してもらえる場合があります。
その他
- 葬儀保険の活用:
- 葬儀費用に備えて、葬儀保険に加入しておくことも検討しましょう。
- 葬儀保険は、葬儀費用をカバーするだけでなく、遺族の経済的な負担を軽減する役割も果たします。
- 公的支援制度の活用:
- 自治体によっては、葬儀費用の一部を補助する制度があります。
- お住まいの地域の役所に問い合わせてみましょう。
葬儀費用は、高額になることが多いため、事前にしっかりと準備しておくことが大切です。葬儀担当者と相談しながら、計画的に進めましょう。
◇遺族間の打ち合わせと共有事項
葬儀後に行う遺族間の打ち合わせは、今後の手続きや故人様の供養を円滑に進める上で非常に重要です。悲しみの中ではありますが、落ち着いて話し合いの場を設けましょう。
打ち合わせの主な内容
- 葬儀費用の精算:
- 葬儀社からの請求書を確認し、費用の内訳や支払い方法について話し合います。
- 領収書は大切に保管し、今後の法要費用や相続手続きの参考にしましょう。
- 香典の整理と分配:
- 香典の金額や記帳内容を確認し、香典返しの手配や分配方法について話し合います。
- 香典帳は、後々の法要や年賀欠礼の連絡などに使用するため、大切に保管します。
- 法事・法要のスケジュール調整:
- 四十九日、一周忌、三回忌など、今後の法要のスケジュールを決めます。
- 寺院や僧侶への依頼、会場の予約、参列者の招待など、具体的な準備についても話し合います。
- 遺産相続に関する話し合い:
- 遺言書の有無や、相続人の範囲、遺産の分け方について話し合います。
- 必要に応じて、弁護士や税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。
- 故人の遺品整理:
- 故人様の遺品をどのように整理するか、方針を決めます。
- 形見分けや供養の方法についても話し合いましょう。
- 各種手続きの確認:
- 死亡届や火葬許可証の提出、故人様の銀行口座の凍結解除、年金や保険の手続きなど、必要な手続きを確認し、分担して進めます。
円滑なコミュニケーションのために
- 早めに話し合いの場を設ける:
- 葬儀後、落ち着いたら早めに話し合いの場を設けましょう。
- 情報共有を徹底する:
- 話し合いの内容や決定事項は、遺族間で共有し、認識のズレを防ぎましょう。
- 故人の遺志を尊重する:
- 遺産相続や供養の方法については、故人様の遺志を尊重することを心がけましょう。
- 感情的にならない:
- 悲しみや疲労から、感情的になりやすい時期ですが、冷静に話し合いを進めましょう。
- 専門家の助言を求める:
- 複雑な手続きやトラブルが発生した場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。
遺族間の協力と円滑なコミュニケーションは、葬儀後の様々な手続きや故人様の供養を滞りなく進めるために不可欠です。
葬儀の準備は、故人様を送り出すために非常に重要ですが、多くの人が何を準備すれば良いか分からずに困ってしまうのが現状です。ここでは、葬儀に必要な持ち物や準備に関するQ&A集を作成しました。
葬儀の持ち物に関するQ&A
Q1: 葬儀に参列する際、必ず持参すべきものは何ですか?
A1: 香典、袱紗、数珠、ハンカチは、葬儀に参列する際に必ず持参すべき基本的な持ち物です。
Q2: 葬儀に参列する際の服装のマナーは?
A2: 葬儀に参列する際は、喪服を着用するのが基本です。男性はブラックスーツ、女性は黒のワンピースやスーツを選び、光沢のない黒靴を履きましょう。アクセサリーは結婚指輪以外は控え、派手なネイルやメイク、香水は避けるべきです。
Q3: 故人の棺に納める副葬品として適切なものは?
A3: 故人の写真、手紙、愛用の品などが一般的ですが、火葬の際に燃えやすいものや腐敗しないものを選ぶ必要があります。ガラスや金属類、プラスチック製品などは避けましょう。
Q4: 葬儀の準備で必要な書類は?
A4: 死亡診断書、故人の戸籍謄本、住民票の除票などが必要です。これらの書類は、葬儀の手続きだけでなく、相続手続きや保険金の請求など、葬儀後の手続きにも必要となります。
Q5: 葬儀中に持参すると便利なものは?
A5: 予備のハンカチやティッシュ、常備薬、雨具などがあると便利です。特に、お子様連れの場合は、おもちゃやお菓子、着替えなども用意しておくと安心です。
Q6: 香典の金額はどのように決めるべきですか?
A6: 故人との関係性や自身の年齢、社会的立場によって異なります。一般的な目安としては、親族であれば1万円~10万円、友人・知人や職場関係者であれば5千円~1万円程度です。
Q7: 数珠の選び方と扱い方のマナーは?
A7: 略式数珠は宗派を問わず使用できます。素材や房の色、サイズなど、自身のスタイルに合った数珠を選びましょう。数珠は左手に持ち、合掌する際は両手の中指にかけます。使用しない時は数珠袋に入れて保管しましょう。
Q8: 葬儀の手土産や供物として適切なものは?
A8: 果物、菓子類、花などが一般的ですが、宗教・宗派に合わせた品物を選びましょう。香りが強すぎるものや殺生を連想させるもの、日持ちしないものは避けるべきです。
Q9: 葬儀で弔辞や挨拶を頼まれた場合、どのような準備が必要ですか?
A9: 故人との関係性や思い出、人柄などを考慮した内容にし、葬儀担当者に形式や流れを確認しましょう。
Q10: 葬儀後に遺族が行うべき準備は何ですか?
A10: 法事・法要の準備、香典返し、遺品整理、各種手続きなどがあります。これらは、葬儀後も故人を偲び、供養するための大切な準備です。
Q11: 葬儀費用の支払い時期と準備は?
A11: 葬儀後1週間から10日以内に支払うことが一般的ですが、葬儀社によって異なるため事前に確認しましょう。故人の預金口座は凍結されることが多いため、ある程度の金額を用意しておく必要があります。
Q12: 葬儀後、遺族間で話し合うべきことは?
A12: 葬儀費用の精算、香典の整理と分配、法事・法要のスケジュール調整、遺産相続に関する話し合い、故人の遺品整理、各種手続きの確認などがあります。
執筆者 監修者
執筆者:畑尾一心
創業昭和30年 熊本県儀式共済株式会社
ハタオ葬儀社 3代目 代表取締役社長
1972年、熊本で50年余年続く葬儀店に生まれる。
葬祭業に従事して30年
現在、年間約400件を超えるご葬儀、ご相談に携わっています。
NPO法人全国葬送支援協議会熊本中央本部 代表
厚生労働省認定葬祭ディレクター技能審査 1級葬祭ディレクター
一般社団法人 終活協議会 終活セミナー講師 終活ガイド資格3級
一般社団法人 終活カウンセラー協会 終活カウンセラー
創業者、会長の想いを引き継ぎながら
日本独自の葬送文化の意味を現代の意味を感じて頂き
後悔の無いお葬式を大切に葬儀の仕事に取り組んでいます。
趣味は、散歩。近所はもちろん、知らない街をあることで
その地域に住む人たちとのコミュニケーションを楽しんでいます。
【ハタオ葬儀社へのお問い合わせ】
〒 862-0949 熊本市中央区国府1丁目12-15
tel:096-364-3220 fax:096-372-5685
e-mail:info@hataosougisha.com
【ハタオ葬儀社の事前相談】
ハタオ葬儀社では、事前相談も承っております。事前相談では、経験豊富な専門スタッフが、ご葬儀の流れや費用、準備することなどを、丁寧にご説明いたします。
事前相談は、ご家族の皆様が、ご自身のペースで、納得のいくご葬儀を準備するための大切な時間だと、ハタオ葬儀社では閑雅ています。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
監修者 畑尾義興
創業 昭和30年 熊本県儀式共済株式会社
ハタオ葬儀社 会長
昭和30年より、熊本の地で先代畑尾義人により創業されたハタオ葬儀社を引継ぎ約40年、創業者の思いである「誰もが誇りと思えるお葬式」を基に経営を引き継ぎ。自身の葬儀の体験から家族の思いがかよい、心と費用の負担を軽くするお手伝いを大切に、地元の感謝の思いを込めて葬儀の仕事一筋に取り組んできました。趣味は釣り、囲碁。熊本の自然と友人との時間を楽しんでいます。
葬儀場の詳細を見る
公営斎場もご利用になれます

【公営斎場】熊本市斎場
住 所
〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町796
アクセス
熊本市役所から車で、約35分

【公営斎場】菊池火葬場
住 所
〒861-1315 熊本県菊池市木柑子1318
アクセス
阿蘇高原線 三里木駅からタクシー24分

【公営斎場】大津火葬場
住 所
〒869-1233 熊本県菊池郡大津町大字大津110
アクセス
豊肥本線「肥後大津駅」からタクシーで5分