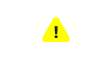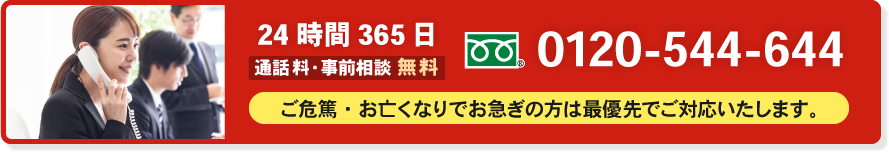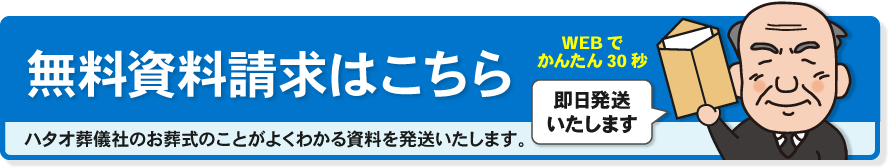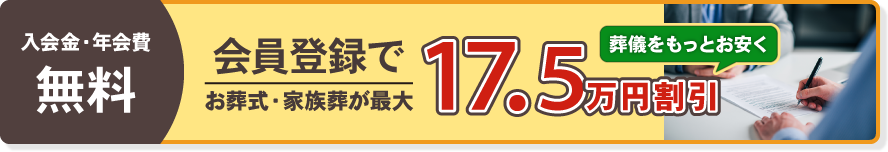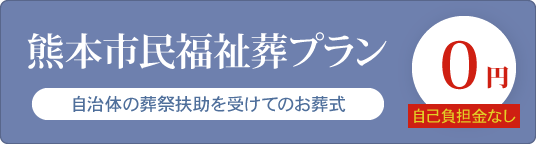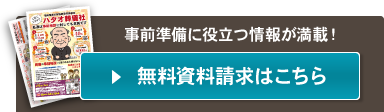新着情報
2025.05.15
不安が和らぐ 葬儀の服装マナー完全ガイド|喪服の選び方、家族葬での注意点まで【ハタオ葬儀社】
① はじめに
葬儀を前に、様々な準備で心身ともにお疲れのことと存じます。大切な方を送るという大変な時に、服装のことにまで気が回らない、どうしたら良いか分からない、という方も少なくないでしょう。特に、葬儀の服装マナーについては、普段あまり経験することではないため、「これで合っているのだろうか?」「失礼はないだろうか?」と不安に感じやすい点かもしれません。
葬儀における服装マナーは、単なる形式的なルールではなく、故人様への深い「感謝」の気持ちや、在りし日を「あたたかくお偲びする」心、そしてご遺族様への配慮を表す、大切な方法の一つです。整えられた服装は、お別れの場にふさわしい落ち着いた雰囲気を作り出し、故人様との最後の時間を心穏やかに過ごすためにも役立ちます。
私たちハタオ葬儀社は、「感謝で送り、あたたかい雰囲気で、人のつながりを大切にする、花いっぱいのお葬式」を心を込めてお手伝いしております。大切な方とのお別れの時間を、後悔なく、心穏やかに過ごしていただくために、葬儀に関するあらゆる面で、皆様に寄り添い、正確で安心できる情報を提供したいと考えております。この記事が、葬儀の服装に関するあなたの疑問や不安を解消し、大切な方を心を込めて送るための一助となれば幸いです。どうぞ、安心して読み進めてください。
② このような方へおすすめ
✅初めて葬儀に参列する、または主催する方。
✅喪服の選び方やマナーに自信がない方。
✅家族葬に参列する際の服装が知りたい方。
✅急な参列で何を着るべきか困っている方。
✅葬儀社選びに不安を感じており、信頼できる情報を探している方。
③ 目次
1. 葬儀における喪服の基本を知ろう
1-1. 「喪服」とは?その役割と種類(正喪服、準喪服、略喪服)を分かりやすく解説
1-2. 適切な喪服選びの3つの基本ポイント(色、素材、デザイン)
1-3. 喪服はいつまでに準備するべき?購入・レンタル・手持ちの服で対応するケース
2. 参列する立場別の服装マナー
2-1. 遺族・親族として参列する場合の格式高い喪服
2-2. 一般参列者として弔問する場合の適切な服装
2-3. 子供の喪服・服装マナー
3. 男性・女性別の具体的な服装と身だしなみ
3-1. 男性の喪服(ブラックスーツ)の正しい着こなし方と小物
3-2. 女性の喪服(ブラックフォーマル)の選び方と注意点
3-3. 葬儀でのメイク、髪型、アクセサリー、ネイルのマナー
4. 家族葬など、葬儀形式による服装の違い
4-1. 「家族葬」における服装の考え方と一般的な傾向
4-2. 「平服でお越しください」と言われた場合の適切な服装レベル
4-3. 急な弔問や通夜における服装の注意点
5. 服装以外に気をつけたい葬儀のマナー
5-1. バッグ・靴・コートなどの持ち物マナー
5-2. 香水や派手な装飾品、光る素材のNG例
5-3. 季節ごとの服装調整と防寒・暑さ対策
【大切な方への想い、どう伝えられたか。お客様の「声」をご覧ください】
【葬儀の「分からない」をもっと解消しませんか?】
【ハタオ葬儀社へのお問い合わせ】
【ご家族のペースで、納得いくまで丁寧なハタオ葬儀社の事前相談】
④ 不安が和らぐ 葬儀の服装マナー完全ガイド|喪服の選び方、家族葬での注意点まで
1. 葬儀における喪服の基本を知ろう
この度は、大切な方を送るという、大変お辛い状況の中、葬儀のご準備をされていることと存じます。心身ともにお疲れのことと存じますが、そのような中で、服装のことまで気が回らない、どうすれば良いかと迷われるお気持ちもきっとあることでしょう。
普段、葬儀の服装マナーに触れる機会はほとんどありませんので、「これで良いのだろうか?」「失礼にあたらないだろうか?」と不安に感じてしまうのは、決して特別なことではなく、自然なことです。どうぞ、ご自分を責めたりなさらないでください。
このセクションでは、そんなあなたの不安を少しでも和らげるために、葬儀における「喪服」とは何か、その基本的な考え方や、知っておきたい種類、そして、これだけは押さえておきたい適切な喪服選びのポイントを、一つ一つ丁寧にご案内いたします。
服装の心配が少しでも軽くなり、大切な方とのお別れの時間を、より心穏やかに、そして故人様へ心を込めて向き合えるためのお手伝いができれば、これほど嬉しいことはありません。どうぞ、安心して読み進めてください。
1-1. 「喪服」とは?その役割と種類(正喪服、準喪服、略喪服)を分かりやすく解説
「喪服」とは、故人様への哀悼の意を表し、ご遺族様への深い配慮を示すために着用する衣服です。お別れの場にふさわしい装いをすることで、静かに故人様を偲び、弔意を示す大切な役割があります。
喪服には、主に三つの格式があります。
1.正喪服(せいもふく): 最も格式の高い喪服です。モーニングコート(男性)やブラックフォーマルスーツ、丈の長いワンピース、黒無地の着物(女性)などがあります。主に喪主や三親等以内のご遺族が、葬儀・告別式や一周忌までの法要で着用することがありますが、近年では準喪服が選ばれるケースが多くなっています。
2.準喪服(じゅんもふく): 一般的に、葬儀や告別式に参列する際に最も多く着用される喪服です。ブラックスーツ(男性)や、ブラックフォーマルと呼ばれる黒無地のワンピース、アンサンブル、スーツ(女性)を指します。ご遺族が着用することも多く、迷ったらこの準喪服を選べばまず間違いありません。
3.略喪服(りゃくもふく): 正喪服や準喪服以外で、弔いの場にふさわしい地味な服装を指します。黒、紺、グレーなどのダーク系の地味な色のスーツやワンピースなどです。通夜や三回忌以降の法要、または「平服でお越しください」と案内があった場合に着用されます。
一般的に、私たちが葬儀や告別式に参列する際には「準喪服」を着用することが多いと覚えておきましょう。
1-2. 適切な喪服選びの3つの基本ポイント(色、素材、デザイン)
どのような喪服を選べば良いか迷ったときは、以下の3つの基本ポイントを思い出してください。
- 色: 基本は「黒」です。ただし、普段着の黒ではなく、光沢のない、より深みのある「漆黒」が望ましいとされています。生地の色が薄い黒や、他の色が入っているものは避けてください。
- 素材: 光沢のあるサテンやシルク、エナメルなどの素材は、慶事を連想させるため避けるべきです。レースやフリルなども控えめなものを選びましょう。ウールやポリエステルなど、派手さがなく落ち着いた印象の素材が適しています。
- デザイン: 肌の露出は極力控えます。男性は襟付きのシャツにブレザーやスーツ、女性は袖があり、スカート丈が膝下またはロング丈のワンピースやアンサンブルが一般的です。デザインはシンプルで装飾の少ないものを選び、身体のラインを強調するようなものは避けます。
これらの基本ポイントを押さえることで、故人様やご遺族に対して失礼のない、心遣いの伝わる装いとなります。
1-3. 喪服はいつまでに準備するべき?購入・レンタル・手持ちの服で対応するケース
「備えあれば憂いなし」と言いますが、訃報は突然届くことがほとんどです。慌てずに済むよう、喪服はできれば前もって準備しておくことをお勧めします。
喪服を用意する方法としては、主に以下の3つがあります。
- 購入: 一度購入すれば、体型が変わらない限り長く使用できます。デパートのフォーマルウェア売り場や紳士服店、ブラックフォーマル専門店、最近ではオンラインでも購入可能です。体型に合わせて仕立てたり、急な必要に備えて早めに準備しておくと安心です。
- レンタル: 頻繁に着用する機会がない方や、サイズが変わってしまった場合、急に必要になった場合に便利です。葬儀社や、フォーマルウェアのレンタル専門店で借りることができます。クリーニングの手間がなく、必要な時にぴったりのサイズを選べるメリットがあります。ハタオ葬儀社でも、提携またはご紹介にて手配が可能ですのでお早めにご相談ください。
- 手持ちの服で対応: 略喪服で良い場合(通夜など)や、どうしても準喪服の準備が間に合わない場合に限られます。この場合でも、黒やダーク系の地味な色で、デザインがシンプルで露出の少ない服を選び、アクセサリーなどを外すなど、最大限マナーに配慮することが重要です。
どのような方法で準備するにしても、いざという時に困らないよう、一度ご自身の状況を確認しておくことをお勧めします。
この内容が、葬儀の服装について基本的な理解を深める一助となれば幸いです。次の項目では、参列する立場ごとのより具体的なマナーについて詳しく見ていきましょう。
2. 参列する立場別の服装マナー
喪服の基本的な考え方や種類についてご理解いただけたでしょうか。続いては、葬儀に参列される皆様と故人様との「つながり」、つまり関係性によって、服装の選び方がどのように変わってくるかを見てまいります。
これは、単にルールがあるからというだけでなく、故人様への想いの深さや、お見送りの場でのそれぞれの役割を考えた、大切な「配慮」の形でもあります。それぞれの立場にふさわしい服装を選ぶことが、故人様への敬意を表し、ご遺族様への心遣いを示すことにつながるのです。
ここでは、ご遺族・ご親族としての場合、ご友人や知人、会社関係者といった一般参列者としての場合、そして大切な宝物であるお子様の服装について、それぞれの立場に合わせた服装マナーを分かりやすくご案内いたします。それぞれの立場で、心を込めて故人様を送るために、服装がどのような役割を果たすのかを考えながら読み進めていただければ幸いです。
2-1. 遺族・親族として参列する場合の格式高い喪服
故人様のご遺族や、三親等以内の近しいご親族として参列される方は、弔いの場を主催、または中心となって故人様を送る立場です。そのため、参列者の中でもっとも格式の高い服装を選ぶのが一般的なマナーとされています。
準喪服が一般的: 以前は正喪服(モーニングや黒留袖など)を着用する方が多かったですが、近年では準喪服(ブラックスーツやブラックフォーマル)を着用されるご遺族様が最も多くなっています。通夜・葬儀・告別式を通して準喪服で参列されるのが一般的です。
正喪服の場合: 地域や家系の習慣によっては、喪主やごく近い方が正喪服を選ばれることもあります。
格式を揃える: ご家族・ご親族間で服装の格式をある程度揃えることも大切です。事前に話し合っておくと安心でしょう。
遺族・親族としての服装は、故人様への最大限の敬意を表すとともに、弔問客を迎える立場としての礼儀を示すものとなります。
2-2. 一般参列者として弔問する場合の適切な服装
ご友人、会社関係者、地域の方など、一般参列者として葬儀や告別式に弔問される場合は、基本的に「準喪服」を着用するのが最も丁寧なマナーとされています。
- 準喪服(ブラックスーツ、ブラックフォーマル): 光沢のない、深みのある黒のスーツやアンサンブルがこれにあたります(詳しい選び方は前述の項目をご参照ください)。これは、弔意を示し、失礼のないようにするという意味合いが込められています。
- 略喪服の場合: 通夜に駆けつける場合や、訃報を急に知って準喪服の準備が間に合わないといったやむを得ない場合は、「略喪服」でも許容されることがあります。黒、紺、グレーなどのダーク系の地味な色のスーツやワンピースなど、控えめな服装を選びましょう。ただし、アクセサリーなどは外し、華美にならないように注意が必要です。
- 遺族より控えめに: 一般参列者は、ご遺族様よりも格式の高い服装にならないよう配慮することもマナーの一つです。正喪服での参列は避けるのが一般的です。
大切なのは、故人様を悼む気持ちと、ご遺族様への配慮です。準喪服を準備しておけば、ほとんどの場合に対応できますので安心です。
2-3. 子供の喪服・服装マナー
お子様が葬儀に参列する場合の服装は、大人ほど厳格ではありませんが、落ち着いた色合いを選ぶことが大切です。
学生服がある場合: 小学生以上の場合は、学校の制服を着用するのが最もふさわしい服装です。制服は正装とみなされます。
制服がない場合: 制服がない小さなお子様や大学生の場合は、黒、紺、グレーなどの地味な色の服装を選びます。
男の子: 白いシャツに、黒、紺、グレーなどのズボンとブレザー、またはカーディガンなど。靴下も地味な色(白、黒、紺など)を選びます。
女の子: 白いブラウスに、黒、紺、グレーなどのスカートやワンピースなど。靴下やタイツも地味な色(白、黒、紺など)を選びます。
避けるべきもの: 明るい色や派手な柄、キャラクターものの服や靴下は避けてください。光る素材や華美なアクセサリー(制服に付いているボタンなどは除く)も不要です。靴もスニーカーよりは落ち着いた色のシンプルなものが望ましいです。
お子様の場合も、お別れの場にふさわしい清潔感のある落ち着いた装いを心がけましょう。
このように、参列する立場によって適切な服装には違いがあります。ご自身の立場に合った服装を選ぶことが、故人様への敬意とご遺族様への配慮につながります。次の項目では、男性・女性それぞれの具体的な服装のポイントについて詳しく解説します。
3. 男性・女性別の具体的な服装と身だしなみ
喪服の基本や、ご自身の立場に合わせた選び方について、少しずつご理解が深まってきたことと存じます。これで、服装の全体像はつかめてきたのではないでしょうか。
続いては、より具体的に、男性は男性の、女性は女性の服装について、そして、お見送りの場にふさわしい身だしなみ全般のポイントを見てまいりましょう。スーツの着こなし方、ワンピースの選び方、そしてメイクや髪型、小物といった、一見細かく思える部分にまで心を配ることは、単なるルールではなく、故人様への真心を静かに表し、また、お見送りに来られた皆様や、悲しみの中にいらっしゃるご遺族様への大切な「配慮」を示すことにつながります。
ここでは、男性のブラックスーツの正しい着こなし方と小物、女性のブラックフォーマルの選び方と注意点、そして、葬儀でのメイクや髪型、アクセサリー、ネイルといった身だしなみ全般のマナーを、一つ一つ丁寧にご案内いたします。細部まで整えることで、安心して、故人様との大切なお別れの時間を過ごしていただけるよう、お手伝いできれば幸いです。
3-1. 男性の喪服(ブラックスーツ)の正しい着こなし方と小物
男性の喪服として最も一般的な準喪服は、ブラックスーツです。ビジネススーツの黒とは異なる、より深い黒(漆黒)を選びます。正しい着こなしと小物選びのポイントは以下の通りです。
- スーツ: 光沢のない、深い黒色のシングルまたはダブルのスーツを選びます。スリーピースでも構いません。
- シャツ: 白無地のレギュラーカラーシャツを着用します。ボタンダウンや織り柄、ストライプ、チェック柄などは避けてください。
- ネクタイ: 黒無地のネクタイを着用します。光沢のある素材や、柄入りのものはNGです。結び目はディンプル(くぼみ)を作らず、シンプルに整えます。ネクタイピンは原則不要です。
- ベルト: 黒無地で、金具が派手でないシンプルなものを選びます。
- 靴下: 黒無地の靴下を着用します。座った時などに肌が見えないよう、くるぶし丈や短いものは避け、ふくらはぎの中間程度の長さがあるものが望ましいです。
- 靴: 黒無地で、光沢のない革製のビジネスシューズが基本です。内羽根式のデザイン(ストレートチップなど)が最も格式が高いとされます。エナメル素材やスエード、ローファー、ブーツ、スニーカーは避けてください。
- カバン: 必要であれば、黒無地で光沢のないシンプルなセカンドバッグやブリーフケースなどを持参します。派手なブランドロゴが入ったものは避けます。
頭からつま先まで、落ち着いた「黒」で統一し、清潔感のある着こなしを心がけましょう。
3-2. 女性の喪服(ブラックフォーマル)の選び方と注意点
女性の喪服(ブラックフォーマル)は、デザインの選択肢が男性よりもやや広いですが、控えめで露出を抑えたものを選ぶことが重要です。
服装の種類: 光沢のない黒無地のワンピース、アンサンブル(ワンピースとジャケットの組み合わせ)、またはスーツが基本です。
・スカート丈: 必ず膝が隠れる丈を選びます。椅子に座った時にも膝が見えないように、膝下丈~ロング丈が安心です。
・袖の長さ: 原則として長袖、または七分袖を選びます。夏場でも肩や腕の露出が多いノースリーブは避けるべきマナー違反です。もしノースリーブのワンピースしか手元にない場合は、必ず上着(ジャケットやカーディガンなど)を羽織るようにしましょう。
ストッキング・タイツ: 黒無地のストッキングかタイツを着用します。夏場でも素足はNGです。肌色ストッキングや柄物、ラメ入りなども避けてください。
靴: 黒無地で、光沢のない素材のパンプスを選びます。ヒールは高すぎず、歩きやすい3~5cm程度の安定感のあるものが適しています。ミュールやサンダル、ブーツ、柄物、金具が派手なものは避けてください。
バッグ: 布製または光沢のない革製の黒無地のものを選びます。金具が目立つものや、アニマル柄(ファーやクロコダイルなど)、ブランドロゴが大きく入ったものは避けます。小さめのハンドバッグなどが一般的です。
落ち着いたデザインと素材を選び、肌の露出を控えることが、女性の喪服マナーの基本です。
3-3. 葬儀でのメイク、髪型、アクセサリー、ネイルのマナー
服装だけでなく、お顔や手元などの身だしなみも大切です。弔意を示す場にふさわしい、控えめな装いを心がけましょう。
メイク: 葬儀では「薄化粧(片化粧)」が基本です。派手な色のアイシャドウ、チーク、口紅は避け、ナチュラルな肌色を基調とした、健康的に見える程度の控えめなメイクをします。ラメやパール入りの化粧品も控えてください。
髪型: 清潔感があり、顔にかからないように整えます。長い髪は一つにまとめるのが一般的です。派手なヘアアクセサリー(シュシュや飾りのついたゴムなど)は避け、黒のシンプルなゴムやピンを使用します。
アクセサリー: 結婚指輪以外のアクセサリーは、原則として控えるか、控えめなものを選びます。つける場合は、一連のパールのネックレスとイヤリング(ピアス)のみが許容範囲とされています。二連以上のネックレスは「不幸が重なる」ことを連想させるためNGです。光るダイヤや色石、プラチナ・ゴールドが強く主張するアクセサリーは避けてください。
ネイル: 派手な色や装飾のあるネイル(ジェルネイル含む)は避けるのがマナーです。ベージュ、クリア、淡いピンクなど、目立たない色にするか、何もつけないのが無難です。落とす時間がない場合は、黒のシンプルな手袋を着用するという方法もあります。
香水: 香水はつけないのがマナーです。体臭が気になる場合は、無香料のデオドラントを使用するなど、最低限の配慮に留めます。
身だしなみは、故人様への敬意と、周りの方への配慮を示す無言のメッセージです。細部まで気を配ることで、より丁寧な弔意を表すことができます。
男性・女性それぞれの服装と身だしなみのポイントについて解説しました。これで、ご自身の服装を整える際の具体的なイメージが湧いてきたのではないでしょうか。次の項目では、家族葬など、葬儀の形式による服装の違いについて見ていきましょう。
4. 家族葬など、葬儀形式による服装の違い
近年、故人様とご家族、親しい方々で温かく向き合う「家族葬」など、葬儀の形式も多様化し、ご家族の想いに寄り添う形が増えていますね。大規模な一般葬とは異なる形式の場合、「服装は、いつも通りで良いのだろうか?」「案内に『平服で』とあったけれど、具体的にどういう服装が良いのだろう?」と、少し戸惑うことがあるかもしれません。
でもご安心ください。どのような形式であっても、故人様への大切な想いに変わりはありません。服装は、その想いを静かに、そして適切に形にするための一つの方法です。形式が異なれば、それに合わせた服装の考え方があることを知っておけば、慌てずに対応できます。
ここでは、家族葬における服装の基本的な考え方や、「平服でお越しください」と言われた場合の具体的な装い、そして、急な弔問や通夜における服装の注意点について、分かりやすくご説明いたします。ご遺族の皆様の意向を大切にしつつ、ご自身の心も穏やかに、お見送りの場に参加するための一助となれば幸いです。
4-1. 「家族葬」における服装の考え方と一般的な傾向
家族葬は、ご家族や親しいご親族を中心に、少人数で執り行われる葬儀です。「近親者のみで行うから、服装も略式で良いのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際には多くの家族葬で、ご遺族・ご親族、そしてごく一部の参列者も「準喪服」を着用されています。
これは、たとえ参列者が少なくても、故人様をきちんとお見送りし、弔意を示す場であることに変わりはないからです。格式を重んじるという意味合いから、準喪服が選ばれることが一般的です。
ただし、ご遺族の意向で「服装は平服で」と案内されるケースもあります。この「平服」の定義は人によって受け取り方が異なるため、迷う方が多いのも事実です。不安な場合は、事前にご遺族や葬儀社に確認することをお勧めします。
4-2. 「平服でお越しください」と言われた場合の適切な服装レベル
ご遺族から「平服でお越しください」と案内があった場合、これは普段着やカジュアルな服装で来て良いという意味ではありません。葬儀における「平服」とは、「喪服(準喪服や正喪服)でなくて構いませんが、弔いの場にふさわしい、地味で控えめな服装で」という意味合いです。
具体的には、以下のような服装を選びます。
- 男性: 黒、紺、濃いグレーなどのダーク系の地味な色のスーツに、白無地のシャツ、地味な色のネクタイ(黒無地でなくても構いませんが、派手な色柄は避けます)。
- 女性: 黒、紺、濃いグレー、茶色などの地味な色のワンピース、アンサンブル、スーツ、またはブラウスとスカートの組み合わせ。露出を控えたデザインを選びます。
ジーンズ、Tシャツ、スウェット、サンダル、スニーカー、明るい色や派手な柄の服など、カジュアルすぎる服装は絶対に避けるべきでしょう。故人様やご遺族への配慮を忘れず、地味で落ち着いた装いを心がけましょう。
4-3. 急な弔問や通夜における服装の注意点
訃報は突然届くため、すぐに駆けつけたいけれど、喪服の準備が間に合わない、という状況も起こり得ます。特に通夜は、本来は故人様と一夜を過ごし、急な弔問に駆けつけるという意味合いが強いため、服装についても配慮が必要です。
- 通夜に駆けつける場合: 仕事帰りなどで着替える時間がない場合は、地味な色の普段着や、ダーク系のビジネススーツで参列しても失礼にはあたりません。「急いで駆けつけました」という気持ちの表れでもあるからです。ただし、アクセサリーは外し、ネクタイの色を地味なものにするなど、可能な範囲で弔意を示す配慮はしましょう。
- 葬儀・告別式の場合: 一方、葬儀・告別式は、故人様を最終的に見送るための厳粛な儀式です。原則として「準喪服」で参列するのが正式なマナーとされています。 もし通夜に略装で参列し、そのまま葬儀・告別式にも参列する場合は、できる限り準喪服に着替えるのが望ましいです。もし準備が難しければ、通夜と同じくダーク系の服装で、最大限の配慮を持って参列することになりますが、基本は準喪服であることを念頭に置いておきましょう。
急な場合に、服装で悩んで参列をためらう必要はありません。大切なのは故人様を悼む気持ちです。ただし、できる限りの配慮は心がけましょう。
葬儀形式や状況に応じた服装の考え方についてご理解いただけたでしょうか。故人様やご遺族の意向、そしてご自身の立場に合わせた適切な服装を選ぶことが大切です。次の項目では、服装以外の小物や身だしなみについて、さらに詳しく注意点をお伝えします。
5.服装以外に気をつけたい葬儀のマナー
喪服の種類や立場、形式ごとの注意点について、詳しく見てまいりました。これで、着るものについては、随分とご安心いただけたのではないでしょうか。
最後になりましたが、葬儀に参列される際は、服装そのものだけでなく、お持ちになるものや、ご自身の身だしなみ全般にも、心を配ることが大切です。こうした細やかな部分への心遣いが、故人様への「ありがとう」という感謝の気持ちや、お偲びする「あたたかい雰囲気」を作る一助となり、また、悲しみの中にいらっしゃるご遺族様への深い「配慮」を示すことにつながります。お別れの場全体が、故人様を温かく送り出せるような、穏やかな雰囲気に包まれるためにも、ぜひ意識したい点です。
ここでは、バッグや靴、コートといった持ち物に関するマナー、そしてメイクや髪型、アクセサリー、ネイルなどの身だしなみマナー、さらに季節ごとの服装調整のポイントについて、丁寧にご説明いたします。服装だけでなく、身だしなみ全てを整えることで、より心穏やかに、故人様との最後のお時間に向き合っていただけるよう、お手伝いできれば幸いです。
5-1.バッグ・靴・コートなどの持ち物マナー
葬儀における持ち物も、服装と同様に「控えめに」「派手さをなくす」が基本です。
- バッグ:
- 色は黒が基本です。紺やグレーなどの地味な色でも問題ありませんが、できれば黒を選びましょう。
- 素材は布製か、光沢のない革(合皮含む)を選びます。エナメルやビニール素材など、光沢のあるものは慶事を連想させるため避けます。
- デザインはシンプルなものが適切です。金具が多いものや装飾が派手なものは避けましょう。
- 大きさは、必要最低限のものが収まる小ぶりのものがよいとされます。ただし、荷物が多い場合は、派手ではないサブバッグを利用するのも差し支えありません。
- 毛皮やクロコダイル、ヘビ革など、動物の殺生を連想させる素材のバッグは厳禁です。
- 靴:
- 色は黒が基本です。
- 男性、女性ともに、光沢のない革靴を選びます。金具の少ない、シンプルなデザインが適しています。
- 女性の場合、ヒールは高すぎないもの(3〜5cm程度)で、太めの安定したものがよいでしょう。ピンヒールやミュール、サンダル、ブーツは不適切です。つま先が出ないデザインを選びます。
- 男性の場合、金具の少ない内羽根式のストレートチップやプレーントゥなどが一般的です。ローファーは略式と見なされることがあるため、避けるのが無難です。
- 靴下やストッキングも黒を選びます。女性は肌色のストッキングでも問題ありませんが、黒がより一般的です。網タイツや柄物は避けます。
- コート・上着:
- 冬場など、肌寒い時期にはコートやジャケットを着用します。
- 色は黒、紺、グレーなどの地味な色を選びます。
- 素材はウールやカシミヤなど、光沢のない落ち着いたものを選びます。ダウンコートなどのカジュアルなものや、ファー付きのものは避けるべきです。
- 会場に入る前に脱ぐのがマナーです。脱いだコートはたたんで腕にかけるか、クロークがあれば預けましょう。
- 車での移動が多い場合でも、会場での振る舞いを考慮し、フォーマルなものを用意するのが望ましいです。
これらの小物に関する注意点は、故人や遺族への敬意を表し、葬儀の荘厳な雰囲気を損なわないための配慮です。派手なものや華美なものは避け、控えめな印象を心がけましょう。
5-2.香水や派手な装飾品、光る素材のNG例
葬儀の場では、周囲への配慮も非常に重要です。個人の好みよりも、弔いの気持ちを共有する場にふさわしいかどうかを優先します。
- 香水:
- 強い香りの香水やコロンは控えましょう。葬儀には様々な年齢や体調の方が参列されます。強い香りは気分を悪くさせる可能性があり、周囲の迷惑となることがあります。
- つけるとしても、ごく控えめに、衣服の内側などに少量つける程度にとどめるのがマナーです。心配な場合は、つけないのが最も無難です。
- 派手な装飾品・光る素材:
- 結婚指輪以外のアクセサリーは、原則としてつけないか、ごくシンプルなものを選びます。
- 光る素材(ゴールド、プラチナ、大きな宝石など)は、お祝い事を連想させるため避けるべきです。
- パールのネックレスは、不幸が重なるという意味合いで二連のものは避け、一連のものを選びます。イヤリングやピアスも一粒パールなど、シンプルで揺れないものが適しています。
- 殺生を連想させるものとして、ファー製品や動物の牙、骨などを使用したアクセサリーは避けるべきです。
- 時計をつける場合は、華美な装飾のないシンプルなデザインのものを選びます。光沢のある金属バンドや、宝石があしらわれたものは避けます。
- お化粧も控えめに、ナチュラルメイクを心がけます。ラメやパール入りのアイシャドウ、つけまつげなどは避けます。口紅の色も肌なじみの良い控えめな色を選びましょう。
これらのマナーは、故人を悼む場において、個人の装飾が目立つことで場の雰囲気を乱さないための配慮です。華やかさや個性を主張するのではなく、故人への哀悼の意を示すことに徹します。
5-3.季節ごとの服装調整と防寒・暑さ対策
葬儀は季節を問わず行われます。マナーを守りつつ、体調を崩さないための適切な服装調整が必要です。
- 冬場の対策:
- 防寒としてコートを着用しますが、前述の通り、黒や地味な色のフォーマルなデザインのものを選びます。
- 首元の防寒には、黒や地味な色の無地のストールやマフラーを使用しても構いません。ただし、光沢のある素材や柄物は避けます。会場内では外します。
- インナーには、防寒性の高い機能性肌着などを着用しても問題ありませんが、着ぶくれしないように注意し、見える部分の色は地味なものを選びます。
- 使い捨てカイロを使用するのも有効な手段です。
- 夏場の対策:
- 夏場の葬儀は非常に暑くなることがあります。男性は上着を着用するのがマナーですが、移動中や受付を済ませた後など、状況に応じて上着を脱いでも構わない場合があります(ただし、式の最中は原則着用)。
- 女性の場合、ワンピースやアンサンブルなど、通気性の良い素材のものを選ぶと比較的快適に過ごせます。
- インナーは吸湿速乾性のある素材を選ぶと、汗による不快感を軽減できます。色は白やベージュなど、透けにくいものを選びます。
- 日傘を使用する場合は、黒や地味な色のものを選びます。ただし、会場の敷地内では傘をたたむのがマナーです。
- 扇子やうちわを使用することも考えられますが、音が立たないように静かに使用し、周囲への配慮を忘れないようにしましょう。派手な色や柄のものは避けます。
- 水分補給も大切ですが、式中に音を立てたり、席を立ったりすることがないよう、事前に済ませておきます。
季節に応じた体温調節は、自身の体調管理のためにも重要です。マナーの範囲内で、無理のない服装を心がけましょう。ただし、どのような季節であっても、肌の露出が多い服装は避けるのが基本です。
これらの服装以外のマナーを守ることは、形式にとらわれるだけでなく、故人への最後の敬意を表し、悲しみの中にいる遺族に寄り添う気持ちを示すための行為です。
⑤ まとめ
はい、承知いたしました。 記事の締めくくりとなる「⑤ まとめ」の概要について、ご要望の内容を踏まえて作成します。これまでの内容を振り返り、ハタオ葬儀社様の温かいメッセージを込めます。
⑤ まとめ
この記事では、葬儀における服装マナーについて、喪服の種類から選び方、参列する立場や葬儀の形式による違い、さらには小物や身だしなみの注意点まで、幅広く解説してまいりました。
ご覧いただいたように、葬儀の服装マナーは、単に決まりだから守るという形式的なものではありません。故人様への深い「感謝」の気持ちや、在りし日を「あたたかくお偲びする」心、そして残されたご遺族様への「お悔やみ」と「配慮」を表すための、大切な心遣いの形なのです。
もし、この記事を読まれてもなお、ご自身の服装について不安を感じていらっしゃるとしても、どうかご自分を責めすぎないでください。最も大切なのは、故人様を大切に思う気持ち、お別れを惜しむ心です。服装は、その大切な気持ちを静かに、そして丁寧に示すための一つの手段に過ぎません。
私たちハタオ葬儀社は、大切な方とのお別れの時間を、ご遺族の皆様が「感謝で送り、あたたかい雰囲気で、人のつながりを大切にする」ひとときとして、心穏やかに過ごせるよう、心を込めてお手伝いしております。服装のことだけでなく、葬儀に関するあらゆる「分からない」や「不安」に、私たちはいつも寄り添い、支えになりたいと願っております。故人様へのお気持ちが伝わるような、花いっぱいのお見送りについても、どうぞご遠慮なくお気軽にご相談ください。
この情報が、皆様の不安を少しでも和らげ、大切な方を心を込めて送るための一助となれば幸いです。
6. Q&A:葬儀の服装について、よくある疑問にお答えします
葬儀の服装マナーについて、基本的なことはご理解いただけたかと思います。ここでは、さらに多くの方から寄せられる、服装に関する具体的な疑問にお答えします。どうぞ、お見送りの準備にお役立てください。
Q1. お数珠の色や種類に決まりはありますか?
- 宗派によって正式な数珠はありますが、一般の弔問客として参列する場合、ご自身の宗派の数珠、または宗派を問わない略式数珠を使用するのが一般的です。色や素材に厳格な決まりはありませんが、派手すぎるものや動物性の素材(象牙、べっ甲など)は避けるのが無難とされています。一般的には、お数珠は左手にかけ、房を下に向けて持つのがマナーです。
Q2. 冬場のコートや防寒具はどのようなものが良いですか?
- 冬場はコートなどの防寒具を着用して構いません。色は黒、紺、グレー、ダークブラウンなど、地味なものを選びましょう。ウールやカシミヤなどの落ち着いた素材が適しています。毛皮素材(リアルファー、フェイクファー問わず)や、ダウンコートなどのカジュアルすぎるものは避けてください。会場に入る前に脱ぐのがマナーです。マフラーや手袋も地味な色を選び、屋内で外します。
Q3. 夏場の服装で、半袖の喪服やワンピースは大丈夫ですか?
- 女性の場合、半袖のブラックフォーマルワンピース自体は販売されており、着用は可能です。ただし、肩や腕の露出を控えるのがより丁寧なマナーとされていますので、できれば七分袖以上のものを選ぶか、ジャケットやカーディガンなど黒の羽織るものを一枚用意しておくと安心です。ノースリーブは避けるのが一般的です。男性は夏場でも長袖シャツにブラックスーツが基本です。
Q4. 靴下は黒であれば柄物でも大丈夫ですか?
- 基本的に、靴下は男性、女性ともに黒無地のものを選んでください。細かい織り柄など、ごく目立たないものであれば許容される場合もありますが、動物柄やドット、ストライプなど、見てすぐに柄だと分かるものは避けるのがマナーです。
Q5. バッグは必ず必要ですか?ブランド物は持っても良いですか?
- 貴重品などを入れるため、バッグは持参するのが一般的です。ただし、日常使いの大きなバッグではなく、小ぶりなハンドバッグなどが適しています。色は黒無地で、光沢のない布製や革製のものが基本です。金具が派手なもの、アニマル柄、大きなブランドロゴが入ったものなど、華美な印象を与えるものは避けてください。
Q6. 葬儀にふさわしいハンカチの色や素材はありますか?
- 葬儀で使うハンカチは、白無地が最も正式とされています。涙を拭いたりするため、清潔感のある綿や麻素材が良いでしょう。黒無地でも構いませんが、白が一般的です。刺繍やレースなどが派手に入ったものは避けてください。
Q7. アクセサリーは結婚指輪以外は一切ダメですか?
- 結婚指輪は着用したままで構いません。それ以外のアクセサリーは、原則として控えめなものを選ぶか、つけないのが無難です。一般的に許容されるのは、一連のパールのネックレスと、それに準ずるパールのイヤリング(ピアス)のみです。二連以上のネックレスや、光るダイヤ、色石、プラチナやゴールドが強く主張するデザインのものは避けましょう。
Q8. 女性の喪服でパンツスタイル(パンツスーツ)はマナー違反ですか?
- 伝統的な喪服はスカートスタイル(ワンピースやスカートスーツ)ですが、近年は女性の社会進出などもあり、パンツスーツのブラックフォーマルも販売されており、受け入れられる傾向にあります。特にご遺族や近しいご親族の間では、動きやすさなどから選ばれる方もいらっしゃいます。ただし、一般参列者としては、スカートスタイルの方がより丁寧な印象を与えるため、迷う場合はスカートを選ぶのがより無難と言えます。
Q9. 雨の場合、傘の色に決まりはありますか?
- 雨天の場合、傘をさしても構いません。色は黒、紺、グレーなどの地味なものを選びましょう。明るい色や、派手な柄のものは避けるのがマナーです。ビニール傘でも色が無色透明であれば問題ありませんが、できれば落ち着いた色のものを用意しておくと安心です。
Q10. 刺青(タトゥー)やピアスは見えないように隠すべきですか?
- はい、葬儀の場では、故人様やご遺族、他の参列者への配慮として、刺青(タトゥー)は衣類やメイクなどで隠すのがマナーです。ピアスなどのアクセサリー類も、結婚指輪や一連のパール以外は、原則として外すか、非常に小さな目立たないもの(スタッドタイプなど)に留めるのが望ましいです。弔事においては、華美な装飾品や自己主張の強いものは避けるという考え方に基づきます。
これらのQ&Aが、皆様の服装に関する疑問や不安を解消する一助となれば幸いです。
⑦ 執筆者・監修者紹介
執筆者:畑尾一心
- 役職: ハタオ葬儀社 3代目 代表取締役社長
- 経歴:
1972年、熊本で50年余年続く葬儀店に生まれる。
葬祭業に従事して30年以上。年間約400件を超える葬儀やご相談に携わり、地域密着型で信頼と実績
現在、NPO法人全国葬送支援協議会熊本中央本部代表としても活動中。
厚生労働省認定葬祭ディレクター技能審査 1級葬祭ディレクターとして専門性を持ち、日々の活動の中で葬儀業界に貢献できること目指しています。
一般社団法人 終活協議会の終活セミナー講師や、終活カウンセラー協会の終活カウンセラーとしても活動しており、地域に密着したサービスを提供しています。 - 理念:
創業者である祖父の想いを引き継ぎ、日本独自の葬送文化の意味を現代に伝え、後悔のないお葬式を大切にし、葬儀業務に取り組んでいます。
「心を込めた葬儀サービス」を提供し、皆様の大切なお見送りをサポートします。 - 趣味:
散歩が趣味で、近所だけでなく知らない街を歩くことで、地域の人々とのコミュニケーションを楽しんでいます。
監修者:畑尾義興
- 役職: ハタオ葬儀社 会長
- 経歴:
昭和30年、熊本で先代畑尾義人により創業されたハタオ葬儀社を引き継ぎ、約40年間経営を行ってきました。
創業者の思い「誰もが誇りと思えるお葬式」を基に経営を引き継ぎ、葬儀業一筋で地元の感謝の気持ちを込めて活動してきました。
自身の葬儀体験から家族の思いが伝わる葬儀を心掛け、心と費用の負担を軽減するお手伝いを大切にしています。 - 理念:
地域密着型で、皆様にとって温かく、心のこもった葬儀を提供することが、私たちの使命です。
ご遺族様の思いを最優先に、感謝の気持ちを込めた葬儀をお手伝いし、後悔のないお見送りをサポートします。 - 趣味:
趣味は釣りと囲碁で、熊本の自然や友人との時間を大切にしています。
ハタオ葬儀社は、創業から70年にわたり地域に根差したサービスを提供してきました。私たちの専門家が執筆し、監修したこの内容は、温かい心で故人をお見送りするための指針です。葬儀に関する不安を感じている方々に、しっかりとしたサポートと信頼できる情報を提供いたします。
【大切な方への想い、どう伝えられたか。お客様の「声」をご覧ください】
【葬儀の「分からない」をもっと解消しませんか?】
【ハタオ葬儀社へのお問い合わせ】
〒 862-0949 熊本市中央区国府1丁目12-15
tel:096-364-3220 fax:096-372-5685
e-mail:info@hataosougisha.com
【ご家族のペースで、納得いくまで丁寧なハタオ葬儀社の事前相談】
葬儀場の詳細を見る
公営斎場もご利用になれます

【公営斎場】熊本市斎場
住 所
〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町796
アクセス
熊本市役所から車で、約35分

【公営斎場】菊池火葬場
住 所
〒861-1315 熊本県菊池市木柑子1318
アクセス
阿蘇高原線 三里木駅からタクシー24分

【公営斎場】大津火葬場
住 所
〒869-1233 熊本県菊池郡大津町大字大津110
アクセス
豊肥本線「肥後大津駅」からタクシーで5分