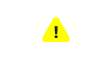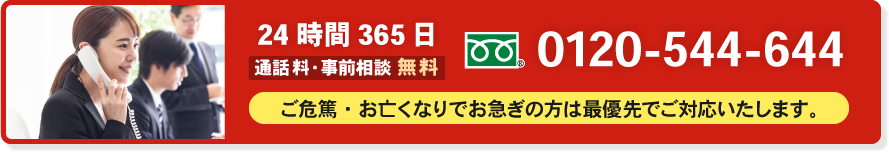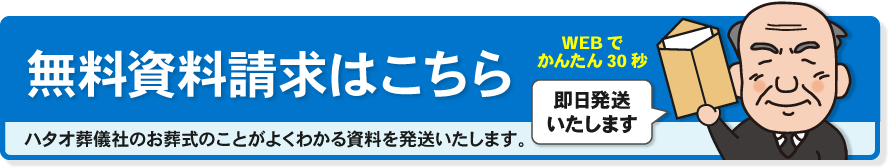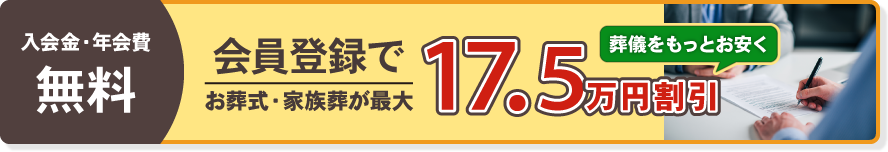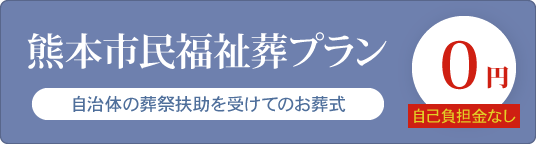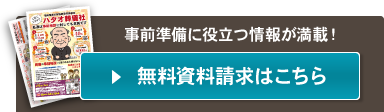新着情報
2025.09.16
【葬儀社監修】香典マナーのすべて:薄墨の書き方、金額相場、渡し方
承知いたしました。ご依頼の香典マナーに関する記事構成案を、画像を使用しない前提で、より深く、より具体的な内容で作成します。読者の理解を助けるために、画像に代わる具体的な表現方法や、表形式の提案を盛り込みます。
全体構成
① はじめに
【この記事でわかること】
- 葬儀の場で迷わない、香典の基本マナー
- 金額や中袋、筆記具に関する正しい知識
- 家族葬など、状況に合わせた香典の正しい扱い方
- なぜ「薄墨」で書くのか、その意味と背景
- ご遺族に感謝の気持ちを伝える、温かい心遣い
「香典の書き方、このままで大丈夫かな…?」そんな不安を感じていませんか?
お通夜や葬儀に参列する際、どう書くべきか悩むのが「香典」です。いざという時に困らないよう、この記事では香典の書き方から金額の相場、渡し方まで、葬儀社の監修のもと、すべてのマナーをわかりやすく解説します。香典に込められた故人への感謝とご遺族への温かいお気持ちを、形として正しく伝えるためにお役立てください。
② このような方へおすすめ
✅ 香典の書き方やマナーに自信がない方
✅ 家族葬や新しい形式の葬儀で香典をどうすべきか迷っている方
✅ 故人やご遺族に失礼のないように、正しい作法を知りたい方
✅ 葬儀の専門家から信頼できる情報を得たい方
✅ 「感謝で送り、あたたかい雰囲気」の葬儀を大切にするハタオ葬儀社の考え方に共感してくださる方
③ 目次
- 【ハタオ葬儀社監修】今さら聞けない香典の基本
- 香典の書き方:誰に、何を、どう書く?
- 金額・お札・ペン…香典の疑問を解決
- 状況別マナー:家族葬や法事での香典
- ハタオ葬儀社よりのまとめ
- 香典マナーQ&A
- 執筆者
④ 【葬儀社監修】香典マナーのすべて:薄墨の書き方、金額相場、渡し方
1. 【ハタオ葬儀社監修】今さら聞けない香典の基本
香典とは?その意味と役割
香典とは、故人様の霊前にお供えする金品のことです。これは単なるお金のやり取りではなく、深い意味が込められています。ひとつは、仏教の「線香」や「お花」を捧げる代わりという意味。もうひとつは、急な葬儀で出費を強いられるご遺族への相互扶助(助け合い)です。
この習慣は、もともと故人のもとへお米や野菜を持ち寄るという日本の古来の文化から発展しました。その後、現金のほうが使い道を選べるという実用的な考えが広まり、現代のような香典の形が定着しました。
香典袋の種類と選び方
香典袋は、宗派や包む金額によってふさわしいものを選ぶことが重要です。誤った袋を選ぶと、失礼にあたることがあるため注意が必要です。
- 水引(みずひき)の種類 水引とは、袋の中央を結んでいる飾り紐のことです。弔事で使われるのは「結び切り」や「あわじ結び」で、これらは一度結ぶと簡単にほどけないことから、「二度と不幸が繰り返さないように」という意味が込められています。
- 水引の色 水引の色は宗派によって異なります。
- 仏式:一般的には黒白の水引を選びます。包む金額が高額な場合は、より格式の高い双銀(銀と銀)の水引を選びましょう。
- 神式:水引の色は仏式と同じく黒白や双銀、または白無地の袋を選びます。
- キリスト教式:キリスト教には「香典」という習慣がないため、水引のない白無地の袋や、ユリや十字架がデザインされた袋を選びます。
- 金額に応じた袋の選び方 包む金額に見合った格の袋を選ぶことも大切です。数千円から1万円程度なら水引が印刷されたシンプルなもので十分です。3万円以上を包む場合は、和紙製の立派な袋や、本物の水引がついたものを選ぶと、より丁寧な気持ちが伝わります。
香典を渡すタイミングと、受付での作法
香典は、お通夜と告別式のどちらで渡しても構いませんが、一般的にはお通夜に持参することが多いです。ご遺族は多忙なため、受付では簡潔に済ませるのがマナーです。
- 受付に並ぶ 袱紗(ふくさ)に包んだ香典を手に、受付の列に並びます。袱紗の色は、紫、紺、グレーなど、地味な色を選びます。
- お悔やみの言葉を述べる 自分の順番になったら、「この度は心よりお悔やみ申し上げます」など、簡潔にお悔やみの言葉を述べましょう。長々と話すのは避け、ご遺族に配慮することが大切です。
- 香典を渡す 袱紗から香典袋を取り出し、袱紗の上に載せたまま、相手から見て正面になるように向きを変えて差し出します。
- 記帳 芳名帳に名前や住所を丁寧に記帳します。香典の金額は、受付で伝える必要はありません。
【ハタオ葬儀社担当者より】
香典は、故人様への最後の贈り物です。形式や作法も大切ですが、それ以上に重要なのは、故人様とご遺族への感謝と、心からの弔意です。私たちハタオ葬儀社は、お客様一人ひとりの想いを形にするお手伝いをいたします。もしご不安なことがあれば、いつでもお電話でご相談ください。
2. 香典の書き方:誰に、何を、どう書く?
香典の書き方には、いくつかのルールがあります。故人やご遺族に失礼のないよう、基本的な作法を身につけましょう。
表書き:宗派ごとの正しい言葉
香典袋の表書きは、故人の信仰していた宗派によって異なります。
- 仏式
- 「御霊前(ごれいぜん)」:仏教の多くの宗派で使われます。
- 「御仏前(ごぶつぜん)」:浄土真宗では、亡くなった方はすぐに仏になるという教えがあるため、「御霊前」ではなく「御仏前」を使用します。四十九日以降の法要でも同様です。
- 神式:**「御玉串料(おたまぐしりょう)」または「御榊料(おさかきりょう)」**と書きます。
- キリスト教式:**「お花料(おはなりょう)」**と書くのが一般的です。
もし故人の宗派がわからない場合は、どの宗派でも失礼にあたらない**「御霊前」**と書くのが一般的です。
名前と住所:中袋・外袋の書き分け
香典袋には、お金を入れる「中袋」と、それを包む「外袋」があります。
- 中袋がある場合 中袋の表に包んだ金額を、裏に自身の郵便番号、住所、氏名を記入します。中袋の書き方が丁寧であるほど、ご遺族が香典の整理をする際の負担を減らせます。
- 中袋がない場合 中袋がないタイプの香典袋では、裏面に直接、郵便番号、住所、氏名を記入します。
【ポイント】 「香典 書き方 裏」という検索は、この中袋がない場合の書き方や、中袋に書き損じたときの対処法を知りたいという意図があると考えられます。どちらの場合も、受け取ったご遺族が確認しやすいように、丁寧に記入することが大切です。
【経験談】連名・会社名・代理人の書き方
- 連名(夫婦・家族・友人) 夫婦の場合は、夫の名前を中央に、その左に妻の名前をフルネームで記入します。連名が3名までの場合は全員の名前を、4名以上の場合は代表者名を中心に書き、その左に「他一同」または「友人一同」などと記載します。
- 会社名 会社の同僚や部署でまとめて香典を出す場合は、個人の氏名の上に会社名や部署名を小さく書きます。
- 代理人 代理で香典を持参する場合は、香典袋の表には本来渡すはずだった人の名前を書き、その左下に「代」と小さく添えます。また、受付では自身の名前を伝え、「〇〇の代理で参りました」と一言添えましょう。
【ハタオ葬儀社担当者より】
香典に記入するお名前は、故人様とのご縁を繋ぐ大切な印です。会社やご友人で連名にする場合は、代表者のお名前を中央に書き、左に全員のお名前を記すのが通例です。ご心配な場合は、お電話でもご相談いただけます。
3. 金額・お札・ペン…香典の疑問を解決
香典に関する疑問は、書き方だけではありません。金額や使用するペン、お札の入れ方など、細かい点までしっかり確認しましょう。
香典にふさわしい金額相場と書き方
故人との関係性や年齢によって、香典の金額相場は異なります。相場はあくまで目安ですが、故人様やご遺族への配慮として知っておくと安心です。
- 故人との関係別相場(目安)
- 親:5万円〜10万円
- 兄弟姉妹:3万円〜5万円
- 祖父母:1万円〜3万円
- 友人・知人:5千円〜1万円
- 職場関係:5千円〜1万円
- 金額の書き方 香典袋の中袋に金額を書く際は、数字の改ざんを防ぐため、旧字体である**大字(だいじ)**を使用するのがマナーです。例えば、「一」は「壱」、「二」は「弐」、「三」は「参」、「五」は「伍」、「十」は「拾」といった文字を使います。一万円を包む場合は「金壱萬圓」、三千円の場合は「金参仟圓」または「金参千圓」と記入します。
お札の向きと、薄墨で書く理由
- お札の向き 中袋にお札を入れる際は、お札の人物像が裏側になるように、また、下を向くように入れます。これは、悲しみに暮れ、顔を伏せている姿を表現しているといわれます。
- 薄墨を使う理由 香典袋に名前を書く際、弔事では薄墨を使用します。これは「涙で墨が薄まってしまった」「急な訃報で墨を磨る時間がなかった」という悲しみを表すためです。近年は便利な筆ペンもありますので、一本用意しておくと安心です。
【専門知識】中袋なしの香典、どうする?
地域によっては、中袋を使わずに外袋へ直接お金を入れる風習があります。特に北海道や東北地方の一部では、この形式が一般的です。中袋がない場合は、香典袋の裏面に、郵便番号、住所、氏名、そして包んだ金額を縦書きで丁寧に記入しましょう。
【ハタオ葬儀社担当者より】
金額の書き方は、数字を間違えずに丁寧にお書きください。香典の準備は故人様への最後の身だしなみです。ハタオ葬儀社では、お電話一本で、お通夜や葬儀に関するあらゆるご相談を承っています。
4. 状況別マナー:家族葬や法事での香典
現代の葬儀は多様化しています。それぞれの形式に合わせた香典マナーを知っておくことで、よりスマートに対応できます。
家族葬の場合:香典は渡すべき?
家族葬は、近親者のみで行われる葬儀形式です。近年増えているこの形式では、ご遺族が香典を辞退されるケースがほとんどです。
- なぜ辞退されるのか?
- ご遺族が香典を辞退される一番の理由は、参列者への負担を減らし、香典返しの手間をなくしたいという考えからです。
- もし辞退されたら?
- ご遺族の意向を尊重し、無理に渡すのは避けましょう。どうしてもお気持ちを伝えたい場合は、葬儀後に改めて弔問し、御供物や御供花を贈るなど、別の形で心遣いを示すのが適切です。
法事(四十九日・一周忌など)での香典
四十九日や一周忌などの法事では、香典の表書きが変わります。
- 表書き:
- 四十九日以降の法事では、「御霊前」ではなく**「御仏前(ごぶつぜん)」**を使用します。これは、仏教の教えでは故人が仏様となる日とされているためです。
- 金額の目安:
- 法事の香典は、故人との関係性や、会食の有無によって異なります。会食がある場合は、その費用を考慮して多めに包むのが一般的です。
【独自性】花いっぱいのお葬式と香典の関係
「感謝で送り、あたたかい雰囲気」を大切にするハタオ葬儀社では、故人様が愛した花で祭壇を飾る「花いっぱいのお葬式」を提案しています。ご遺族が香典の代わりに御供花や供物を希望される場合もありますので、その際はご遺族の意向を確認しましょう。
【ハタオ葬儀社担当者より】
時代とともに葬儀の形は変わります。私たちは、故人様との温かいお別れを最優先に考え、形式にとらわれない柔軟なご提案をしています。ご不明な点があれば、いつでもお問い合わせください。
⑤ ハタオ葬儀社よりのまとめ
香典は、故人様への感謝と、大切な方を亡くされたご遺族への、温かいお気持ちを伝える大切な手段です。書き方のルールやマナーは、故人様を敬い、ご遺族を思いやる心遣いの表れに他なりません。この記事が、皆様のふとした不安を少しでも和らげ、心穏やかに故人様との最後の時間を過ごす一助となれば幸いです。
私たちハタオ葬儀社は、「感謝で送り、あたたかい雰囲気」をモットーに、形式にとらわれすぎない、お客様一人ひとりの想いを大切にした葬儀をご提供しています。もし、香典のことだけでなく、ご不安なことやお悩みがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。葬儀の専門家として、いつでも皆様のお気持ちに寄り添い、丁寧にご案内いたします。
⑥ Q&A
Q1:香典袋は、どこで手に入りますか?
A1:コンビニやスーパー、100円ショップなどで購入できます。
Q2:香典の金額を奇数にするのはなぜですか?
A2:偶数は割り切れるため、「縁が切れる」と連想され、縁起が悪いとされるからです。
Q3:中袋に住所を書きたくないのですが…?
A3:ご遺族が香典返しをする際に必要となりますので、正確な住所を記入しましょう。
Q4:香典に新札を入れても良いですか?
A4:新札は「事前に準備していた」ととられるため、避けるのがマナーです。一度折り目をつけてから包みましょう。
Q5:会社の同僚と連名で出す場合、全員の名前を書くべきですか?
A5:人数が少ない場合は全員の名前を書きますが、多い場合は「〇〇部一同」などと記載し、別紙に全員の名前を記します。
Q6:家族葬で香典を辞退された場合、後日渡しても良いですか?
A6:ご遺族の意向を尊重し、基本的には渡さないのがマナーです。どうしてもお気持ちを伝えたい場合は、日を改めて弔問し、御供物などをお渡しする方法もあります。
⑦ 執筆者
⑦ 執筆者
執筆者:畑尾一心
役職: ハタオ葬儀社 3代目 代表取締役社長
経歴:
1972年、熊本で50年余年続く葬儀店に生まれる。
葬祭業に従事して30年以上。年間約400件を超える葬儀やご相談に携わり、地域密着型で信頼と実績
現在、NPO法人全国葬送支援協議会熊本中央本部代表としても活動中。
厚生労働省認定葬祭ディレクター技能審査 1級葬祭ディレクターとして専門性を持ち、日々の活動の中で葬儀業界に貢献できること目指しています。
一般社団法人 終活協議会の終活セミナー講師や、終活カウンセラー協会の終活カウンセラーとしても活動しており、地域に密着したサービスを提供しています。
想い:
創業者である祖父の想いを引き継ぎ、日本独自の葬送文化の意味を現代に伝え、後悔のないお葬式を大切にし、葬儀業務に取り組んでいます。
「心を込めた葬儀サービス」を提供し、皆様の大切なお見送りをサポートします。
趣味:
散歩が趣味で、近所だけでなく知らない街を歩くことで、地域の人々とのコミュニケーションを楽しんでいます。
監修者:畑尾義興
役職: ハタオ葬儀社 会長
経歴:
昭和30年、熊本で先代畑尾義人により創業されたハタオ葬儀社を引き継ぎ、約40年間経営を行ってきました。
創業者の思い「誰もが誇りと思えるお葬式」を基に経営を引き継ぎ、葬儀業一筋で地元の感謝の気持ちを込めて活動してきました。
自身の葬儀体験から家族の思いが伝わる葬儀を心掛け、心と費用の負担を軽減するお手伝いを大切にしています。
理念:
地域密着型で、皆様にとって温かく、心のこもった葬儀を提供することが、私たちの使命です。
ご遺族様の思いを最優先に、感謝の気持ちを込めた葬儀をお手伝いし、後悔のないお見送りをサポートします。
趣味:
趣味は釣りと囲碁で、熊本の自然や友人との時間を大切にしています。
ハタオ葬儀社は、創業から70年にわたり地域に根差したサービスを提供してきました。私たちの専門家が執筆し、監修したこの内容は、温かい心で故人をお見送りするための指針です。葬儀に関する不安を感じている方々に、しっかりとしたサポートと信頼できる情報を提供いたします。
大切な方への想い、どう伝えられたか。お客様の「声」をご覧ください
【大切な方への想い、どう伝えられたか。お客様の「声」をご覧ください】
【葬儀の「分からない」をもっと解消しませんか?】
【ハタオ葬儀社へのお問い合わせ】
【ご家族のペースで、納得いくまで丁寧なハタオ葬儀社の事前相談】
葬儀場の詳細を見る
公営斎場もご利用になれます

【公営斎場】熊本市斎場
住 所
〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町796
アクセス
熊本市役所から車で、約35分

【公営斎場】菊池火葬場
住 所
〒861-1315 熊本県菊池市木柑子1318
アクセス
阿蘇高原線 三里木駅からタクシー24分

【公営斎場】大津火葬場
住 所
〒869-1233 熊本県菊池郡大津町大字大津110
アクセス
豊肥本線「肥後大津駅」からタクシーで5分