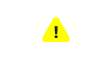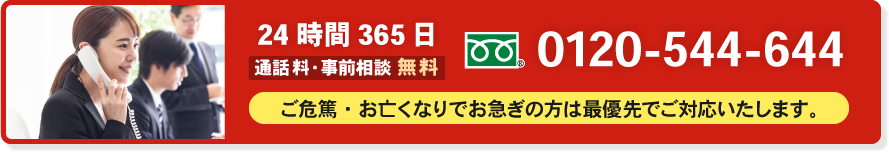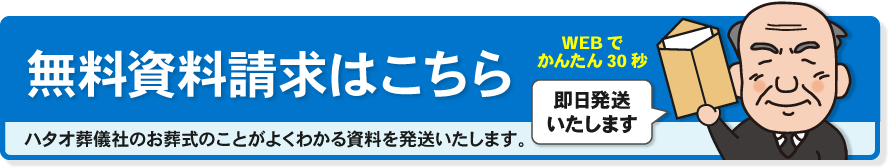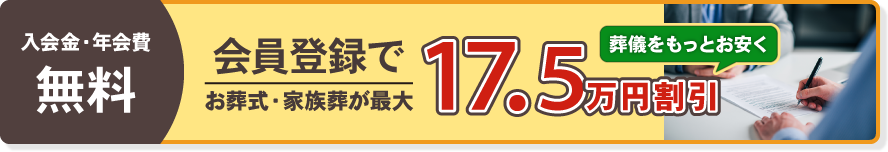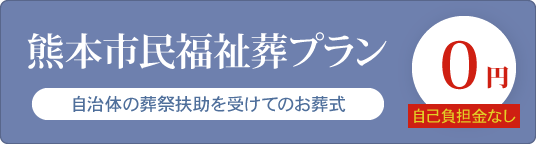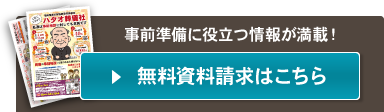新着情報
2025.09.29
【葬儀後の神棚】熊本での神棚封じの期間は?やり方と注意点を解説
①はじめに
葬儀後の神棚封じ、故人様への想いを込めて
- 神棚封じを行う時期はいつ?
- 神棚封じはなぜ必要?
- 実際の神棚封じのやり方を詳しく解説
- もし間に合わなかったらどうする?
- 神棚封じに関するよくある疑問を解消
「お葬式はやり直しがきかないから、絶対に失敗したくない」というお気持ち、とてもよくわかります。特に、初めてのことで何から手をつけて良いのか分からず、情報過多な状況に戸惑っている方も少なくありません。
私たちハタオ葬儀社は、この熊本の地で、ご家族の想いを何よりも大切に、あたたかいお別れの時間をご提供したいと考えています。だからこそ、慌ただしい中で一つずつ決めるのではなく、ご希望やご不安をじっくりお聞かせいただける事前相談をおすすめしています。
今回、神棚封じについてもお話ししましたが、葬儀後の手続きは他にもたくさんあります。不安なこと、分からないことがあれば、どんな小さなことでも構いません。私たちハタオ葬儀社は、皆さまが安心して大切な方とのお別れに臨めるよう、心を込めてお手伝いさせていただきます。
花いっぱいのあたたかいお葬式で、故人様とのお別れを、心に残る大切な思い出にしませんか。
②このような方へおすすめ
- ✅ 葬儀後の神棚の扱いに困っている方。
- ✅ 神棚封じの正しいやり方を知りたい方。
- ✅ 熊本での神棚封じの風習や期間について知りたい方。
- ✅ 葬儀後に行うべき手続きや流れを把握したい方。
- ✅ 専門家の視点から、分かりやすい情報を探している方。
③目次
- はじめに
- 神棚封じを行う時期はいつ?熊本での忌中・喪中の期間
- なぜ神棚封じを行うのか?その意味と理由
- 神棚封じの正しいやり方と手順
- 神棚封じ、もし間に合わなかった場合は?
- 神棚封じに関するよくある疑問とQ&A
- ハタオ葬儀社よりのまとめ
- 執筆者
葬儀を終えられ、ほっと一息ついた時、「そういえば神棚は…」と不安を感じていませんか?
① 【神棚封じの時期】熊本での忌中・喪中の期間と風習
①-1 神棚封じを行うタイミングはいつ?
神棚封じは、故人様がご逝去された直後に行うのが一般的です。これは、神道において「死」を特別なけがれとして捉える考え方に基づいています。ご家族が悲しみに包まれる中で、まず神棚に白い半紙を掛け、神様への敬意と配慮を示すのです。
この「忌中(きちゅう)」と呼ばれる期間は、神様の領域にけがれが及ばないようにと古くから守られてきた習わしです。ただし熊本では、中央区・東区・西区・南区、そして合志市や菊陽町など地域ごとに少しずつ風習の違いがあります。ご家庭ごとの慣習に合わせて確認しておくと、安心して進められるでしょう。
①-2 神道と仏教における忌中・喪中の期間について
「忌中」と「喪中」は似ている言葉ですが、意味合いには違いがあります。
- 忌中 … 故人様を偲びつつ、けがれを慎む期間。
仏教では四十九日法要まで、神道では五十日祭までとされるのが一般的です。 - 喪中 … 深い悲しみを胸に、日常生活でも慎みをもって過ごす期間。
多くの場合は一年間を指します。
熊本での葬儀や家族葬においても、この「忌中」と「喪中」の違いを踏まえて神棚封じや法要の流れを整えていくことが大切です。
①-3 忌中の間にやるべき神棚封じのポイントとアドバイス
忌中の間は、神棚の扉を開けたり、新たにお供えをしたりすることを控えるのが古くからの習わしです。白い半紙を静かに掛ける「神棚封じ」という所作には、神様への敬意とともに、残された家族が心にけじめをつけるという大切な意味が込められています。
また、故人様のご命日から七日ごとに法要を営むご家庭も多く見られます。熊本では、葬儀後の四十九日までは「忌中」として静かに日々を過ごすことが一般的であるため、この期間を迎える前に、早めに神棚封じを整えておくと心の準備も進み、安心して次の節目を迎えることができるでしょう。
ハタオ葬儀社からのご案内
熊本市での葬儀や家族葬では、突然の慌ただしさの中で神棚封じをつい後回しにしてしまうご家族も少なくありません。けれども、神棚封じはご遺族の心を整える大切な習わしのひとつです。
もしご不安がありましたら、ご逝去直後からどうぞ遠慮なく私たちにご相談ください。地域の風習を大切にしながら、正しい時期や方法をご案内し、ご家族が安心して大切な儀式を進められるよう、専門のスタッフが心を込めてお手伝いいたします。
② なぜ神棚封じを行うのか?その意味と理由を理解する
②-1 神道における「死の穢れ」の考え方
神道では、「死」は特別な“穢れ”として受け止められています。神様は清らかで尊い存在であるため、その世界に死のけがれが及ばないように、家の神棚を白い紙で封じるのです。これは単なる形式ではなく、亡き人を迎えた家に一時的に宿るとされるけがれを神様に近づけないための、静かで深い祈りの表れでもあります。
熊本における直葬や一日葬においても、この考え方は大切に守られてきました。葬儀の規模が小さくても大きくても、神様を敬い、故人様を想う心に違いはなく、その祈りが家族の心を支える習わしとして受け継がれているのです。
一方、仏教では「死」を穢れとしてではなく、命が次の世界へと移り変わる過程として捉えます。四十九日までを「忌中」とし、その間は故人様の魂が成仏の道を歩むと考えられています。そのため、神道が「神棚を封じて死のけがれを遠ざける」のに対し、仏式では「法要を重ねて故人様の冥福を祈る」ことを重視します。
このように、神道と仏教では死に対する考え方に違いがありますが、共通しているのは「亡き人を敬い、心を込めて見送る」という姿勢です。熊本ではどちらの宗教でも、古くからの習わしを大切にしながら、ご家族が安心して故人様を送り出せるような風習が息づいています。
②-2 神様への配慮と故人様への敬意
神棚封じは、神様に対する敬意と配慮のしるしであると同時に、残されたご家族が故人様を静かに偲ぶための時間をつくる大切な行為でもあります。一見すると形式的な作業のように思えるかもしれませんが、その背景には「神様に失礼をしないように」という敬虔な心と、「今は故人様に心を寄せたい」という深い思いが重なっています。
たとえ仏式のお葬儀であっても、神棚封じを行うことで、ご家族は余計な心配事にとらわれることなく、弔いに心を集中させることができます。こうした所作が、ご遺族にとっての区切りとなり、悲しみの中でも少しずつ心を整えていく支えとなるのです。
熊本でも、仏式の家族葬を選ばれたご家庭が、葬儀後すぐに自宅で神棚封じをなさるケースは少なくありません。白い半紙をそっと掛けるだけの簡素な所作ですが、その瞬間、ご家族は「これで正しく整えることができた」という安心を得られます。地域の慣習に沿ったこうした行いは、形式を超えて、ご遺族の心を静かに支える大切な習わしとして今も受け継がれているのです。
②-3 神棚封じを行わないとどうなる?注意点とアドバイス
神棚封じをしなかったからといって、何か具体的な不利益が直ちに生じるわけではありません。けれども、古くから受け継がれてきた信仰や、神様への敬意、そして故人様を大切に想う気持ちを考えると、できるだけ行っておくことが望ましい習わしです。
白い半紙をそっと掛けるだけの小さな所作ですが、その一手間によって「正しく整え、きちんとお見送りができた」という安心感がご家族の心に生まれます。神棚封じは形式的な儀式ではなく、ご遺族の心を静かに支え、悲しみの中に落ち着きを与えてくれる大切な習慣なのです。
熊本でも、葬儀後の慌ただしさの中で神棚封じを忘れてしまい、後から気づいて慌ててご相談に来られるご家族も少なくありません。その場合でも、気づいた時点で心を込めて整えれば十分です。地域の慣習に沿ってきちんと対応することで、ご遺族は「これで安心だ」と心を落ち着けることができるのです。
ハタオ葬儀社担当者より
熊本での家族葬や葬儀後には、役所での手続きや法要の準備など、思いのほか多くのことが次々と待っています。その慌ただしさの中で、神棚封じはつい後回しになってしまうことも少なくありません。
けれども、神棚封じを早めに整えておくことで、ご家族の心の負担は軽くなり、安心して次の節目を迎えることができます。小さな所作ではありますが、その一つひとつが「大切な方を正しく、そしてあたたかく見送る」ことにつながります。
どうか焦らず、一歩ずつ準備を進めてみてください。私たちハタオ葬儀社は、地域の風習を踏まえながら、ご家族の想いに寄り添い、安心して儀式を整えていただけるよう心を込めてお手伝いいたします。
③ 神棚封じの正しいやり方と手順を解説
③-1 必要な準備物と神棚封じの手順
神棚封じに必要なものは、白い半紙と、それを留めるためのセロテープなど、身近にある簡単な道具だけです。もし半紙が手元になければ、白い奉書紙やコピー用紙でも代用できます。大切なのは、模様や文字のない「真っ白で無地の紙」を用いること。その白さには、清らかさと静けさを表し、神様への敬意とご家族の祈りの心が込められるのです。
手順はとてもシンプルです。
- まず神棚の扉を静かに閉めます。
- その正面を覆うように、白い半紙を貼ります。
- 神棚にお供えしていたものはすべて下げ、しばらくお休みいただきます。
白い紙を掛ける所作は、神様に「しばしの間お守りください」という祈りを込めると同時に、ご家族が心を整えるための大切な時間となります。
③-2 神棚封じを誰がやるべきか?
神棚封じは、一般的には故人様のご家族が手を合わせるようにして行います。ご親族が集まっている場合には、相談のうえでどなたかが代表して行っても差し支えありません。大切なのは「誰がするか」ではなく、「故人様を想い、ご家族が心を込めて取り組むこと」です。その静かな所作こそが、神様への敬意となり、ご遺族の心を落ち着かせるひとつの区切りとなります。
③-3 神棚封じを行う際の注意点とアドバイス
白い半紙を貼るときは、神棚の正面全体をやさしく覆うようにしてください。半紙には何も記さず、必ず無地のまま用います。封じを終えた後は、新しいお供えをしたり、扉を開けたりすることは控え、忌明けの時期を迎えるまで静かにそのままにしておくのが習わしです。
熊本では、葬儀社がご家族に寄り添いながら、神棚封じの手順や意味を丁寧にお伝えすることも多くあります。不安や迷いがあるときは、どうぞ一人で抱え込まずにご相談ください。専門家と一緒に進めることで、安心して大切な儀式を整えることができます。
ハタオ葬儀社担当者より
熊本市で家族葬や葬儀を終え、ご自宅に戻られたとき、多くのご家庭ではまず神棚封じを整えます。けれども、突然の慌ただしさの中で「これでよいのだろうか」と迷われることも少なくありません。
そのようなときは、どうぞ事前相談の際に遠慮なくお尋ねください。地域の風習を踏まえながら、一つひとつの手順や意味を丁寧にご説明いたします。ご家族が安心して大切な儀式を整え、心静かに故人様をお見送りできるように、私たちは心を込めてお手伝いいたします。
④ 葬儀後、神棚はいつまで封じるべきか?期間の目安
④-1 神棚封じを解くタイミングはいつ?
神棚封じを解くのは、忌明け(きあけ) にあたる時期です。
仏式では四十九日法要を終えた後、神道では五十日祭を終えた後に行うのが一般的とされています。法要や祭儀が滞りなく済んだことを、神様やご先祖様に静かにご報告し、その節目に合わせて神棚の封じを解くのです。
この所作は、単に紙を外すという行為にとどまらず、ご家族にとって「一区切りを迎える」大切な意味を持ちます。悲しみの中にも、少しずつ日常を取り戻すための歩みを進める、そのきっかけとなる瞬間なのです。
④-2 封じを解く際の注意点と手順
封じを解くときは、まず白い半紙を静かに、丁寧にはがしてください。続いて神棚を清め、新しいお供え物を整えたうえで扉を開けます。
この所作は、神様に「無事に忌明けを迎え、日常を取り戻しました」と感謝をお伝えする祈りであると同時に、ご家族にとっても「これからまた歩んでいこう」という心の準備となります。小さな所作のひとつですが、その一つひとつが悲しみの中で前を向くための大切な節目となるのです。
④-3 神棚封じの期間を過ぎてしまったら?アドバイス
もし四十九日や五十日を過ぎてしまっても、決して慌てる必要はありません。
神棚封じは「期日をきっちり守らなければならない決まり事」ではなく、ご家族が故人様を想い、心を込めて整えることに大きな意味があります。熊本では、仏式であれば四十九日法要、神道であれば五十日祭を一区切りとするのが一般的です。
けれども、もしその時期を過ぎてしまっても、気づいたときに丁寧に封じを解き、神棚を清め、新しいお供えを整えれば十分です。大切なのは日付そのものではなく、そこに込められた祈りの心です。小さな所作であっても、故人様への感謝やご家族の思いを伝える行為は、残された人の心を静かに支え、前へ進む力を与えてくれます。
ハタオ葬儀社担当者より
熊本での家族葬や直葬の後は、役所への手続きや法要の準備など、多くのことに追われてしまい、神棚封じをつい忘れてしまう方も少なくありません。けれども、どうぞご安心ください。神棚封じは、慌てて行うよりも、心を込めて整えることが何よりも大切です。
私たちは、地域の風習を大切にしながら、正しい方法や時期について丁寧にご案内いたします。ご不安なことや分からないことがあれば、どうぞいつでもお気軽にご相談ください。ご家族が安心して大切な儀式を整え、故人様を心静かにお見送りできるように――私たちハタオ葬儀社が心を込めてお手伝いいたします。
⑤ 記事内に豆知識や用語解説
用語解説
忌中(きちゅう)
故人様の死を悼み、けがれを避けて静かに身を慎んで過ごす期間のことをいいます。仏式では四十九日法要まで、神道では五十日祭までとされるのが一般的です。この間は祝い事を控え、故人様を偲びながら日々を送ります。忌中は、ご家族にとって故人様との別れを受け入れる大切な時間でもあり、心を整えるための静かな節目ともいえます。
喪中(もちゅう)
故人様を偲びながら過ごす期間であり、この間は結婚式や新年のお祝いごとなど、喜び事を控えるのが一般的です。多くの場合、一年間を目安として設けられます。喪中は、悲しみを抱えながらも故人様を大切に思い続ける時間であり、残されたご家族にとっては「心を静め、日常へと少しずつ歩みを戻す」ための大切な期間でもあります。
四十九日(しじゅうくにち)
仏教の教えでは、故人様の魂が四十九日をもってこの世を離れ、次の世界へと旅立つとされています。そのため、この日は「忌明け」と呼ばれ、ご遺族にとっても深い悲しみの中で一区切りを迎える大切な法要の日となります。四十九日は、故人様を偲び、感謝の思いを伝えると同時に、ご家族が少しずつ日常を取り戻すための心の節目ともいえるでしょう。
⑤ ハタオ葬儀社よりのまとめ
神棚封じは、故人様をあたたかくお見送りするための大切な行いです。慌ただしい中で、つい後回しにしてしまいがちですが、この記事が皆さまの不安を少しでも解消し、故人様と向き合う時間を持つきっかけになれば幸いです。
私たちハタオ葬儀社は、熊本市、中央区、東区、南区、西区を中心に、心あたたまる家族葬や葬儀のお手伝いをしております。葬儀後の手続きや供養のこと、何でもお気軽にご相談ください。事前相談も承っております。お花いっぱいのお葬式で、大切な方との最期の時間を心に残るものにしませんか?
⑥ Q&A
- Q: 神棚封じは必ずやらないといけないものですか?
A: 宗教的な風習ですので、必ずではありませんが、神様への配慮や故人様への敬意という点で、行うことをおすすめします。
- Q: 神棚封じをした半紙は、いつまで貼っておくのですか?
A: 四十九日法要(忌明け)が終わるまで貼っておくのが一般的です。
- Q: 神棚封じは、故人様が亡くなってから何日以内にやるべきですか?
A: ご逝去された後、できるだけ早く行うのが良いとされています。
- Q: 仏教徒ですが、神棚封じは必要ですか?
A: 仏教の宗派によっては神棚封じをしないこともありますが、神道由来の風習として行う家庭も多くあります。
- Q: 神棚封じは誰がやるべきですか?
A: 特に決まりはありませんが、故人様のご家族が行うことが多いです。
- Q: 葬儀後に神棚封じを忘れてしまった場合はどうすればいいですか?
A: 気づいた時点で心を込めて行えば問題ありません。
⑦ 執筆者・監修者紹介
執筆者:畑尾一心
役職: ハタオ葬儀社 3代目 代表取締役社長
経歴:
1972年、熊本で50年余年続く葬儀店に生まれる。
葬祭業に従事して30年以上。年間約400件を超える葬儀やご相談に携わり、地域密着型で信頼と実績
現在、NPO法人全国葬送支援協議会熊本中央本部代表としても活動中。
厚生労働省認定葬祭ディレクター技能審査 1級葬祭ディレクターとして専門性を持ち、日々の活動の中で葬儀業界に貢献できること目指しています。
一般社団法人 終活協議会の終活セミナー講師や、終活カウンセラー協会の終活カウンセラーとしても活動しており、地域に密着したサービスを提供しています。
想い:
創業者である祖父の想いを引き継ぎ、日本独自の葬送文化の意味を現代に伝え、後悔のないお葬式を大切にし、葬儀業務に取り組んでいます。
「心を込めた葬儀サービス」を提供し、皆様の大切なお見送りをサポートします。
趣味:
散歩が趣味で、近所だけでなく知らない街を歩くことで、地域の人々とのコミュニケーションを楽しんでいます。
監修者:畑尾義興
役職: ハタオ葬儀社 会長
経歴:
昭和30年、熊本で先代畑尾義人により創業されたハタオ葬儀社を引き継ぎ、約40年間経営を行ってきました。
創業者の思い「誰もが誇りと思えるお葬式」を基に経営を引き継ぎ、葬儀業一筋で地元の感謝の気持ちを込めて活動してきました。
自身の葬儀体験から家族の思いが伝わる葬儀を心掛け、心と費用の負担を軽減するお手伝いを大切にしています。
理念:
地域密着型で、皆様にとって温かく、心のこもった葬儀を提供することが、私たちの使命です。
ご遺族様の思いを最優先に、感謝の気持ちを込めた葬儀をお手伝いし、後悔のないお見送りをサポートします。
趣味:
趣味は釣りと囲碁で、熊本の自然や友人との時間を大切にしています。
ハタオ葬儀社は、創業から70年にわたり地域に根差したサービスを提供してきました。私たちの専門家が執筆し、監修したこの内容は、温かい心で故人をお見送りするための指針です。葬儀に関する不安を感じている方々に、しっかりとしたサポートと信頼できる情報を提供いたします。
大切な方への想い、どう伝えられたか。お客様の「声」をご覧ください
【大切な方への想い、どう伝えられたか。お客様の「声」をご覧ください】
【葬儀の「分からない」をもっと解消しませんか?】
【ハタオ葬儀社へのお問い合わせ】
【ご家族のペースで、納得いくまで丁寧なハタオ葬儀社の事前相談】
葬儀場の詳細を見る
公営斎場もご利用になれます

【公営斎場】熊本市斎場
住 所
〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町796
アクセス
熊本市役所から車で、約35分

【公営斎場】菊池火葬場
住 所
〒861-1315 熊本県菊池市木柑子1318
アクセス
阿蘇高原線 三里木駅からタクシー24分

【公営斎場】大津火葬場
住 所
〒869-1233 熊本県菊池郡大津町大字大津110
アクセス
豊肥本線「肥後大津駅」からタクシーで5分