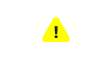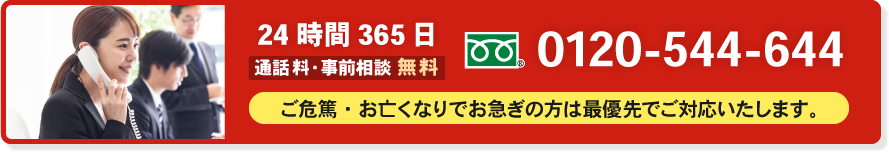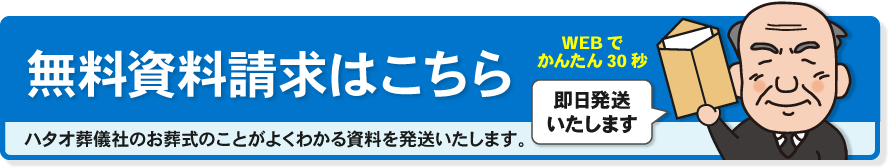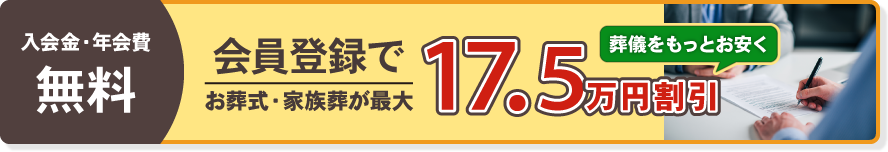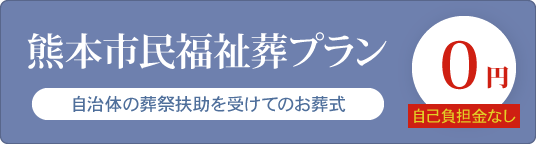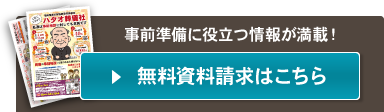新着情報
2025.10.06
故人を北枕で安置する本当の意味とは?仏教由来の理由を熊本の葬儀社が解説
① はじめに
ご遺体を安置する際、頭を北向きにする「北枕」は、誰もが一度は耳にしたことがある言葉ではないでしょうか。しかし、なぜ北向きにするのか、その本当の意味を知る方は少ないかもしれません。
- 北枕の由来は仏教にある
- 縁起が悪いとされるのはなぜか
- 現代の葬儀事情と北枕の関係
- 北枕が難しい場合の対処法
- 故人様への想いを込めた安置の重要性
このコラムでは、北枕の歴史的背景から現代の葬儀における意味、そして実際の安置で困った際の対処法まで、専門家の視点から分かりやすく解説します。
「故人を北枕で安置する」と聞いた時、あなたはどのような疑問や不安を感じますか?「本当にそうしなければいけないの?」「マンションの構造上、北枕が難しい場合はどうすればいいの?」など、様々な思いが頭をよぎるかもしれません。このコラムを通じて、あなたの不安を解消し、故人様を心穏やかに見送るためのヒントをお伝えできれば幸いです。
② このような方へおすすめ
✅ 故人を北枕で安置する意味が分からず困っている。
✅ 北枕は縁起が悪いという話を聞いて、不安になっている。
✅ 家族の看取りが近づき、安置の正しい方法を知りたい。
✅ 昔ながらの風習と現代の葬儀について、何が正しいか分からない。
✅ 熊本で葬儀を検討しており、安置の相談ができる情報がほしい。
③ 目次
- 北枕が意味する仏教の教えと、その歴史的背景
- 現代の葬儀事情と北枕にまつわる誤解を解く
- 北枕で安置できない場合でも安心できる方法
- 故人様への想いを込めた安置の重要性
- 熊本での葬儀、北枕に関するご相談は専門家へ
④ 記事本文
① 北枕が意味する仏教の教えと、その歴史的背景
仏教において故人様を北枕で安置することは、単なる風習ではなく、深い信仰と祈りの心が込められています。特に日本の葬儀においては、北枕は「縁起が悪い」と誤解されることもありますが、その根底には尊い仏教の教えが流れているのです。ここでは、その由来と歴史を紐解き、北枕の本当の意味を改めて理解していきましょう。
①-1 お釈迦様が入滅された時の姿が由来
北枕の最も有名な由来は、仏教の開祖であるお釈迦様(ゴータマ・シッダールタ)が亡くなられた時の姿にあります。お釈迦様は沙羅双樹の木の下で、頭を北に、顔を西に向けて横たわり、安らかに入滅されたと伝えられています。この姿は「頭北面西(ずほくめんさい)」と呼ばれ、弟子たちに看取られながら最期の教えを説かれた場面として、仏教徒にとって非常に大切な出来事です。
この姿を模倣することは、故人様が安らかに極楽浄土へと旅立てるようにとの願いを込める行為であり、日本の葬儀文化に深く根づきました。北枕は「死の象徴」とされがちですが、本来は「安らぎと成仏への祈り」を象徴しているのです。
【ハタオ葬儀社より】
熊本市で家族葬をされる際も、ご自宅や斎場での安置時には、まず故人様のお身体を清め、穏やかな表情に整えて差し上げます。その後、できる限り北枕に安置することで、ご遺族は「お釈迦様と同じ姿で見送れた」という安心感を抱かれることが多いです。もし間取りや状況により北枕が難しい場合でも、心を込めて安置することが何より大切です。北枕という形を通じて、ご家族の祈りが故人様へと届くように、私たち専門家が丁寧にお手伝いしています。
①-2 北は聖なる方角、南は俗世の方角
仏教の世界観において、方角には象徴的な意味が与えられています。その中でも「北」は特別な意味を持ち、「永遠不変」「悟り」「安らぎ」といった聖なるイメージと結びつけられてきました。これに対し「南」は、人々が日常を営む場所や煩悩にまみれた俗世を象徴する方角として捉えられてきました。つまり、北は精神性や清浄さを、南は生活や欲望を象徴する対比として理解されてきたのです。
このような考え方から、故人様を北枕で安置することには大切な意味が込められています。頭を北に向けることによって、亡き人が俗世の煩わしさから解き放たれ、心穏やかに仏の世界へと旅立てると信じられてきました。単なる作法や慣習ではなく、ご遺族が故人様に「どうか安らかに」「どうか迷わずに」という祈りを込める営みなのです。北枕には、亡き人を敬い、成仏を願う深い想いが映し出されています。
この思想は、古代インドから仏教が広まる中で日本にも受け継がれました。時代を経て各地域で解釈の幅は広がりましたが、根底にあるのは「故人様を仏の世界へ導きたい」という変わらぬ祈りです。現代でも、葬儀や家族葬の場で北枕が大切にされているのは、この精神性が日本人の死生観に深く根ざしているからにほかなりません。
【ハタオ葬儀社より】
熊本での葬儀や家族葬では、まず故人様を安らかに休めていただくために、お部屋を整えることから安置が始まります。その際、できる限り北の方角に頭を向けて安置することで、故人様が心穏やかに旅立つ準備が整うように、私たちは心を込めてお手伝いさせていただいております。地域の慣習とご家族の想いに寄り添いながら、安心して見送れるよう支えることが、葬儀社としての大切な務めだと考えています。
①-3 故人様を生き返らせないための風習ではない
北枕という言葉を耳にすると、多くの方が「縁起が悪い」というイメージを抱きます。中には「故人様を北枕にするのは、生き返らせないための風習だ」といった誤解も語られることがあります。しかし、これは事実とは異なり、本来の意味から大きくかけ離れています。
仏教における北枕は、故人様を「死の世界に閉じ込める」ためのものではなく、「仏の世界へ導く」ための祈りにほかなりません。お釈迦様が入滅されたときの姿を模倣し、同じように安らかに旅立っていただきたいという尊い願いが込められています。北枕は、故人様を敬い、その成仏を願う心をかたちにしたものなのです。
では、なぜ「縁起が悪い」といわれるようになったのでしょうか。それは、もともと北枕が故人様のための作法であることから、「生きている人がわざわざ真似をするのは不吉」と捉えられるようになったことに由来します。つまり、北枕が持つ本来の意味が正しく伝わらないまま、誤解や迷信として広がってしまったのです。
本来の北枕は、亡き人を想い、安らかに成仏していただくための心づかいです。そこには「生き返らせない」といった否定的な意味は一切ありません。むしろ、ご遺族が故人様の旅立ちに寄り添い、敬意を示す美しい祈りの形といえるでしょう。
【ハタオ葬儀社より】
熊本市で葬儀をお手伝いする私たちは、北枕を「故人様に安らぎを届けるための大切な作法」として捉えています。正しい意味を知ることで、「縁起が悪いのでは」といった不安が解消され、心穏やかにお見送りの準備を進められるはずです。家族葬や一日葬といった形を問わず、故人様とご遺族にとって最も安心できる形でお支えしてまいります。
② 現代の葬儀事情と北枕にまつわる誤解を解く
マンションや住宅事情により、物理的に北枕が難しい現代社会。この章では、北枕に対する正しい理解を深め、柔軟に対応することの重要性をお伝えします。
②-1 仏壇や床の間、水回りとの関係性
ご自宅で故人様を安置する際には、単に「北枕にするかどうか」だけではなく、お部屋の環境や家具との位置関係を考慮することも大切です。特に注意すべきなのは、仏壇や床の間、さらには台所やトイレなどの水回りとの位置関係です。これらは日常生活に根付いた空間でありながら、葬儀においては「敬意を示すべき対象」と「避けるべき対象」に分かれるため、安置の際に配慮が求められます。
まず、仏壇や床の間に頭を直接向けるのは避けるのが一般的です。仏壇は礼拝の対象であり、日々手を合わせる神聖な場でもあります。そこに故人様の頭を向けると「仏様に背を向ける」あるいは「仏壇を足元にする」という誤解を招きかねません。故人様に失礼のないよう、仏壇や床の間に対して頭を向けるのは控えたほうが安心です。
次に、水回りの位置も配慮すべき要素です。台所やトイレ、浴室などは清浄さよりも生活臭や実用性が重視される空間であり、故人様の足を向けるのは「不敬」とされることがあります。そのため、もし北枕にすると水回りの方向へ足が向いてしまう場合には、北枕を優先するのではなく、仏壇や水回りを避ける配置を選ぶのが現実的です。
つまり、「北枕=絶対」ではなく、故人様への敬意を第一に考えるのが本来の安置のあり方です。間取りによっては北枕が叶わないこともありますが、その場合には西枕や斜めに安置するなどの柔軟な対応も許容されます。大切なのは「形式を守ること」ではなく、「ご家族が安心して送り出せる形」を整えることなのです。
【ハタオ葬儀社より】
熊本市や合志市、菊陽町での家族葬においても、北枕を基本としながらも、お部屋の構造や仏壇の配置を踏まえたご提案を行っています。ご遺族が「これで安心だ」と思える安置方法を整えることが、何よりの供養につながります。どのような場合でも、地域の習慣とご家族の想いを大切にしながら、私たちは丁寧にサポートしています。
②-2 無理に北枕にこだわる必要はない
現代の葬儀では、形式よりも故人様やご遺族の気持ちを優先することが大切です。無理に北枕にこだわって、ご遺族が不便を感じたり、心を痛めたりするようでは本末転倒です。故人様への想いを込めて、安らかに休んでいただける場所に安置することが最も重要です。
【ハタオ葬儀社より】 熊本での葬儀、特に家族葬では、ご自宅の環境に合わせて柔軟に対応することが求められます。北枕が難しい場合でも、ご遺族様が心を込めて安置できる最善の方法をご提案いたしますので、どうぞご安心ください。
②-3 北枕は日本独自の風習
北枕という言葉を耳にすると、多くの日本人は「故人様を安置するときの作法」や「生きている人がすると縁起が悪い」というイメージを抱きます。しかし、この考え方は仏教が深く根付いた日本独自の文化的背景によるものです。海外に目を向けると、北枕を不吉とする習慣はほとんど存在しません。むしろ国や地域によっては、方角と睡眠の関係に異なる価値観が見られます。
たとえば、中国をはじめとした風水の世界では、北に頭を向けて眠ることが推奨されることもあります。これは、地球の磁力と体の向きを合わせることで気の流れが安定し、健康や安眠につながると考えられているためです。このように、北枕は必ずしも「不吉」や「死」と結びつけられるものではなく、むしろ良い影響をもたらす方角とされる場合もあるのです。
こうした比較からもわかるように、北枕には科学的・実務的な根拠があるというより、日本人の死生観や宗教観に根差した「文化的な意味合い」が大きいといえます。つまり、北枕は葬儀の作法としては大切に受け継がれてきたものの、それが絶対的な規範ではなく、地域や宗派によって柔軟に解釈されてきた習慣なのです。
現代では、間取りの都合やご遺族の気持ちを優先して安置の向きを決めるケースも多く見られます。大切なのは「北枕を守るかどうか」ではなく、「故人様を敬い、心安らかに送り出したい」というご家族の想いに寄り添うことです。北枕を日本特有の文化として理解しながらも、時代に合わせた柔軟な考え方が求められているといえるでしょう。
【ハタオ葬儀社より】
熊本市で家族葬や葬儀をご検討の際は、故人様やご家族のご意向を第一に考えることが大切です。形式に囚われすぎるのではなく、専門家として最もふさわしい安置方法を一緒に考え、ご遺族が安心して見送れるよう心を込めてお手伝いいたします。
③ 北枕で安置できない場合でも安心できる方法
ご自宅の構造上、どうしても北枕が難しいケースは少なくありません。そんな時でも、故人様を安らかに見送るための適切な安置方法があります。
③-1 北西や北東に頭を向けての安置
ご自宅の間取りや家具の配置によって、どうしても真北に頭を向けて安置できない場合があります。そのような時には、無理をせず北西や北東に少し角度をずらして安置する方法がよく用いられます。北西や北東といった方角は「北」の要素を含んでいるため、北枕の代替として考えられることが多く、ご遺族の心情を尊重した柔軟な選択肢といえます。
大切なのは「正確に北でなければならない」という形式よりも、故人様を敬い、心穏やかに送りたいというご遺族の気持ちです。わずかな角度の違いが問題になることはなく、むしろご家族が納得して安置できることの方が、供養として大切な意味を持ちます。
【ハタオ葬儀社より】
熊本市での家族葬や葬儀の際、ご自宅で安置するにあたり「北枕にできないのでは」と不安に思われる方も少なくありません。私たちはご自宅の間取りや環境を拝見し、ご遺族の気持ちに配慮した最適な安置方法をご提案しています。無理のない形で故人様をお迎えすることが、ご遺族にとっても心の支えとなるのです。
③-2 斎場での安置という選択肢
ご自宅での安置が難しい場合には、葬儀社の専用安置施設や斎場に故人様をお預かりする方法もあります。これらの施設は温度や湿度の管理が整っており、衛生面でも安心できる環境です。特に夏場やご自宅が集合住宅の場合には、施設に安置する方が故人様にとってもご家族にとっても安心といえるでしょう。
また、斎場で安置する場合には、通夜や葬儀の準備も同じ施設内で進められるため、移動の負担が少なくなるという利点もあります。ご遺族にとっては精神的にも体力的にも余裕を持って葬儀に臨むことができ、落ち着いた環境で故人様を見送ることができます。
【ハタオ葬儀社より】
熊本市を中心に、当社では専用の安置室や斎場をご用意しています。ご自宅での安置が難しい場合や不安がある場合には、専門の施設にお預けいただくことで、より良い環境で故人様をお守りすることが可能です。ご家族にとっても安心できる選択肢としてご活用いただけます。
③-3 葬儀社の専門家へ相談する
北枕にまつわる疑問や不安、あるいはご自宅の環境に合わせた安置方法については、専門家である葬儀社に相談するのが最も確実です。地域ごとの慣習や宗派による違い、さらにはご遺族の希望に合わせて、最善の方法を一緒に考えてくれる存在が葬儀社です。
「北枕ができないが大丈夫か」「仏壇の向きと重ならないか」といった小さな疑問も、専門家に相談することで安心に変わります。大切なのは「迷いながら進める」のではなく、「納得のいく形で送り出す」こと。葬儀社に寄り添ってもらうことで、ご家族の心の負担も大きく軽減されます。
【ハタオ葬儀社より】
熊本での葬儀、とくにご自宅での安置に不安をお持ちの方は、どうぞ私たちハタオ葬儀社にご相談ください。地域の慣習やご家族の想いを大切にしながら、故人様にとって最も安らかな環境を一緒に考え、心を込めてサポートいたします。安心してご相談いただけることが、私たちの役割だと考えています。
④ 故人様への想いを込めた安置の重要性
安置は、故人様とのお別れの時間であり、大切な旅立ちの準備期間です。この時間を、ご遺族が後悔なく過ごすためには、形式だけでなく、故人様への想いを込めることが何よりも大切です。
④-1 故人様の安らかな眠りを祈る時間
安置の期間は、故人様が静かに眠り、旅立ちの準備をするための大切な時間です。ご遺族は故人様のおそばで過ごし、思い出を語りかけ、安らかな眠りを祈ります。
④-2 形式よりも気持ちを大切にする
形式に囚われすぎず、故人様が「どんな場所で休みたいか」を考えることも大切です。生前好きだった場所や、心が落ち着く場所に安置することで、故人様への感謝の気持ちを伝えることができます。
④-3 専門家と心を合わせて見送る準備
故人様をどう安置するか、という問題は、ご遺族様だけが抱え込む必要はありません。私たち葬儀の専門家は、ご遺族様の心に寄り添い、故人様への想いを形にするためのお手伝いをいたします。
【ハタオ葬儀社より】 熊本市での家族葬において、私たちはご遺族様が故人様と心を通わせる大切な時間を何よりも尊重します。北枕の意味を理解し、故人様を想う気持ちを込めた安置が、穏やかなお見送りに繋がることをお約束します。
⑤ 熊本での葬儀、北枕に関するご相談は専門家へ
⑤ ハタオ葬儀社よりのまとめ
北枕という習慣は、決して単なる迷信ではありません。仏教の開祖であるお釈迦様が入滅された際の姿に由来し、故人様を安らかに極楽浄土へ導くという深い意味が込められています。北枕には「生き返らせないため」といった誤った解釈も一部で語られますが、本来は敬意と祈りの象徴であり、亡き人を大切に想う心の表れなのです。
とはいえ、現代の住宅事情や間取り、ご遺族の生活環境を考えると、必ずしも真北に安置できるとは限りません。仏壇や水回りとの関係、限られたスペースなど、さまざまな事情の中でご家族は判断を迫られます。そのような場合に無理に形式へこだわる必要はありません。北西や北東に角度を取る、あるいは斎場の安置室を利用するなど、柔軟な選択肢があってよいのです。大切なのは「北枕でなければならない」という形ではなく、「故人様を思い、ご遺族が納得できるかどうか」という心の部分にあります。
私たちハタオ葬儀社は、熊本市をはじめ合志市や菊陽町など地域に根ざし、ご家族の想いを第一に考えたお葬式をお手伝いしてまいりました。北枕や安置の方法について不安を抱える方も多いですが、どうぞご安心ください。専門家として地域の慣習を踏まえながら、ご家族の心に寄り添った最善の方法を一緒に考え、ご提案いたします。
葬儀は故人様を送り出す大切な儀式であると同時に、ご家族にとって心を整える時間でもあります。どんな小さな疑問や不安でも構いません。北枕に限らず、葬儀に関することはどうぞお気軽にご相談ください。安心できる形でお見送りができるよう、私たちが真心を込めてお支えいたします。
⑥ Q&A
Q1:なぜご遺体を北枕にするのですか?
A:仏教の開祖であるお釈迦様が亡くなられた際、頭を北に向けて横たわられた姿に由来します。故人様が安らかに仏の世界へ旅立てるようにという願いが込められています。
Q2:北枕で寝ると縁起が悪いというのは本当ですか?
A:故人様のためである北枕を、生きている人間が真似るべきではないという考えが広まったためです。科学的な根拠や不吉な意味合いはありません。
Q3:自宅の構造上、北枕ができません。どうすればいいですか?
A:真北にこだわらず、北西や北東など少しでも北の方角に頭を向ける、または葬儀社の専用安置施設を利用する方法もあります。ご自宅の状況に合わせてご相談ください。
Q4:北枕の代わりに他の向きでも大丈夫ですか?
A:はい、大丈夫です。無理に北枕にこだわらず、仏壇や水回りとの関係性、そして故人様やご遺族が最も安らげる場所に安置することが大切です。
Q5:家族葬でも北枕は必要ですか?
A:必要不可欠な作法ではありません。ご家族の想いやご希望を優先して、安置の向きを決められることが大切です。
Q6:北枕や安置について、誰に相談すればいいですか?
A:葬儀社の専門家にご相談ください。ご遺族の不安に寄り添い、最適な安置方法を提案してくれます。
⑦ 執筆者・監修者紹介
執筆者:畑尾一心
役職: ハタオ葬儀社 3代目 代表取締役社長
経歴:
1972年、熊本で50年余年続く葬儀店に生まれる。
葬祭業に従事して30年以上。年間約400件を超える葬儀やご相談に携わり、地域密着型で信頼と実績
現在、NPO法人全国葬送支援協議会熊本中央本部代表としても活動中。
厚生労働省認定葬祭ディレクター技能審査 1級葬祭ディレクターとして専門性を持ち、日々の活動の中で葬儀業界に貢献できること目指しています。
一般社団法人 終活協議会の終活セミナー講師や、終活カウンセラー協会の終活カウンセラーとしても活動しており、地域に密着したサービスを提供しています。
想い:
創業者である祖父の想いを引き継ぎ、日本独自の葬送文化の意味を現代に伝え、後悔のないお葬式を大切にし、葬儀業務に取り組んでいます。
「心を込めた葬儀サービス」を提供し、皆様の大切なお見送りをサポートします。
趣味:
散歩が趣味で、近所だけでなく知らない街を歩くことで、地域の人々とのコミュニケーションを楽しんでいます。
監修者:畑尾義興
役職: ハタオ葬儀社 会長
経歴:
昭和30年、熊本で先代畑尾義人により創業されたハタオ葬儀社を引き継ぎ、約40年間経営を行ってきました。
創業者の思い「誰もが誇りと思えるお葬式」を基に経営を引き継ぎ、葬儀業一筋で地元の感謝の気持ちを込めて活動してきました。
自身の葬儀体験から家族の思いが伝わる葬儀を心掛け、心と費用の負担を軽減するお手伝いを大切にしています。
理念:
地域密着型で、皆様にとって温かく、心のこもった葬儀を提供することが、私たちの使命です。
ご遺族様の思いを最優先に、感謝の気持ちを込めた葬儀をお手伝いし、後悔のないお見送りをサポートします。
趣味:
趣味は釣りと囲碁で、熊本の自然や友人との時間を大切にしています。
ハタオ葬儀社は、創業から70年にわたり地域に根差したサービスを提供してきました。私たちの専門家が執筆し、監修したこの内容は、温かい心で故人をお見送りするための指針です。葬儀に関する不安を感じている方々に、しっかりとしたサポートと信頼できる情報を提供いたします。
大切な方への想い、どう伝えられたか。お客様の「声」をご覧ください
【大切な方への想い、どう伝えられたか。お客様の「声」をご覧ください】
【葬儀の「分からない」をもっと解消しませんか?】
【ハタオ葬儀社へのお問い合わせ】
【ご家族のペースで、納得いくまで丁寧なハタオ葬儀社の事前相談】
葬儀場の詳細を見る
公営斎場もご利用になれます

【公営斎場】熊本市斎場
住 所
〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町796
アクセス
熊本市役所から車で、約35分

【公営斎場】菊池火葬場
住 所
〒861-1315 熊本県菊池市木柑子1318
アクセス
阿蘇高原線 三里木駅からタクシー24分

【公営斎場】大津火葬場
住 所
〒869-1233 熊本県菊池郡大津町大字大津110
アクセス
豊肥本線「肥後大津駅」からタクシーで5分