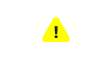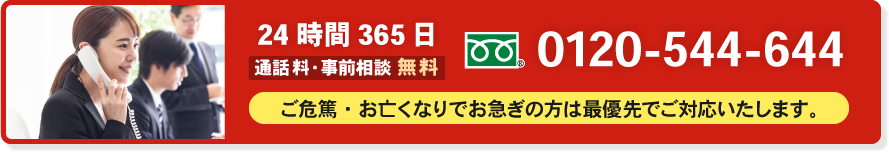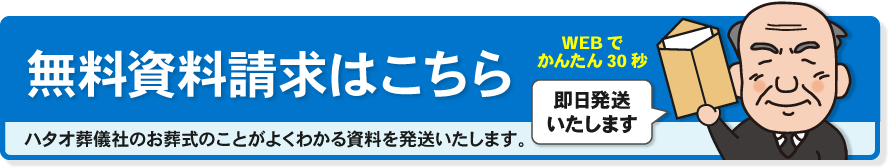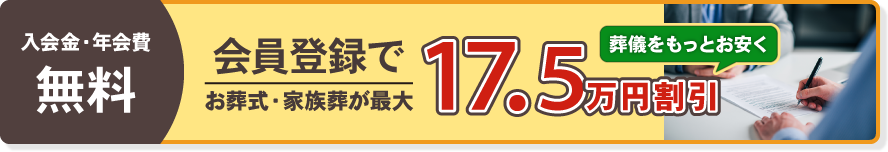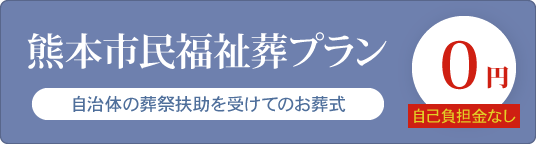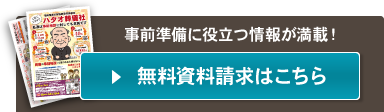新着情報
2025.10.20
【死装束とは?】意味・着せ方(左前の理由)・着物や浴衣の違い・三角頭巾や六文銭まで徹底解説
① はじめに
- 死装束の意味を正しく理解できる
- 左前にする理由と覚え方を解説
- 着物や浴衣などの違いが分かる
- 三角頭巾や六文銭の象徴的な意味を知る
- 熊本市・合志市・菊陽町など地域習慣にも対応
葬儀の準備は、誰もが日常的に慣れているものではありません。特に「死装束」という言葉を耳にしても、どのような衣装なのか、なぜ左前に着せるのか、どのような意味や象徴があるのかは、知らない方がほとんどでしょう。
死装束は、故人様を敬い、安心して旅立っていただくための大切な装いです。着物や浴衣の選び方、三角頭巾や六文銭などの装飾の意味まで、ひとつひとつに深い由来があります。正しい知識を持つことで、ご遺族としても迷いが減り、安心してお見送りの準備ができるのです。
この記事では、初めて死装束に触れる方にも分かりやすく、専門的な観点からその基本と象徴、準備のポイントまでやさしく解説します。心を込めて、大切な方を丁寧に送り出すための知識として、ぜひ参考になさってください。
② このような方へおすすめ
✅ 死装束の意味がよく分からず困っている
✅ 左前にする理由を知りたい
✅ 着物や浴衣のどちらを選ぶのか分からない
✅ 三角頭巾や六文銭の意味を知りたい
✅ 熊本市や合志市、菊陽町など地域の葬儀習慣の情報がほしい
③ 目次
- 死装束とは?意味や由来をわかりやすく解説
- 死装束の正しい着せ方と左前の理由
- 死装束と着物・浴衣・エンディングドレスの違い
- 三角頭巾や六文銭の意味と役割
- 熊本市・合志市・菊陽町の葬儀習慣と死装束の注意点
- まとめ|正しい理解で安心のお見送りを
④ 大切な人を送るときに「正しい方法が分からない…」と悩んでいませんか?
① 葬儀・家族葬における死装束とは?意味や由来を解説
葬儀や家族葬で「死装束」という言葉を耳にすることがありますが、具体的に何を意味するのか、どんな歴史や意味があるのかを知っておくことは、ご遺族が安心して準備を進めるためにとても重要です。ここでは、死装束の基本と由来について、熊本市の葬儀事情も踏まえてやさしく解説します。
①-1 死装束とは何か?仏教・神道における意味
死装束は、故人様を安らかに送り出すために着せる特別な衣装のことです。
- 仏教の場合
白い衣(白装束)を中心に、故人が極楽浄土へ旅立つための清らかな装いとして用います。清浄な白は「生まれ変わり」や「罪を洗い流す」という意味も持ちます。 - 神道の場合
神道では、故人が祖霊として穢れなく旅立つことを願い、白や淡い色の装束を用いることが多く、神事に沿った形で身を清めます。
ポイント:宗派によって衣装の種類や着せ方に違いがありますが、どちらも「故人の魂を尊重し、清らかに送る」という共通の思いが込められています。
①-2 死に装束との違いと、読み方の整理
「死装束」と「死に装束」は混同されることがありますが、実際にはほぼ同じ意味で使われることも多い用語です。
- 死装束(しそうぞく)
一般的に葬儀の文書や式場で用いられる正式な表記です。 - 死に装束(しにしょうぞく)
読み方や地域差により使われることがありますが、意味としては「死装束」と同じく、故人を送るための衣装を指します。
ポイント:熊本市の家族葬では、地域や寺院ごとに呼び方や衣装の細かい差異があるため、葬儀社と確認すると安心です。
①-3 死装束の歴史と由来を知ることで安心できる理由
死装束は、古くから日本の葬送文化に根ざした習慣で、江戸時代には「旅立ちの装束」として広く認知されていました。白い布で身を包むことや、頭巾・六文銭などの象徴物は、故人の魂を迷わせず浄土へ導く意味があります。
- 三角頭巾:邪気を防ぐとされる守りの意味
- 六文銭:冥途の旅の費用としての象徴
由来を知ることで、ただ形式として行うのではなく、「なぜこうするのか」を理解し、安心して故人を送り出す準備ができます。
👉 ハタオ葬儀社担当者より
熊本市での葬儀や家族葬では、宗派や地域の習慣に合わせて、死装束の意味を少しでも知っておくと安心です。衣装や小物には、それぞれ故人を思う気持ちや祈りが込められています。慌てず、落ち着いて整えることで、心を込めて大切な方を見送ることができますよ。
② 葬儀・家族葬で間違えない死装束の着せ方と左前の理由
死装束を着せるとき、特に注意したいのが「左前」に着せることです。普段の着付けとは逆になるため、初めて行う方は戸惑いやすいポイントでもあります。ここでは、左前にする理由や基本的な着せ方、実務で気をつける点をわかりやすく解説します。
②-1 左前にする理由とは?仏教的意味と覚え方
- 左前(ひだりまえ)とは
衣の前身頃の左側が上になる着せ方で、普段の着物の右前とは逆になります。 - 仏教的な意味
左前は「死者専用の着せ方」とされ、故人が現世を離れ、あの世に旅立つ特別な状態を示します。邪気や災いを避け、魂が迷わず浄土へ向かうことを象徴しています。 - 覚え方のコツ
「亡くなった方は左に行く」というイメージを持つと忘れにくく、実際の着せ方でも迷いません。
②-2 縦結び・襟合わせなど着せ方の基本ルール
死装束の着付けには、いくつかの基本ルールがあります。
- 襟合わせ
- 左前にし、衿がきれいに重なるように整える
- 縦結び(たてむすび)
- 帯や紐は縦に結ぶことで、整然とした見た目を作る
- 小物の配置
- 三角頭巾や六文銭などは、中央や適切な位置に置く
- 衣のたるみやしわに注意
- シワや歪みがあると、見た目だけでなく、遺族の安心感にも影響します
②-3 間違えやすいポイントと実務での注意点
- 右前にしてしまう
→ 仏式・神式ともに死者専用の左前が基本。誤ると失礼になる場合があります。 - 帯や紐の結び方が不安定
→ 縦結びにすることで、死装束全体が整い、乱れにくくなります。 - 小物の配置や向き
→ 三角頭巾や六文銭などの象徴物は、位置や向きに注意。寺院の指示に従うと安心です。 - 布の重なりやシワ
→ 遺族が目にするものなので、丁寧に整えることで安心感を提供できます。
👉 ハタオ葬儀社担当者より
熊本市、 合志市での葬儀や家族葬では、死装束の左前は「亡くなった人専用」の着せ方として理解されています。正しい着せ方を知ることで、遺族も安心してお見送りの準備ができます。
③ 葬儀・家族葬で選ぶ死装束の種類|着物・浴衣・エンディングドレス
死装束には、伝統的な着物や浴衣だけでなく、近年ではエンディングドレスや私服に近い衣装を選ぶケースも増えています。故人の人柄や家族の希望に合わせて選ぶことができ、安心してお見送りの準備ができます。ここでは、それぞれの特徴と選び方、宗派・地域の慣習について解説します。
③-1 着物と浴衣の違い|地域や状況での選択
- 着物(白装束)
- 正式な死装束として古くから用いられる
- 生地や柄に格式があり、儀式感を大切にしたい場合に適している
- 仏教・神道どちらでも基本的に使用可能
- 浴衣タイプの白装束
- 布が柔らかく、着せやすい
- 小規模の家族葬や、自宅での葬儀に向く
- 熊本市・周辺地域では、簡略化した家族葬でよく使われるケースも
選び方のポイント
- 式場の広さや家族の人数、地域の慣習に応じて選ぶと安心
- 小規模葬なら浴衣タイプ、正式な式なら着物タイプが無難
③-2 現代的なエンディングドレスや私服のケース
- 最近では故人の個性を反映させるため、エンディングドレスや生前の愛用服を着せる場合も増えています
- 特徴:
- 明るい色や淡い色のドレスも選べる
- 形式にとらわれず、故人らしい最後の姿を大切にできる
- 注意点:宗派や葬儀形式によっては着用が制限される場合があるため、事前に葬儀社に相談
③-3 宗派ごとの違いと熊本での慣習の比較
- 仏教式
- 白装束を基本とし、左前に着せる
- 菊陽町や熊本市周辺では、寺院の指導に従うことが一般的
- 神道式
- 清浄な白や淡色の装束
- 神職による指示に従い、衣装や頭巾を整える
- 地域差
- 熊本市中央区・南区では正式な白装束が多い
- 菊陽町・合志市では、故人の希望や家族の意向に応じて柔軟に選ぶ傾向が強い
👉 ハタオ葬儀社担当者より
菊陽町の家族葬でも、故人の希望に合わせて死装束を選ぶ方が増えています。着物・浴衣・エンディングドレスなど、種類を知ることで、家族も安心してお見送りの準備ができます。
④ 葬儀・家族葬における死装束の小物|三角頭巾や六文銭の意味
死装束には、衣装だけでなく小物にも深い意味があります。三角頭巾や六文銭、杖などの副葬品は、故人のあの世への旅を守り、無事を願う象徴です。ここでは、代表的な小物の意味と役割をやさしく解説します。
④-1 三角頭巾とは?故人の旅立ちを象徴する意味
- 三角頭巾
- 頭を守る布で、故人があの世へ迷わず旅立つことを象徴します
- 邪気や災いから守る意味もあり、昔から葬送儀礼で使われてきました
- 白装束と合わせて着せることで、清浄さと保護の意味を兼ね備えています
④-2 六文銭や杖などの副葬品の役割
- 六文銭
- 冥途の旅費として象徴的に添えられる小物
- 形は地域や寺院によって異なり、熊本市や周辺では六文銭の形を変えて添えることもあります
- 杖
- あの世での旅を支える道具として添えられることがあります
- 特に高齢の方の葬儀で、旅立ちの安全を祈る意味があります
- その他の副葬品
- 故人の人柄や地域慣習に応じて、花や装飾品を添えることもあります
④-3 小物に込められた「無事にあの世へ」の祈り
- 歴史的に、死装束の小物は単なる飾りではなく、故人の魂の安全や安らぎを願うものです
- 三角頭巾や六文銭は「無事にあの世へ行けますように」というご遺族の祈りを象徴しています
- これらの意味を知ることで、準備や着せ方も迷わず行え、安心してお見送りができます
👉 ハタオ葬儀社担当者より
熊本市や周辺地域の葬儀では、六文銭を形を変えて添える習慣もあります。地域や宗派に応じた小物の意味を理解することで、故人に心を込めた準備ができ、ご遺族も安心して家族葬を進められます。
⑤ 熊本市・合志市・菊陽町での家族葬|死装束の地域的注意点
死装束の準備や着せ方は、宗派だけでなく地域の習慣によっても微妙な違いがあります。特に熊本市、合志市、菊陽町では、家族葬を行う際に地域特有の慣習を知っておくことが安心につながります。ここでは、地域ごとの注意点を解説します。
⑤-1 熊本市の葬儀習慣と死装束の扱い
- 熊本市中央区・南区・東区では、葬儀や家族葬において白装束を基本とすることが一般的です
- 左前に着せること、三角頭巾や六文銭などの小物も整えることが重視されます
- 式場の規模や寺院の指導に従い、正しい着せ方を行うことがマナーとして認識されています
⑤-2 合志市・菊陽町の葬儀・家族葬での準備の違い
- 合志市や菊陽町では、故人の希望に応じて衣装や小物の選択が柔軟に行われる傾向があります
- 家族葬や小規模葬が多く、自宅での準備や簡略化された衣装を選ぶケースも増えています
- 地域の寺院や葬儀社のサポートを受けながら、左前や小物の配置など基本は守りつつ、柔軟に対応できることがポイントです
⑤-3 熊本の地域文化と死装束のとは
- 熊本では、伝統的な葬送習慣を尊重する意識が強く、白装束や小物の意味を理解して準備することが安心につながります
- 家族や親族が故人を丁寧に送るという気持ちが、地域文化として大切にされています
- 地域ごとの慣習を踏まえることで、葬儀当日の不安を減らし、安心して家族葬を進められます
👉 ハタオ葬儀社担当者より
地域ごとの習慣を理解して準備することで、家族葬がより安心して進められます。熊本市・合志市・菊陽町では、それぞれの文化や寺院のしきたりに沿った死装束の扱いを知ることが大切です。
⑤ 最後に…なぜ、このようなことをするのか?
日々、死に装束のお手伝いをさせていただく中で、ただの作業ではなく、故人を想う「最後の旅支度」として整えることの大切さを実感しています。衣服を整える一つひとつの動作には、故人への感謝と尊敬の思いが込められています。
私自身も、祖母の死装束を整えた際、これまで家族を支えてくれた感謝の気持ちが自然とあふれ、手や足に触れるたびに心がやすらぐ体験をしました。この瞬間、死装束は単なる形式ではなく、故人への「感謝の気持ちを伝える行為」であると深く理解しました。
家族を送り出す準備は初めての方にとって不安が大きいものです。しかし、信頼できる専門家の支えがあれば、手順や衣装の選び方に迷うことなく、安心して整えることができます。迷ったときは、一人で抱え込まず、ぜひ相談できる先を持ってください。故人に心を込めて旅支度を整えることで、遺族の心もやすらぎ、後悔のないお見送りが実現できると思います。
⑥ Q&A
1. 死装束とは何ですか?
死装束とは、故人を葬儀の際に包む特別な衣装で、故人の「最後の旅支度」として着せられます。白装束が一般的で、故人の魂を清浄に保ち、あの世への旅路を守る意味があります。仏教・神道のどちらの宗派でも、衣装や小物を通して故人への敬意や感謝を表します。
2. なぜ死装束は左前にするのですか?
死装束は、普段の着物と逆の「左前」に着せます。
- 意味:左前は「亡くなった方専用」の着せ方で、故人が現世を離れ、あの世へ安全に旅立つことを象徴します。
- 覚え方:「亡くなった方は左に行く」とイメージすると忘れにくく、実務でも迷わず着せることができます。
3. 死装束は着物と浴衣どちらが一般的ですか?
- 着物タイプ:正式な葬儀や寺院での家族葬では一般的。格式があり、伝統的な雰囲気を重視できます。
- 浴衣タイプ:自宅葬や小規模な家族葬で用いられることが多く、柔らかく着せやすいです。
熊本市や周辺地域では、式場の形式や規模に応じてどちらも使われます。正式な場合は着物タイプ、簡略化した家族葬なら浴衣タイプが選ばれることが多いです。
4. 三角頭巾や六文銭にはどんな意味がありますか?
- 三角頭巾:故人の頭を守り、あの世への旅を邪気から守る象徴です。
- 六文銭:冥途の旅費として象徴的に添えられます。地域や寺院によって形を変えて使うこともあります。
- 杖やその他小物:旅路を支える、無事にあの世へ行けるよう祈る意味があります。
5. 熊本市や合志市の家族葬では死装束に違いがありますか?
- 熊本市:伝統的な白装束が多く、左前や小物の配置も正式に行われます。
- 合志市・菊陽町:小規模な家族葬が多く、故人の希望に応じて衣装や小物を柔軟に選ぶ傾向があります。
- 共通点:左前や小物の意味は変わらず、宗派や地域の慣習に沿った準備が大切です。
6. 好きな服を死装束にしても良いですか?
はい、故人の希望や個性を尊重する場合は可能です。
- エンディングドレスや生前愛用していた服を死装束として用いるケースも増えています。
- 宗派や葬儀形式によっては制限があることもあるため、事前に葬儀社や寺院に相談すると安心です。
⑦ 執筆者・監修者紹介
-
執筆者:畑尾一心
- 役職: ハタオ葬儀社 3代目 代表取締役社長
- 経歴:
1972年、熊本で50年余年続く葬儀店に生まれる。
葬祭業に従事して30年以上。年間約400件を超える葬儀やご相談に携わり、地域密着型で信頼と実績
現在、NPO法人全国葬送支援協議会熊本中央本部代表としても活動中。
厚生労働省認定葬祭ディレクター技能審査 1級葬祭ディレクターとして専門性を持ち、日々の活動の中で葬儀業界に貢献できること目指しています。
一般社団法人 終活協議会の終活セミナー講師や、終活カウンセラー協会の終活カウンセラーとしても活動しており、地域に密着したサービスを提供しています。 - 想い:
創業者である祖父の想いを引き継ぎ、日本独自の葬送文化の意味を現代に伝え、後悔のないお葬式を大切にし、葬儀業務に取り組んでいます。
「心を込めた葬儀サービス」を提供し、皆様の大切なお見送りをサポートします。 - 趣味:
散歩が趣味で、近所だけでなく知らない街を歩くことで、地域の人々とのコミュニケーションを楽しんでいます。 -
監修者:畑尾義興
- 役職: ハタオ葬儀社 会長
- 経歴:
昭和30年、熊本で先代畑尾義人により創業されたハタオ葬儀社を引き継ぎ、約40年間経営を行ってきました。
創業者の思い「誰もが誇りと思えるお葬式」を基に経営を引き継ぎ、葬儀業一筋で地元の感謝の気持ちを込めて活動してきました。
自身の葬儀体験から家族の思いが伝わる葬儀を心掛け、心と費用の負担を軽減するお手伝いを大切にしています。 - 理念:
地域密着型で、皆様にとって温かく、心のこもった葬儀を提供することが、私たちの使命です。
ご遺族様の思いを最優先に、感謝の気持ちを込めた葬儀をお手伝いし、後悔のないお見送りをサポートします。 - 趣味:
趣味は釣りと囲碁で、熊本の自然や友人との時間を大切にしています。 - ハタオ葬儀社は、創業から70年にわたり地域に根差したサービスを提供してきました。私たちの専門家が執筆し、監修したこの内容は、温かい心で故人をお見送りするための指針です。葬儀に関する不安を感じている方々に、しっかりとしたサポートと信頼できる情報を提供いたします。
- 大切な方への想い、どう伝えられたか。お客様の「声」をご覧ください
-
【大切な方への想い、どう伝えられたか。お客様の「声」をご覧ください】
-
【葬儀の「分からない」をもっと解消しませんか?】
-
【ハタオ葬儀社へのお問い合わせ】
-
【ご家族のペースで、納得いくまで丁寧なハタオ葬儀社の事前相談】
葬儀場の詳細を見る
公営斎場もご利用になれます

【公営斎場】熊本市斎場
住 所
〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町796
アクセス
熊本市役所から車で、約35分

【公営斎場】菊池火葬場
住 所
〒861-1315 熊本県菊池市木柑子1318
アクセス
阿蘇高原線 三里木駅からタクシー24分

【公営斎場】大津火葬場
住 所
〒869-1233 熊本県菊池郡大津町大字大津110
アクセス
豊肥本線「肥後大津駅」からタクシーで5分