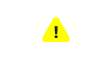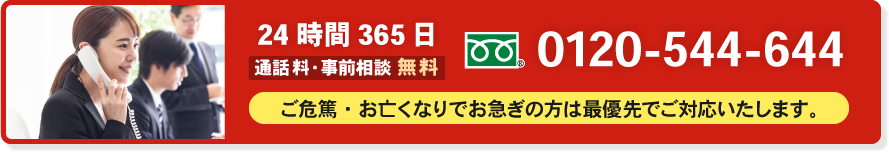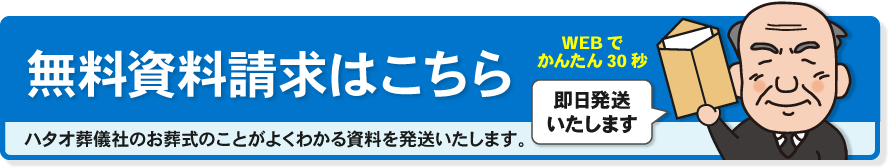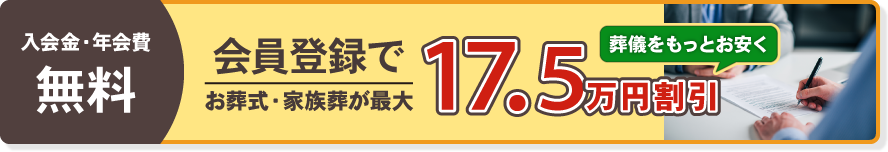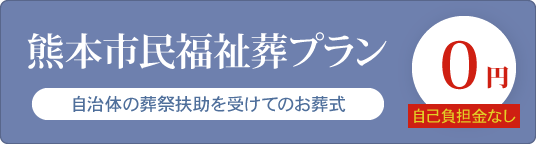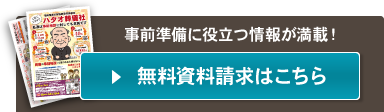スタッフブログ
2025.03.10
3月10日を迎えて 「二度と起きないで」—— 大空襲の犠牲者を悼む法要
3月10日を迎えて
皆さま、こんにちは畑尾一心です。
ハタオ葬儀社のスタッフブログをご覧いただき、ありがとうございます。本日3月10日は、私たちにとって決して忘れてはならない日の1日です。
戦争により多くの命が失われて日です。
1945年のこの日、東京大空襲が発生し、多くの尊い命が奪われました。日本の歴史の中でも10万人を超す多くの民間人が一夜にして犠牲となったこの出来事は、戦争の悲惨さを私たちに深く刻み込んでいます。戦後79年が経過した今も、あの夜の惨劇を語り継ぎ、二度と同じ悲劇を繰り返さないことを誓う日でもあります。
「二度と起きないで」—— 大空襲の犠牲者を悼む法要
本日、東京都内では東京大空襲の犠牲者を追悼する法要が行われました。秋篠宮さまをはじめ、多くの関係者や遺族の方々が参列し、犠牲者の冥福を祈りました。
この法要では、参列者一人ひとりが戦争の悲劇を振り返り、「二度とこのようなことが起きないように」との願いを込めて黙祷を捧げました。遺族の方々の中には、「あの日のことは一生忘れられない」と語る方も多く、戦争の記憶が今もなお人々の心に深く刻まれていることを感じました。
東京大空襲の被害を受けた方々の中には、家族を失いながらも懸命に生き抜いてきた方も多くいらっしゃいます。彼らの証言や、残された手記を通じて、私たちは戦争の悲惨さを学び、平和の大切さを再認識することができます。
熊本にもあった空襲の記憶
東京大空襲の陰に隠れがちですが、熊本もまた戦火の影響を強く受けました。1945年7月には熊本大空襲が発生し、市街地が30%が焼き尽くされ、多くの命が奪われました。熊本城をはじめとする歴史的建造物も被害を受け、戦争の悲劇は全国各地に広がっていました。
熊本で空襲を経験した方々の中には、家族と離れ離れになったり、突然の攻撃で大切な人を失った方も多くいました。戦後、熊本の街は復興を遂げましたが、その傷跡は今も人々の記憶に刻まれています。こうした歴史を知ることで、私たちは戦争の恐ろしさを改めて実感し、平和の大切さを再認識できるのではないでしょうか。
祖父の教え——今を生きることの大切さ
私の祖父も戦争を経験し、戦後の苦しい時代を生き抜いてきました。祖父はよく、「戦争で先に逝った仲間や家族の分まで、今を生きる私たちが精いっぱい生きることが大切なんだ」と話していました。
祖父は多くの友人や家族を戦争で失いましたが、決して憎しみや恨みを口にすることはありませんでした。それよりも、「生きていることそのものが奇跡なんだ。だからこそ、毎日を大切にし、感謝の気持ちを持って過ごすことが、亡くなった人たちへの何よりの供養になる」と教えてくれました。
祖父の言葉は、私にとって今も心の支えになっています。日々の忙しさの中でつい忘れがちになりますが、命を与えられた私たちは、亡くなった方々の分まで精いっぱい生きることが求められているのかもしれません。
戦後復興と家族の絆
戦争は、多くの人々に悲しみと苦しみをもたらしました。愛する家族を失い、大切な故郷が焼け野原となる中、それでも人々は前を向き、生き抜く力を持ち続けました。戦後の日本には、失ったものが多くありましたが、同時に「これからを生きる人々のために」「家族のために」という強い思いがありました。
私の祖父もまた、戦争で家族を失い、大きな悲しみを抱えながらも、「生き残った私たちが、できることをしていこう」と決意し、懸命に働きました。食べるものも十分ではなく、寒さに耐えながらの生活。それでも、家族の存在が支えとなり、共に助け合いながら生き抜いてきました。
そのような時代を経て、日本は復興を遂げ、私たちは今、平和な日々を過ごしています。この日常があるのは、戦後の苦しい時代を乗り越え、懸命に生きた人々のおかげです。その人達は、「家族がいるから頑張れる」「支え合うことで前に進める」と信じ、互いに手を取り合いながら歩んできました。
時代は変わり、便利な世の中になりましたが、家族の絆の大切さは変わりません。忙しい日々の中で、家族と過ごす時間が減ってしまうこともあるかもしれません。でも、どんな時も「家族がいる」ということが、心の支えとなり、生きる力になります。
一緒に食卓を囲むこと、何気ない会話を交わすこと、感謝の気持ちを伝えること。それらのひとつひとつが、家族の絆を深め、温かい心を育んでいきます。戦後の人々が大切にしてきた「支え合う気持ち」を、私たちも忘れずに、これからの時代を生きていきたいものです。
これからも、家族とともに笑い合い、支え合いながら、あたたかな毎日を紡いでいきましょう。
次の世代に伝えたいこと
戦争の記憶が少しずつ薄れていく今、私たちはどのように平和の大切さを伝えていけばいいのでしょうか。戦争を経験した世代が少なくなり、過去の出来事が遠いものになりつつあるからこそ、今を生きる私たちがしっかりと学び、伝えていくことが大切だと思います。
平和の大切さを伝える方法は、学校の勉強だけではありません。お家で家族と話をすることも、とても大切な学びになります。たとえば、おじいちゃんやおばあちゃんが戦争中にどんな暮らしをしていたのかを子供たちに話を聞かせています。当時のことを知っている人の言葉は、教科書や本で読むよりも、ずっと心に残るものです。
また、年に1回は戦争のことを学べる場所に行ってみるのもおすすめです。知覧飛行場、広島や長崎の原爆資料館、沖縄のひめゆり平和祈念資料館などでは、戦争が人々の暮らしにどんな影響を与えたのかを知ることができます。実際に当時の写真や遺品を見たり、戦争を経験した方のお話を聞いたりすると、「戦争ってこんなに怖くて、悲しいものだったんだ」と実感することができます。
本や映画を通して学ぶこともできます。「はだしのゲン」や「火垂るの墓」などの作品は、戦争がどれほど大変だったのかを伝えてくれますし、「この世界の片隅に」では、戦時中の人々の暮らしがどのようなものだったのかを知ることができました。こうした物語に触れることで、戦争は過去の出来事ではなく、今の私たちにも大切な意味を持つことを感じることができます。
でも、何よりも大切なのは、「今ある日常のありがたさ」に気づくことかもしれません。ごはんを食べること、家族と過ごすこと、安心して眠れること――これらはすべて、平和だからこそできることです。当たり前に思える毎日も、決して当たり前ではないのです。戦争を経験した人たちがどれほど大変な思いをしたのかを知ると、今の暮らしがどれほど恵まれているのか、改めて感じられるのではないでしょうか。
私たちができることは、小さなことかもしれません。でも、日々の暮らしの中で「ありがとう」と言うこと、身近な人を大切にすること、思いやりを持って過ごすこと――そうした積み重ねが、平和を守る一歩になるのではないかと思います。
「戦争を繰り返さないように」――その願いを次の世代へ伝えていくことが、今を生きる私たちの大切な役目なのかもしれません。
未来への願い
戦争によって失われた多くの命。その悲しみを胸に刻み、私たちは「平和な未来を築く」ことを考え続けなければなりません。命の大切さを伝え、家族や友人との絆を深めることが、平和への第一歩です。
私たち葬儀という仕事は、命の尊さを実感する場に日々立ち会っています。だからこそ、「いま、目の前にいる大切な人を想うこと」の重要性を、皆さまと共有したいと考えています。
3月10日という日を通じて、改めて命の重みを考え、平和の尊さを胸に刻む。そんな一日になれば幸いです。
ハタオ葬儀社は、これからも皆さまの大切な時間を支え、安心してお別れができるようお手伝いをしてまいります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
執筆者 監修者
執筆者:畑尾一心
創業昭和30年 熊本県儀式共済株式会社
ハタオ葬儀社 3代目 代表取締役社長
1972年、熊本で50年余年続く葬儀店に生まれる。
葬祭業に従事して30年
現在、年間約400件を超えるご葬儀、ご相談に携わっています。
NPO法人全国葬送支援協議会熊本中央本部 代表
厚生労働省認定葬祭ディレクター技能審査 1級葬祭ディレクター
一般社団法人 終活協議会 終活セミナー講師 終活ガイド資格3級
一般社団法人 終活カウンセラー協会 終活カウンセラー
創業者、会長の想いを引き継ぎながら
日本独自の葬送文化の意味を現代の意味を感じて頂き
後悔の無いお葬式を大切に葬儀の仕事に取り組んでいます。
趣味は、散歩。近所はもちろん、知らない街をあることで
その地域に住む人たちとのコミュニケーションを楽しんでいます。
葬儀場の詳細を見る
公営斎場もご利用になれます

【公営斎場】熊本市斎場
住 所
〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町796
アクセス
熊本市役所から車で、約35分

【公営斎場】菊池火葬場
住 所
〒861-1315 熊本県菊池市木柑子1318
アクセス
阿蘇高原線 三里木駅からタクシー24分

【公営斎場】大津火葬場
住 所
〒869-1233 熊本県菊池郡大津町大字大津110
アクセス
豊肥本線「肥後大津駅」からタクシーで5分